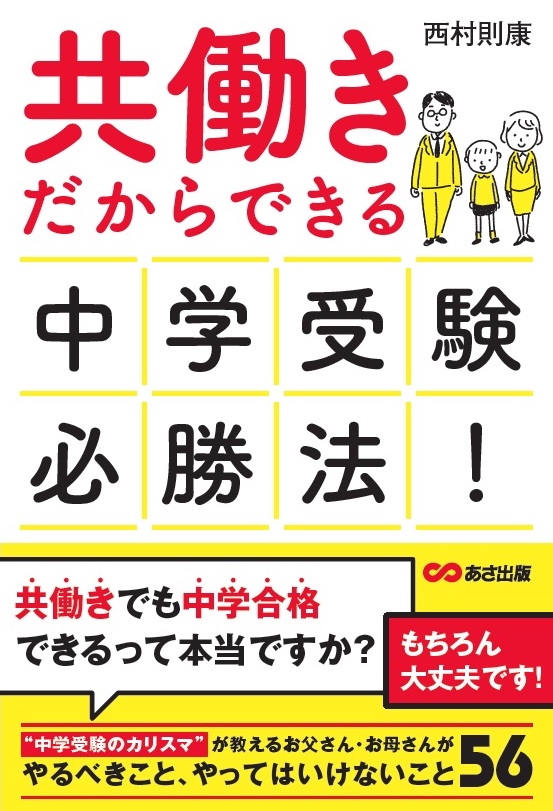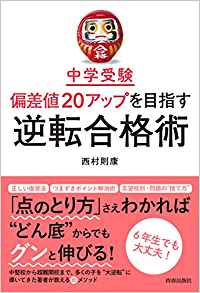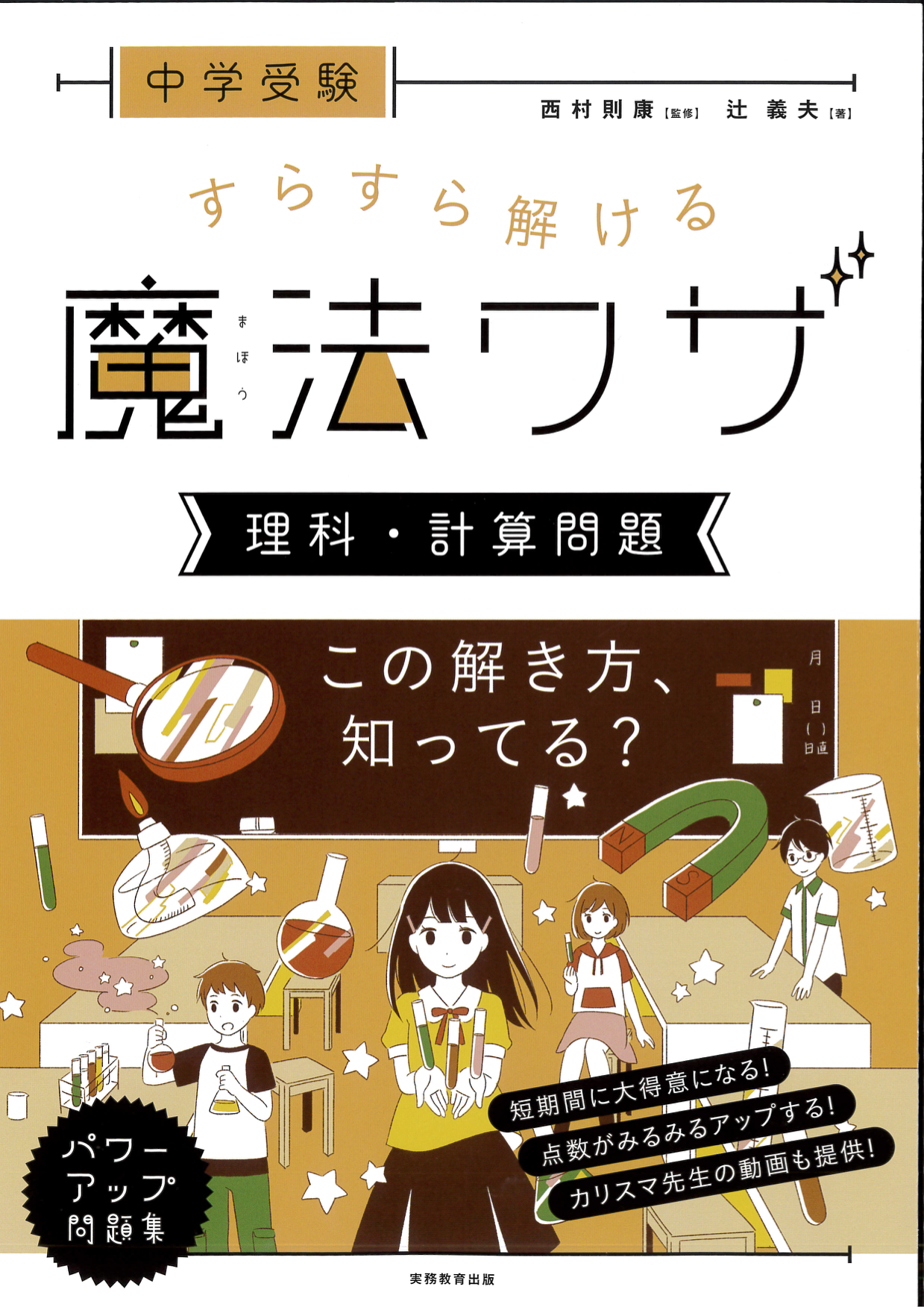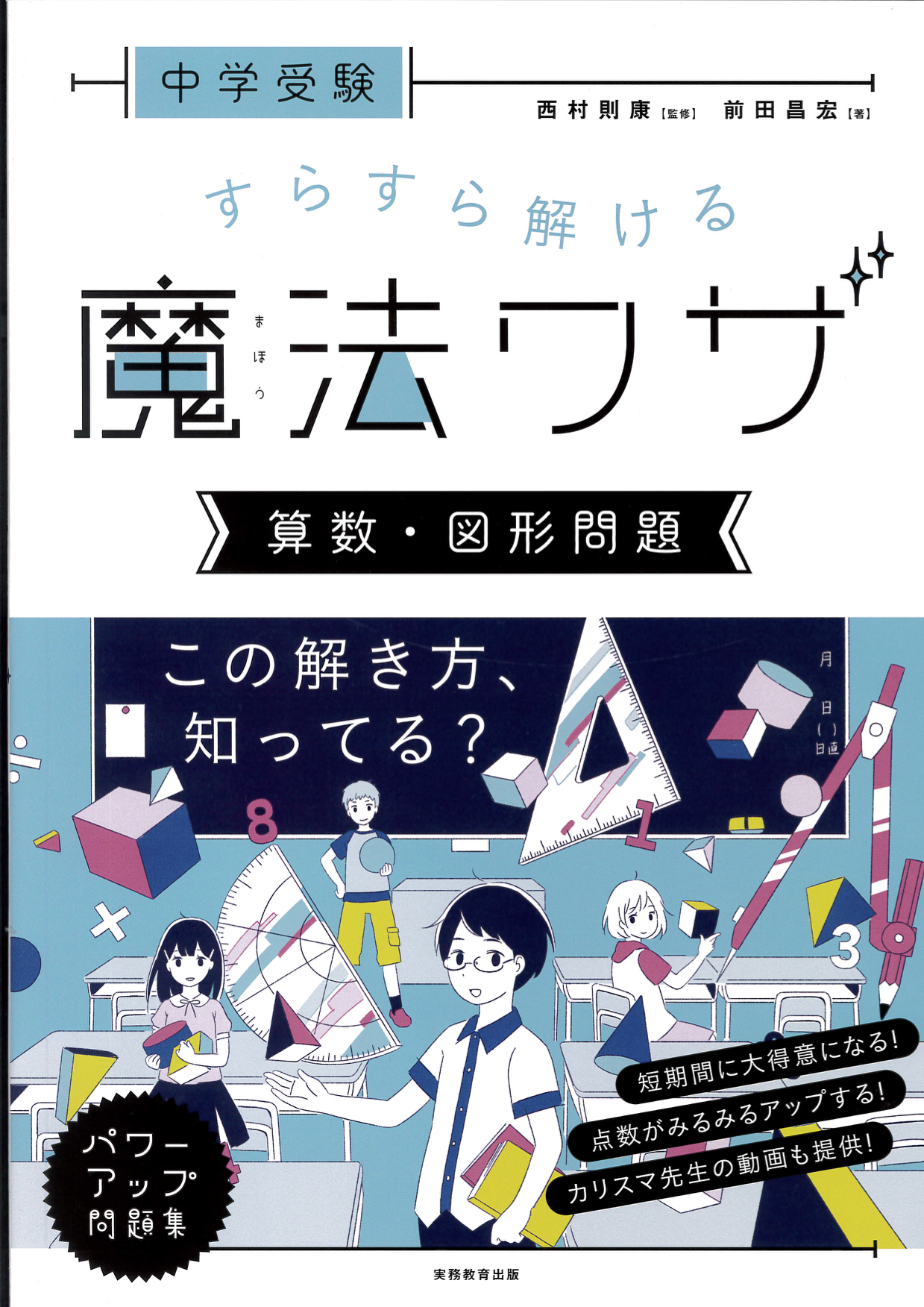目次
デジタル教材と生成AIの現状
AIやデジタル教材を使うメリット
メリットがあればデメリットも存在する
AIはあくまでも「自分で考える」ためのツール
話題のチャットGPTやデジタル教材などのAIツール。
中学受験生の皆さんは学習に活用したり、それら(もしくは「彼ら」)と会話をしたりしたことはありますか?
デジタル教材と生成AIの現状
2025年5月8日、新興出版社啓林館が小学生の約55%が家庭学習でデジタル教材を使用していることを発表しました。(保護者327名を対象とした調査より)
中でも小学生がよく使用しているデジタル教材は、一位が「タブレット学習アプリ」(68.1%)、ついで「教育用ゲームアプリ」(30.8%)、三位が電子書籍・ドリル(27.5%)で、それらを利用する理由としては「楽しく学べるから」という回答が多かったそうです。
2019年にスタートした文部科学省のGIGAスクール構想を背景に、近年さらにタブレットやチャットGPT、アプリなどを使用したデジタル学習の普及が進んでいます。
しかし、便利で楽しい反面、これらを用いることにさまざまな不安や迷いを抱いている中学受験生の皆さんや親御さんも多いのではないでしょうか。
実際、生成AIを扱う各社の利用規約では、多くの場合、小学生の利用を「対象外」あるいは「保護者の同意のもと」に限定しています。
そこで今日はデジタル学習や、デジタル教材や生成AIを学習に用いることのメリット・デメリットを考えてみましょう。
AIやデジタル教材を使うメリット
まずメリットには、デジタル教材やAIを日常的に使うことによる情報活用能力の向上、そして何よりスピードと利便性がありますね。
分厚い教科書を何冊も持ち歩かずとも、気軽にいつでもどこでも学習したり、わからないことを一瞬で調べたりすることができますし、気になる分野をドリル的に演習するために、似通った問題を大量に集めることも実に簡単です。
また、アプリ系のデジタル教材は音や映像やゲーム要素などが加わり、通常の紙テキストよりも楽しく学べるかもしれませんし、AIは大量のデータを基に分析することに長けているので、学習履歴や到達度といったスタディ・ログから一人一人に最適な学習内容・指導方法を分析するなど、教育の質の向上に役立つことが期待できます。
ためしに夏休みの定番である読書感想文の作成をAIに促せば、これまで毎年何時間も机に向かって必死にやっていたのがバカらしくなるほど、瞬時にそれなりのものが作成されることに驚くでしょう。
(もちろん、生成AIからの抽出物をそのまま自分の成果物として使用することは、自分のためにならないこと、また使用方法によっては不適切又は不正な行為になることを理解しておくことが大切です)
もはや、私たち人間は記憶力や単純な文章作成力、作業スピードではAIに太刀打ち出来ません。
ですから、そのような力が必要な場面ではAIを大いに活用し、今後皆さんの生活や学習に積極的に役立てるのが普通のことになっていくと思います。
メリットがあればデメリットも存在する
しかし、気がかりな点もたくさんあります。
まず、物理的に長時間画面を見つめ続けることが、成長期の皆さんの目の健康や正しい姿勢の維持に悪影響を及ぼす可能性があります。
実際それらを使っているご家庭からは、
「タブレット学習で記憶した内容は直後のテストには効果的だけれど、なぜかすぐ忘れてしまう」
「その場では解けるようになっても、角度を変えた問題が出題されると解けない」
「筆圧が弱くなった」
「視力が落ちた」
「ゼロから自分の力で文章を書くことが億劫になった・出来なくなった」
など、様々な困り事をよく耳にしています。
また生成AIで調べ物などをする場合、AIが何に注目し、どのように分析したり判断をしたりした上で結果を導き出したかは見えづらいため、思考のプロセスを学ぶ機会が失われやすくなってしまう可能性があります。
AIの間違った回答(統計的にそれらしい応答ではあるが正しくない情報)も鵜呑みにしてしまうのではないか、という不安もありますね。
心も身体も発展途上である子どもたちへの健康被害や、「考える力」「学ぶ意思」を育む上で困難がある可能性が存在する点は、やはり見逃せない懸念事項です。
AIはあくまでも「自分で考える」ためのツール
私たちはAIツールがあくまでも「自分で考える」ための「ツール」であることを忘れず、それらを活用する際の事実確認(ファクトチェック)のやり方や重要性を身につけておくことが大切ですし、メインは紙の教材にして、補助的にデジタル教材などのAIツールを使用するなど、身体への負担についても注意深く配慮していきたいものです。
これはお子さんに限ったことではありませんが、AIの言いなりになってしまわぬように、さまざまなことに対して「自分ごと」として真剣に向き合う姿勢でいなければ、あっという間にAIに「使われる」ようになってしまったり、これまで私たちが当たり前に持っていた能力や意欲を奪われてしまったりすることでしょう。
中央大学の杉山直学長は学生たちの卒業式で、生成AIで作成した祝辞をあえて読み上げました。
そして、それについて「もっともらしいけど空虚」と切り捨て、「人は人にしかできないことに挑んでいくことが求められる」と、改めて卒業生らを激励しました。
すでにずいぶん前から、特に名門と言われるような学校の入試では、知識の蓄積だけを問うものではなく、学校や塾では誰も聞いたことや習ったことがないような、柔軟な思考力や創造力を問う問題が扱われるようになってきています。
技術の発展を拒絶する必要はなく、むしろ私たち人間はAIの力を大いに、積極的に「使い」つつ、人間が武器とする、人間だからこそ発揮できるプロデュース力や編集力という分野については、ますますその力を研鑽していく、というのが理想なのではないでしょうか。
そしてその要・基盤となるのが、自分が絶対的に信頼を置ける【身体感覚】や【知性】であり、【創造力】だと私は考えています。
これを読んでくれている中学受験生の皆さんが、そのような力を持った、これからの世の中をつくっていく人に成長されることを、今からとても楽しみにしています。
受験相談・体験授業お申込み
必須の項目は必ず入力してください。

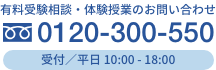
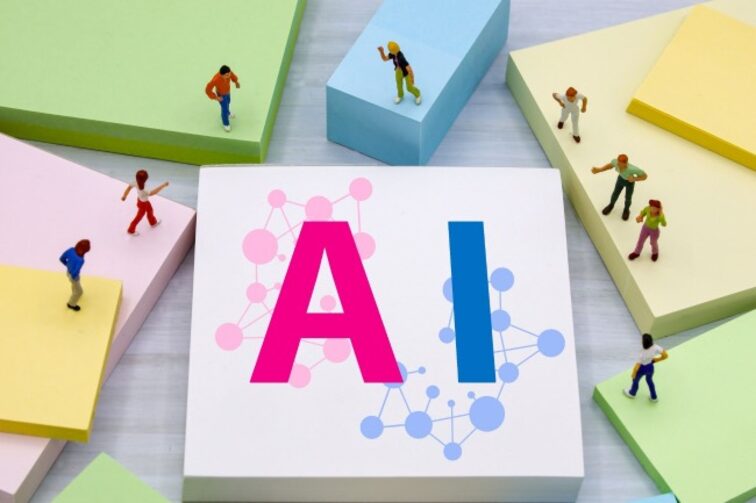

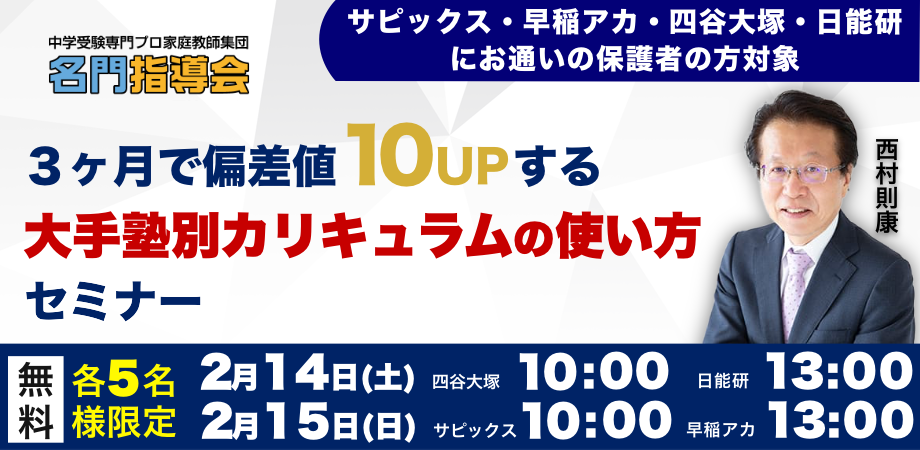
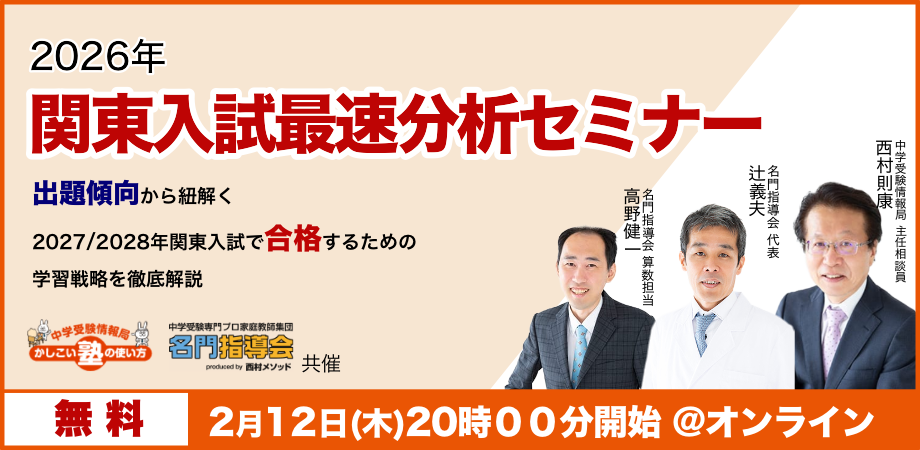
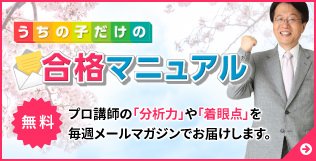



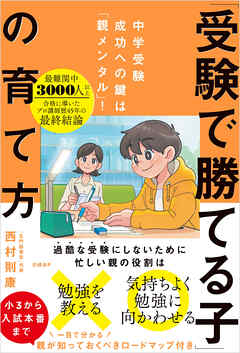
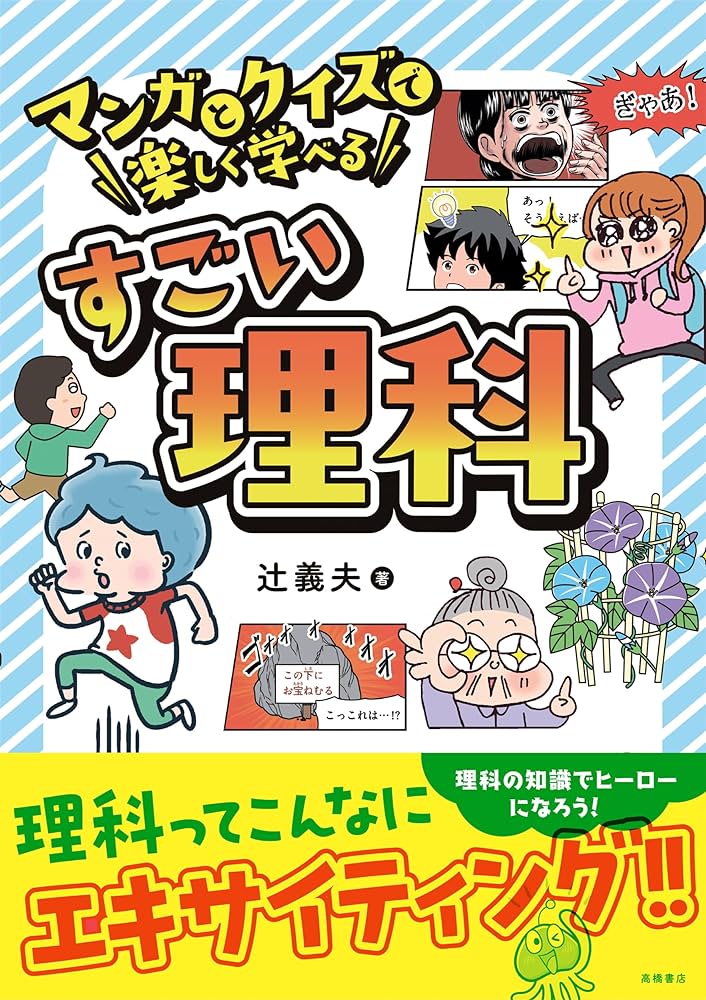
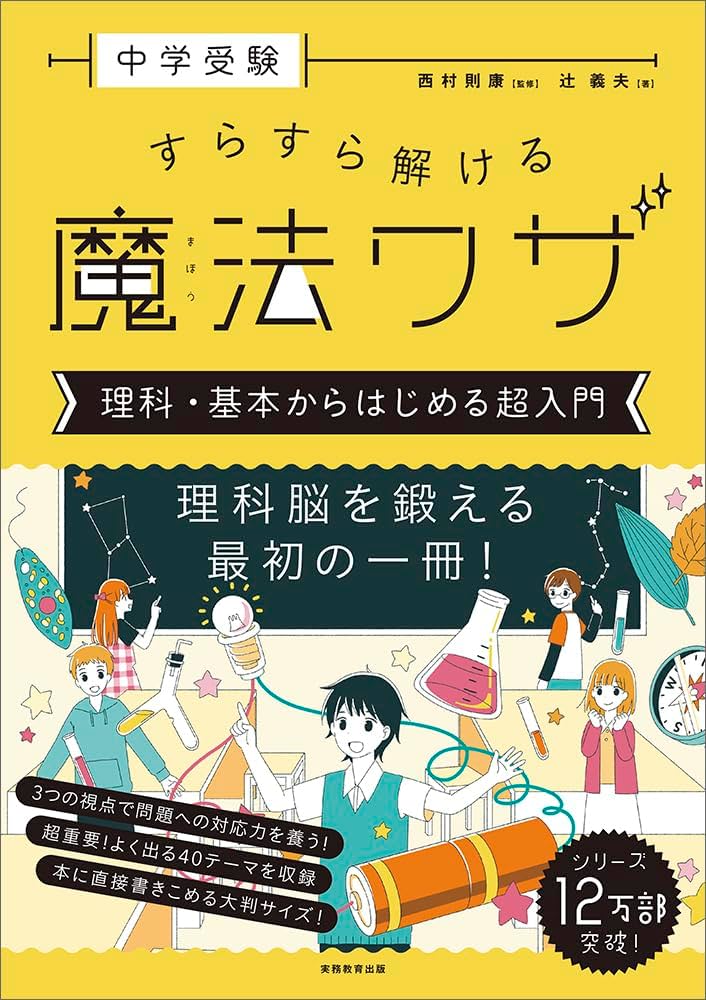
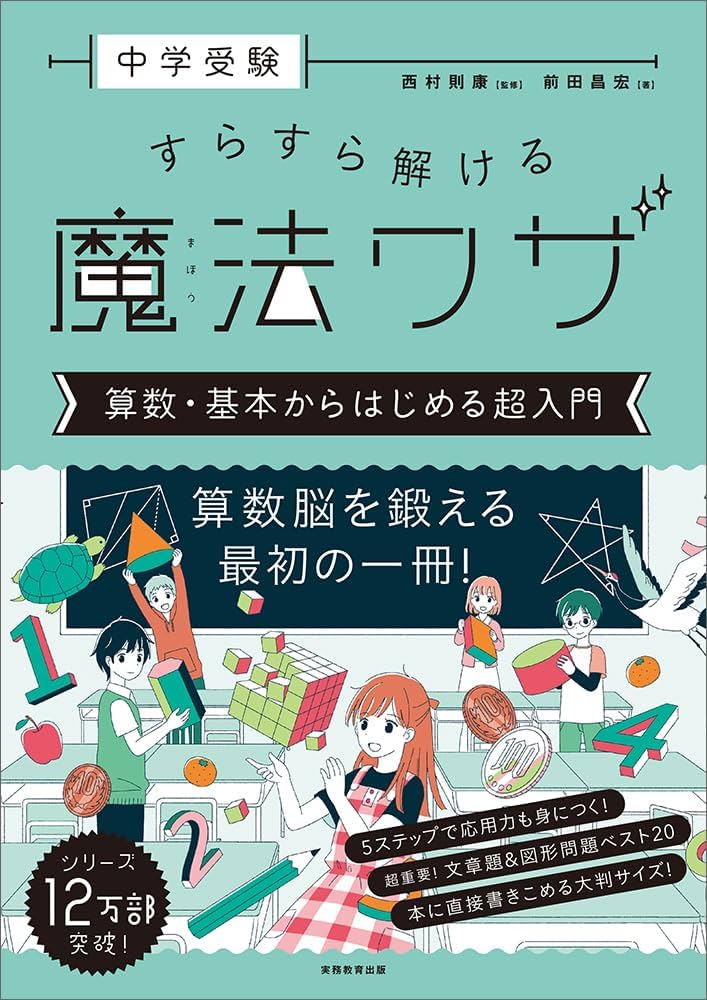
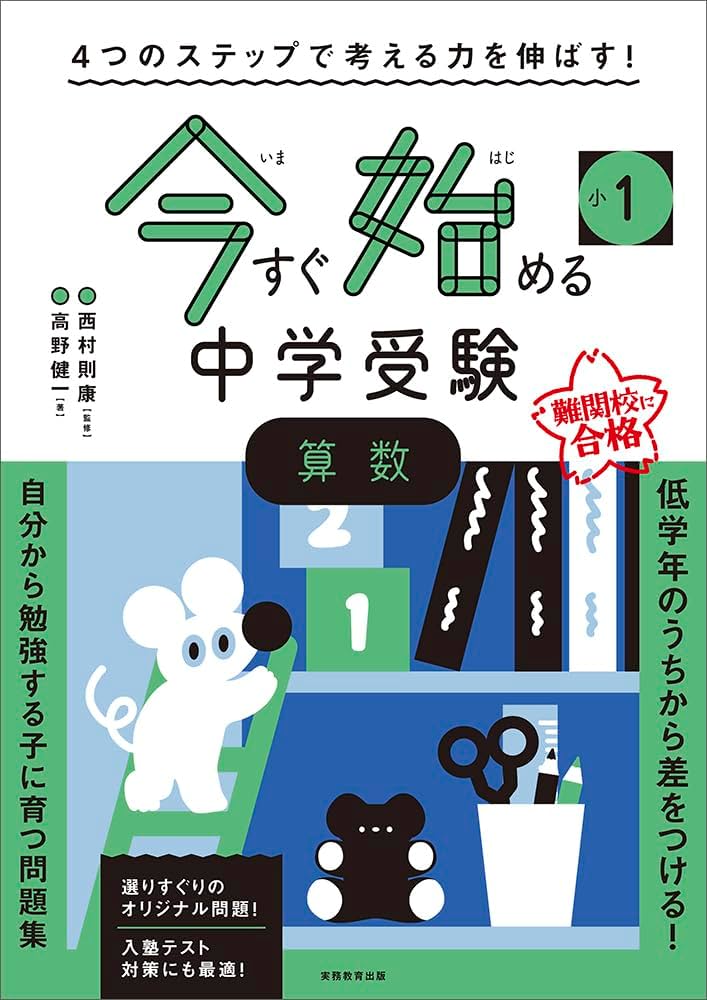
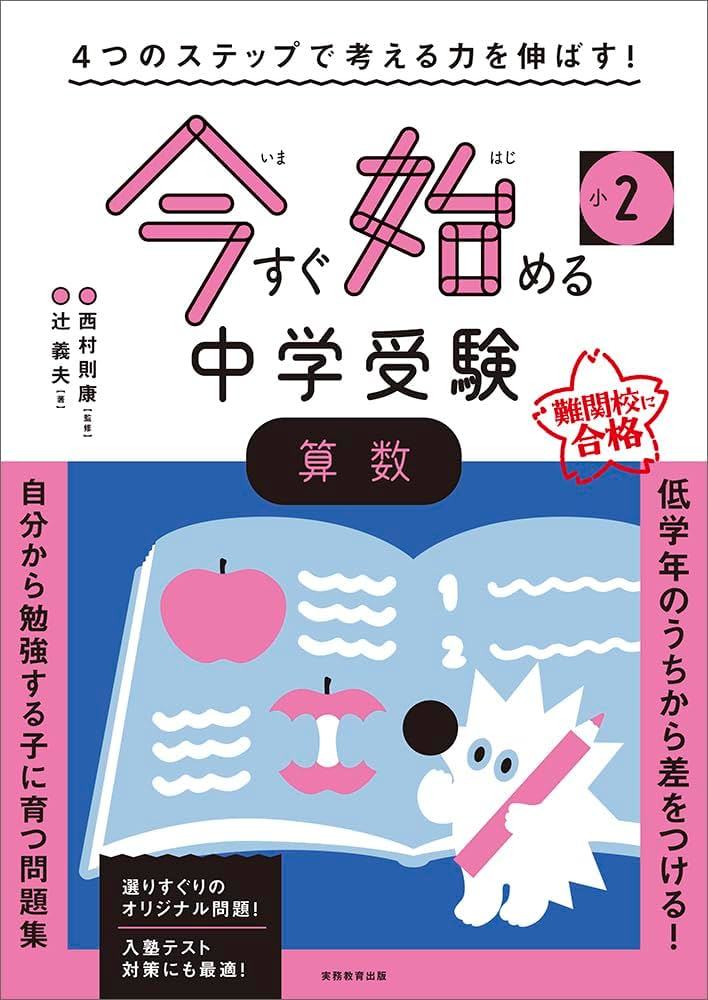
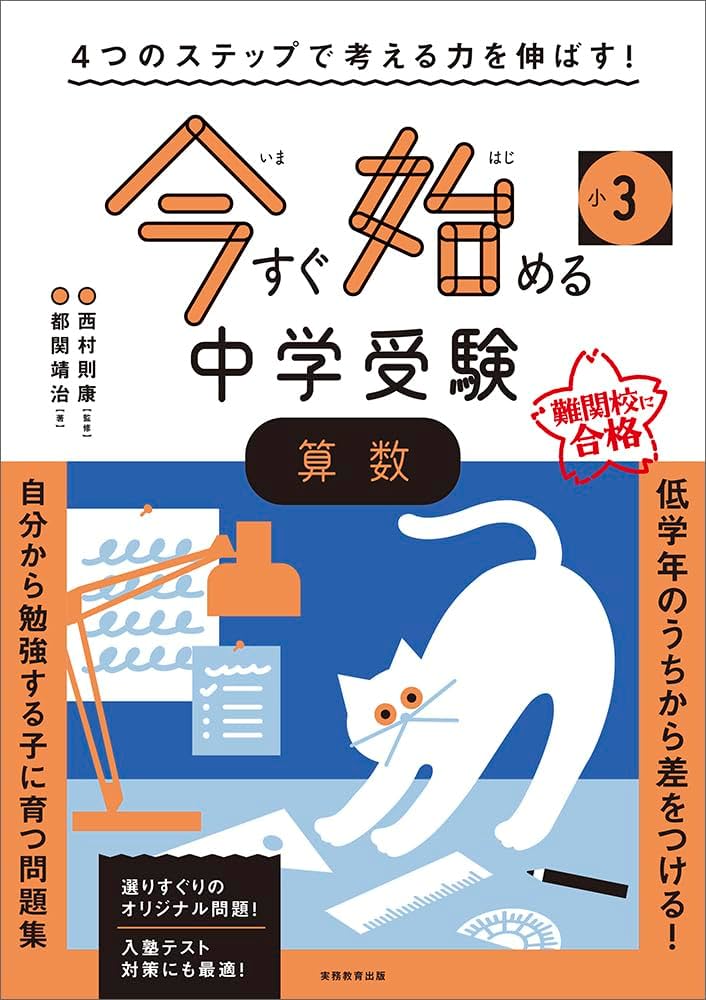
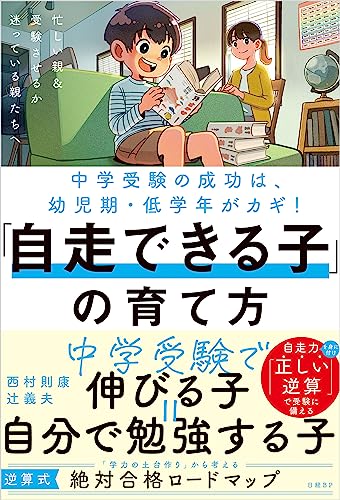
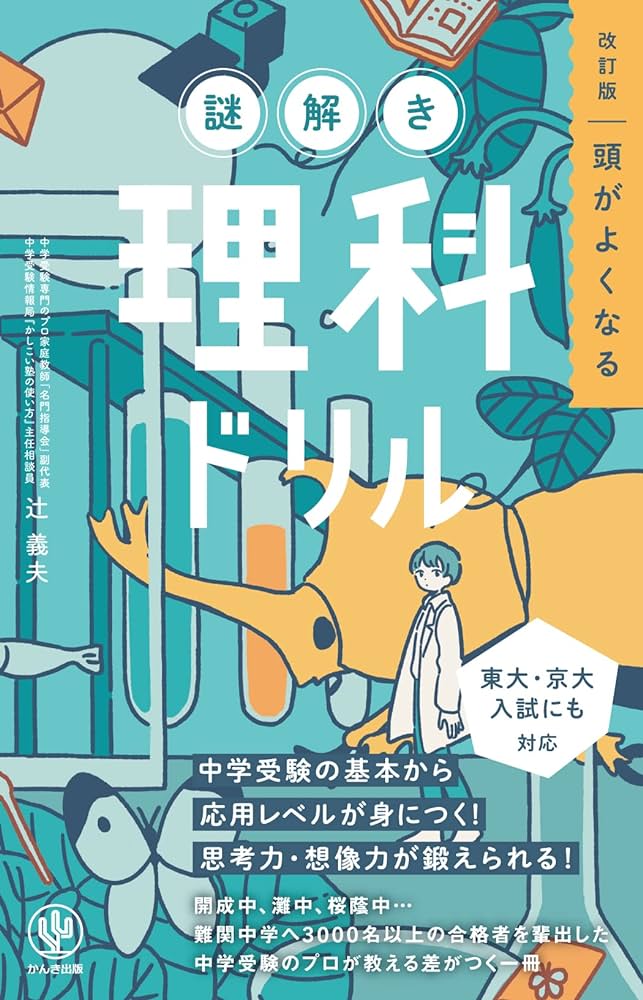
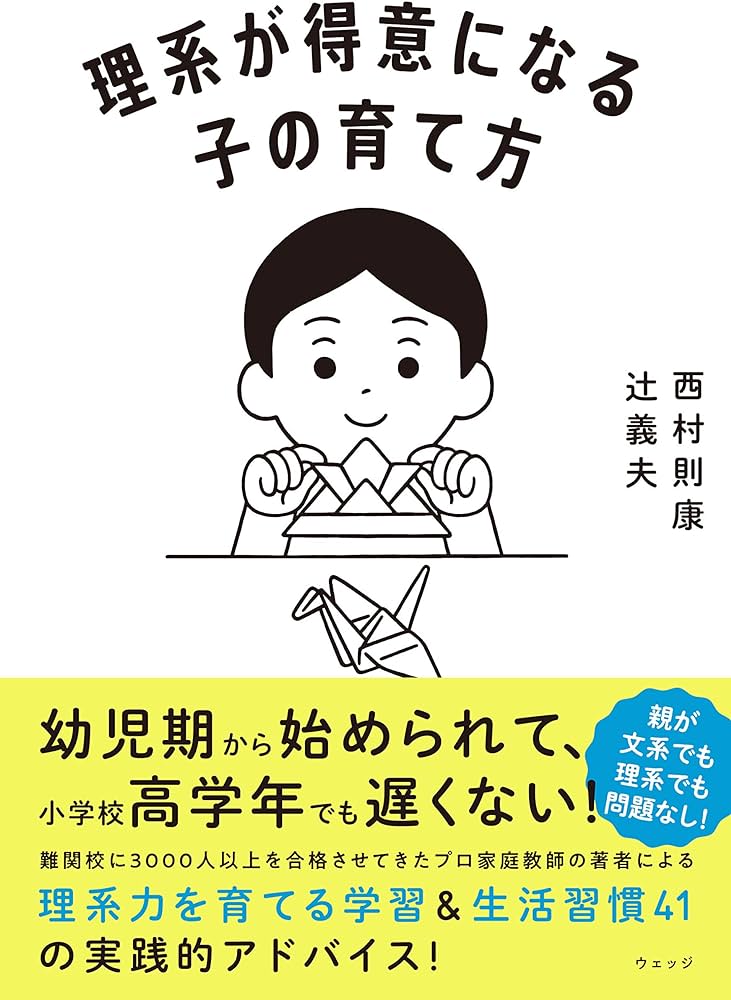

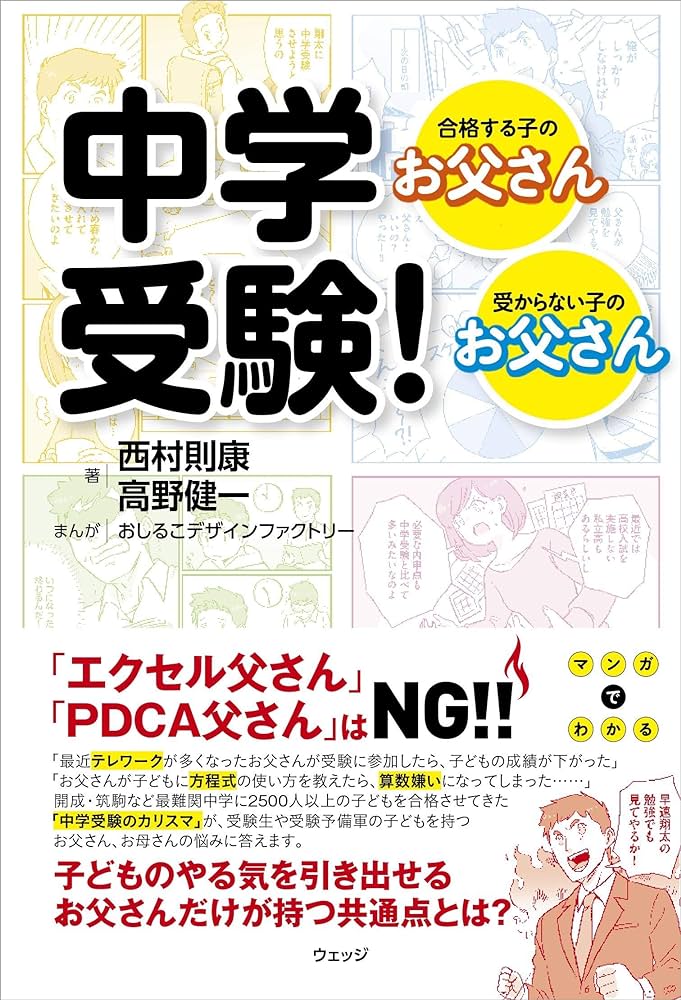
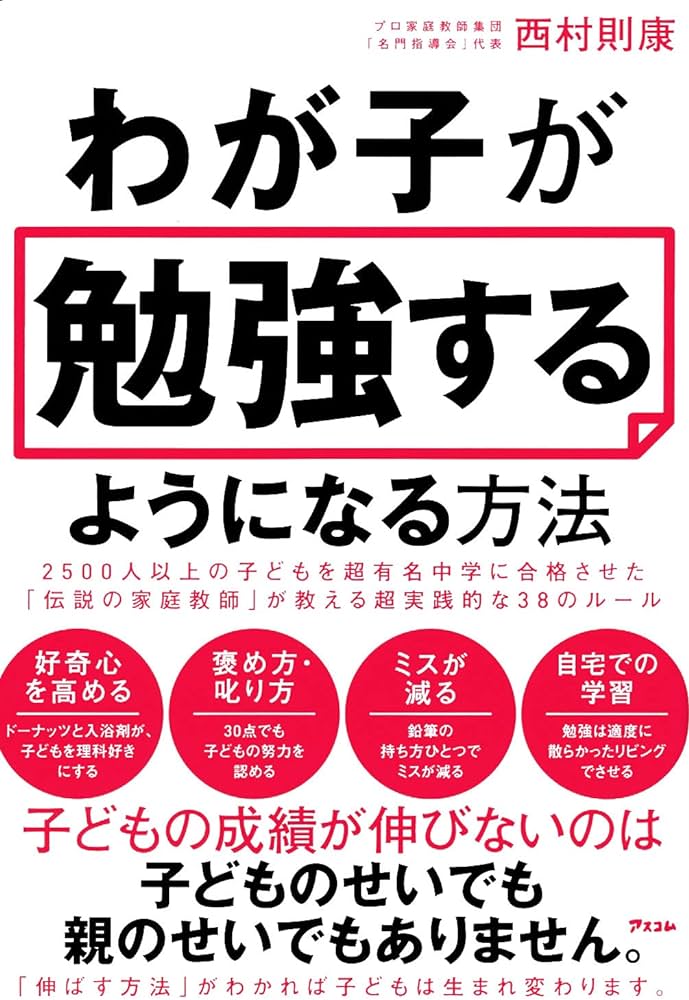
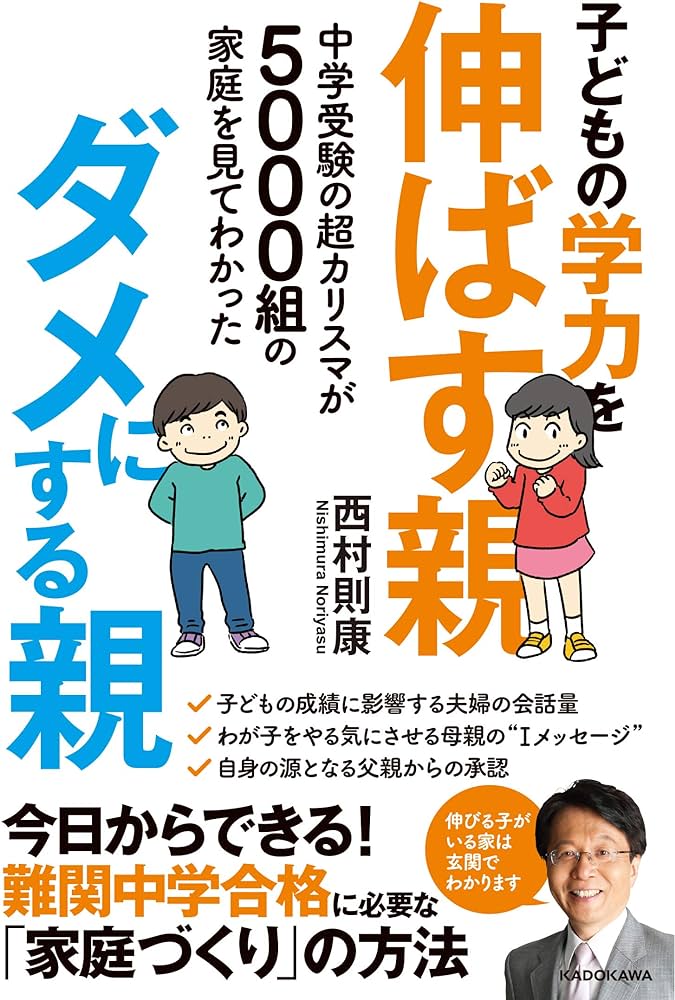
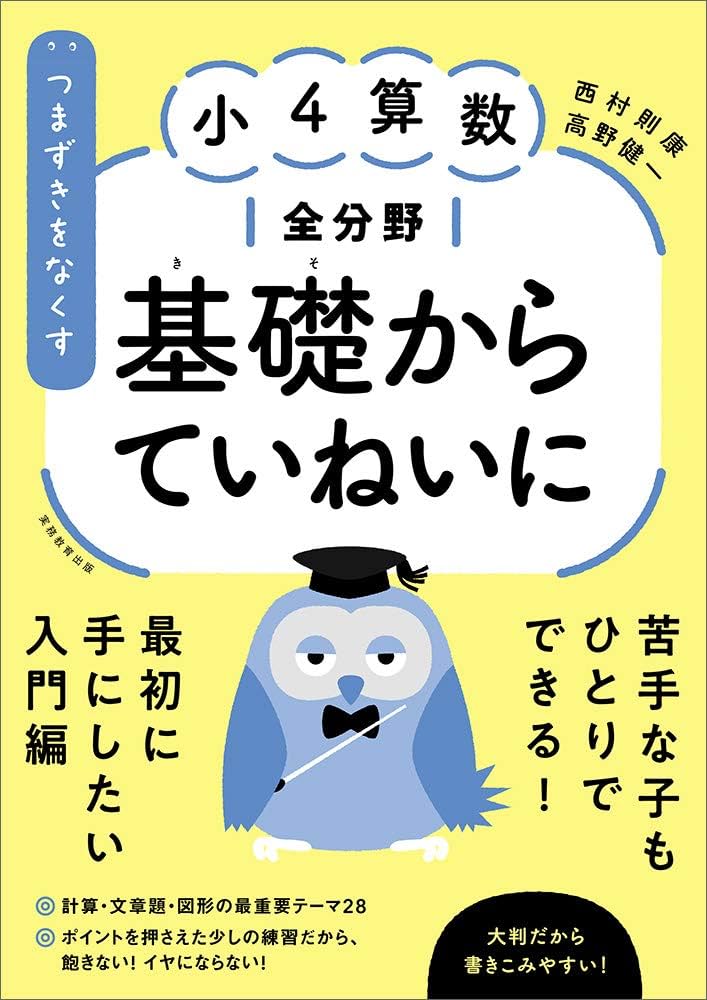
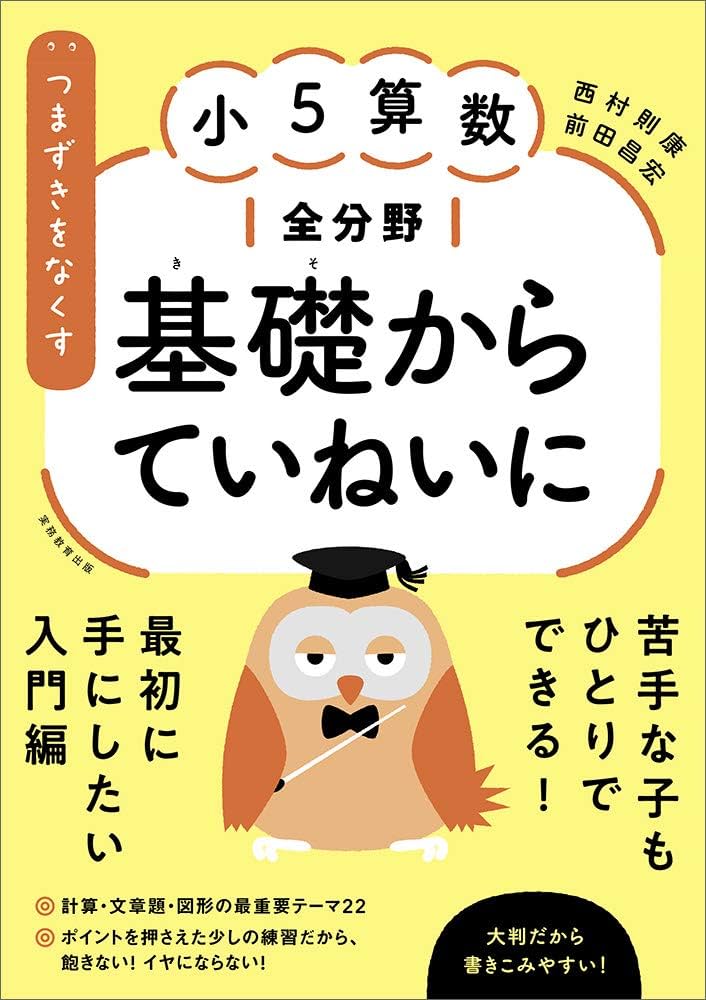
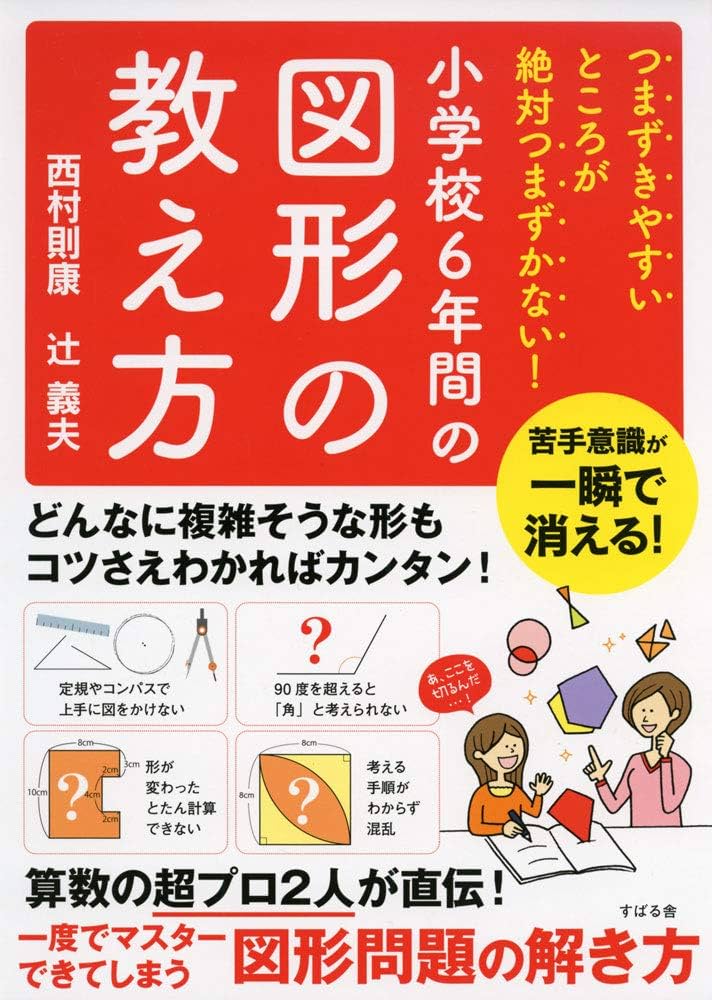
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)