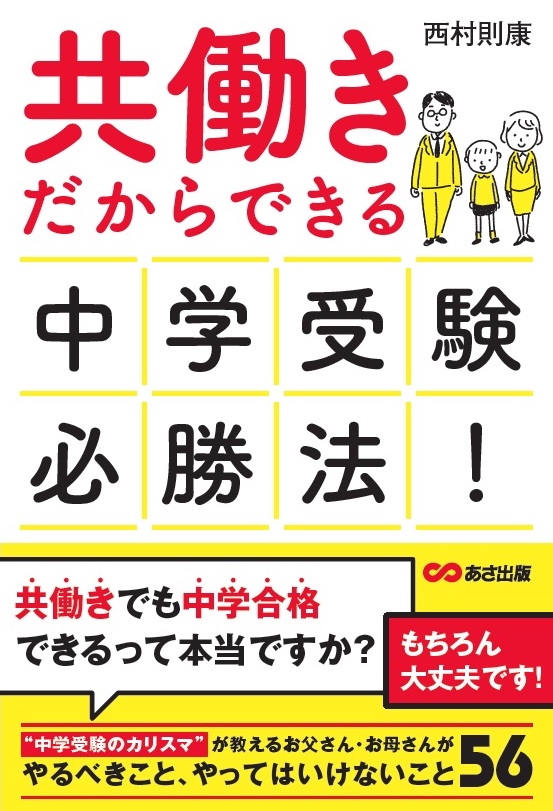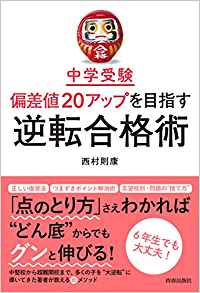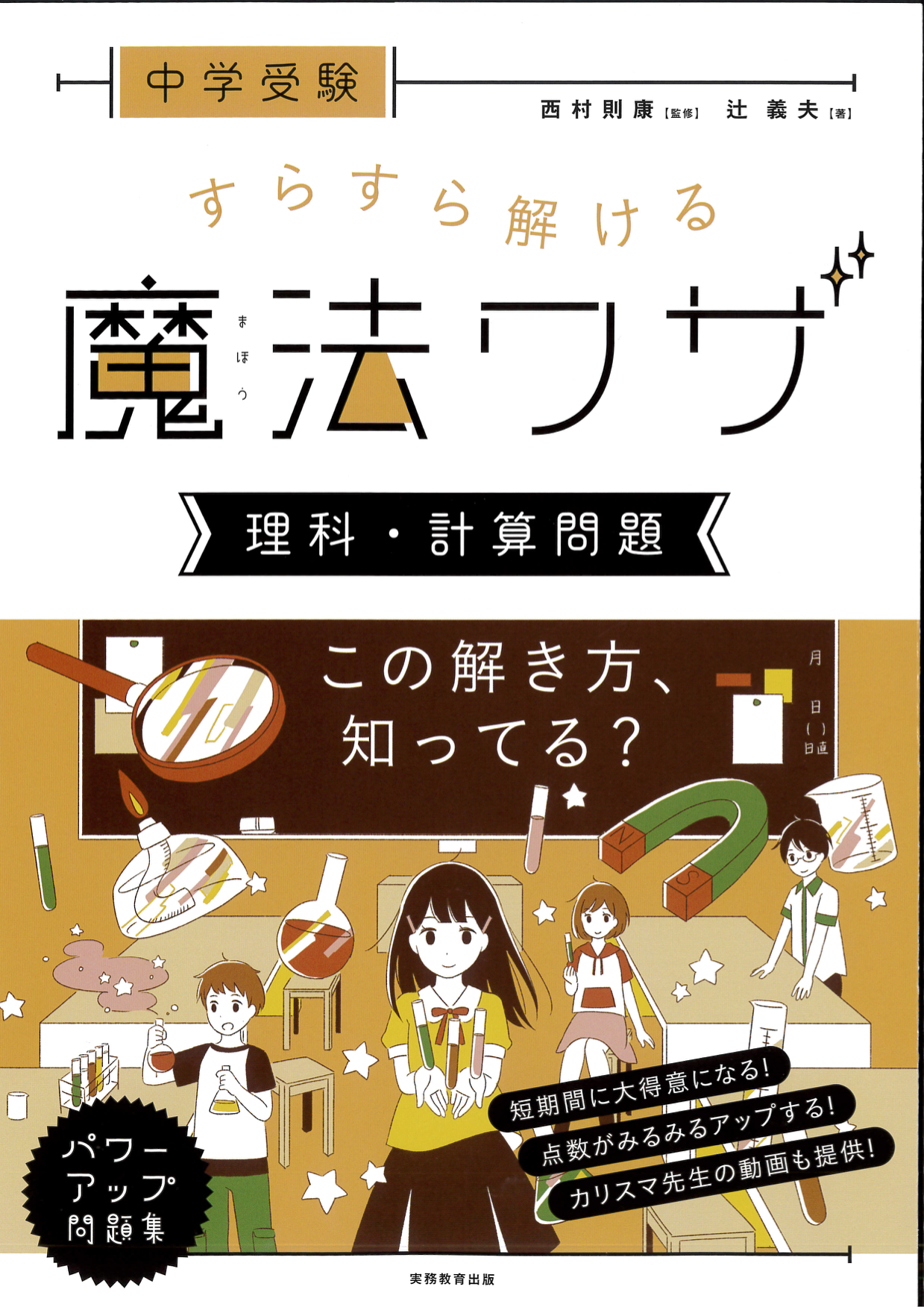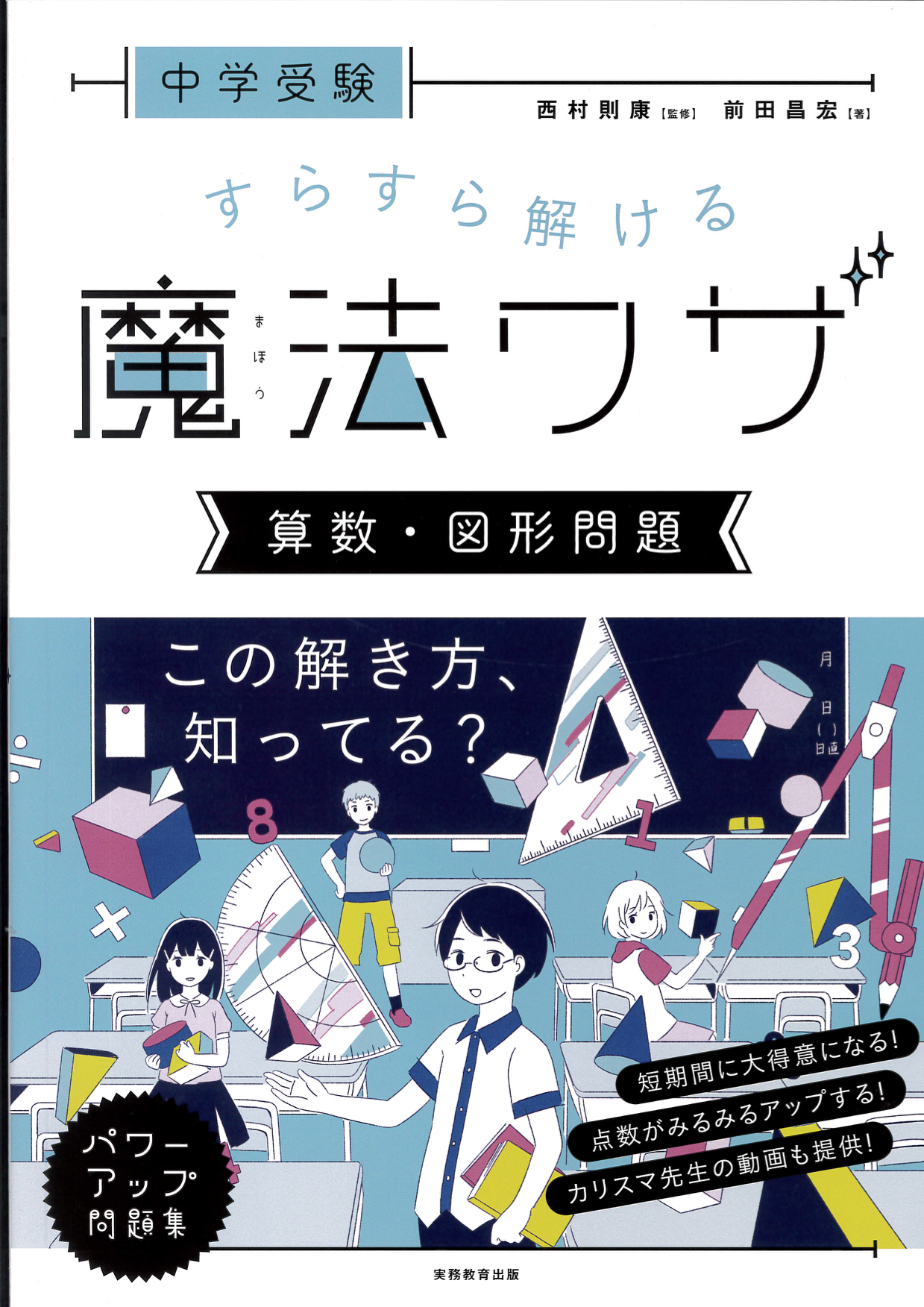目次
4年生・5年生の2学期の重要性
4年生の2学期に注意すべきこと:基礎の土台を固める
5年生の2学期に注意すべきこと:学習量の壁を乗り越える
保護者の方へ:伴走者としての心構え
長い夏が終わったかと思えば、いきなり冬が来るのではという気温になり、お子さん、親御さんも体調管理に気をつけていただきたいこの頃ですね。
中学受験を目指す小学4年生・5年生の2学期の学習について、これまで何回かお伝えしてきましたが、あらためて今回の記事では、特に注意していただきたい点をまとめてお話ししたいと思います。
2学期は、受験学年である6年生に向けて、基礎学力の定着と応用力への橋渡しをする上で、非常に重要な時期となります。ここでつまずくと、後々大きな負担になりかねません。
4年生・5年生の2学期の重要性
4年生の2学期は、中学受験の学習が本格化し、各教科で抽象的な概念や複雑な単元が導入され始める時期です。特に算数では、特殊算や図形などの重要な分野が登場します。
5年生の2学期は、「受験の天王山」とも呼ばれるほど、学習量が最も多くなり、難度も急上昇します。ここで成績が安定するかどうかで、6年生のスタートが変わってきます。
4年生の2学期に注意すべきこと:基礎の土台を固める
4年生の2学期で最も注意すべきは、「基礎の穴」を作らないこと、そして学習習慣を確立することです。
1. 算数:「割合」「速さ」の土台づくり
算数で特に重要なのは、「割合(分数・小数)」と「速さ」の概念です。この時期に導入されるこれらの単元は、6年生で学習する多くのや応用問題の基礎となります。
• 定義や原理をしっかり理解させること:公式を覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか」を親子で一緒に考える時間を持ちましょう。
• 計算力の徹底強化:計算ミスはトレーニングによって減らすことができます。正確な計算力を維持するため、毎日欠かさず計算トレーニングを行う習慣をつけましょう。
2. 国語:読解力の「型」の習得
国語では、「論説文・説明文の読み方」、すなわち「接続詞や指示語の役割」「筆者の主張の見つけ方」といった読解の基本的な「型」を習得することが大切です。
• 本文に根拠を探す習慣:自分の意見ではなく、「本文のどこに答えのヒントがあるか」を意識させるようにしましょう。
• 語彙力の充実:難しい言葉が出てきたら、その都度、辞書で意味を調べ、例文を作るなど、深く理解させる工夫が必要です。
3. 学習習慣の確立:「やればできる」の成功体験
4年生のうちに自分から机に向かう習慣を確立することが、後の成長を大きく左右します。
• 「ルーティン」の作成:帰宅後のスケジュールを固定し、「この時間は必ず勉強」という時間割を親子で決めましょう。
• 褒めて伸ばす:結果よりも、勉強に取り組んだ姿勢や小さな努力を具体的に褒め、モチベーションを維持させることが重要です。
5年生の2学期に注意すべきこと:学習量の壁を乗り越える
5年生の2学期は、受験に直結する重要な単元、分野の学習が増え、内容も一気に難しくなります。ここでは、消化不良を起こさないよう注意すること、苦手分野を放置しないことが鍵になります。
1. 算数・理科:単元間の「関連付け」を意識する
難度の高い単元が次々と出てきますが、重要なのは学習したことを「単発の知識」で終わらせないことです。
• 算数:入試頻出分野の早期完成:「比(割合の応用)」「立体図形」「場合の数」といった入試の合否を分ける重要単元が集中します。これらの分野は、焦らず、「なぜそうなるのか」を考えながら演習して「完全に理解した」状態を目指しましょう。
• 理科:暗記から「原理の理解」へ:理科でも、知識が複雑になる分、「なぜそうなるのか」という原理・仕組みを理解することが重要です。特に「てこ」「滑車」などの物理分野は、自分で図を書いて仕組みを説明できるレベルにすることが理想ですね。
2. 社会:流れを掴む「歴史」と「地理の深い知識」
歴史が本格的に始まり、地理も細かな知識が増えます。
• 歴史:人の営みとして理解する:「いつ、誰が、何をしたか」だけでなく、「なぜその事件が起こったのか」という時代背景や因果関係を、ストーリーとして理解しておくことが大切です。特に近代〜現代に関しては、流れを掴むことを最優先し、年号は後からで構いません。
• 地理:白地図を活用する:単なる地名や特産物の暗記ではなく、産業と地形・気候の関連性など、具体的な場所を白地図で確認しながら、多角的な知識として定着させることが大切です。
3.復習の仕組みを確立する
新しい単元の学習に追われ、復習がおろそかになりがちなのが5年生の2学期最大の落とし穴です。
• 「ウィークリー復習」の習慣:週末に「この1週間で習ったこと」をざっと見直す時間を取りましょう。特に間違えた問題だけをピックアップして解き直すことが効率的です。
• 「苦手分野リスト」の作成:親子で「この単元はまだ不完全だ」という分野を特定し、リスト化して定期的に取り組みましょう。放置は絶対にいけません。
保護者の方へ:伴走者としての心構え
最後に、保護者の皆様にお願いしたいのは、完璧を求めすぎないこと、そしてお子さんの心の状態を見ていただきたいことです。
2学期は、子どもにとって精神的にも肉体的にも負担が大きくなる時期です。親は成績の浮き沈みに過度に一喜一憂せず、努力のプロセスを評価してあげてください。学習の計画を立てるサポートは必要ですが、横について教える場合は、自分で考える力を奪わないよう、答えをすぐに教えるのではなく、どうすれば解けるかを一緒に考えてあげる「伴走者」に徹していただけると理想です。
もちろん、この部分は和屋市たち家庭教師が担うケースも多いです。ご家庭だけで「行き詰まり」を感じていらっしゃるようでしたら、ご相談いただけると対応します。
この2学期を乗り越えることができれば、お子様は大きく成長し、6年生での受験勉強に弾みがつくはずです。一緒に頑張っていきましょう。
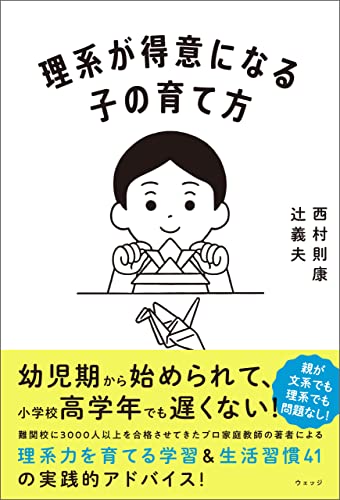
西村則康・辻義夫著
理系が得意になる子の育て方
WEDGE 1650円(税込)
受験相談・体験授業お申込み
必須の項目は必ず入力してください。

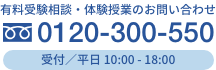


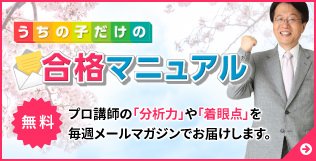



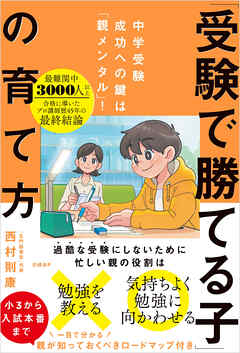
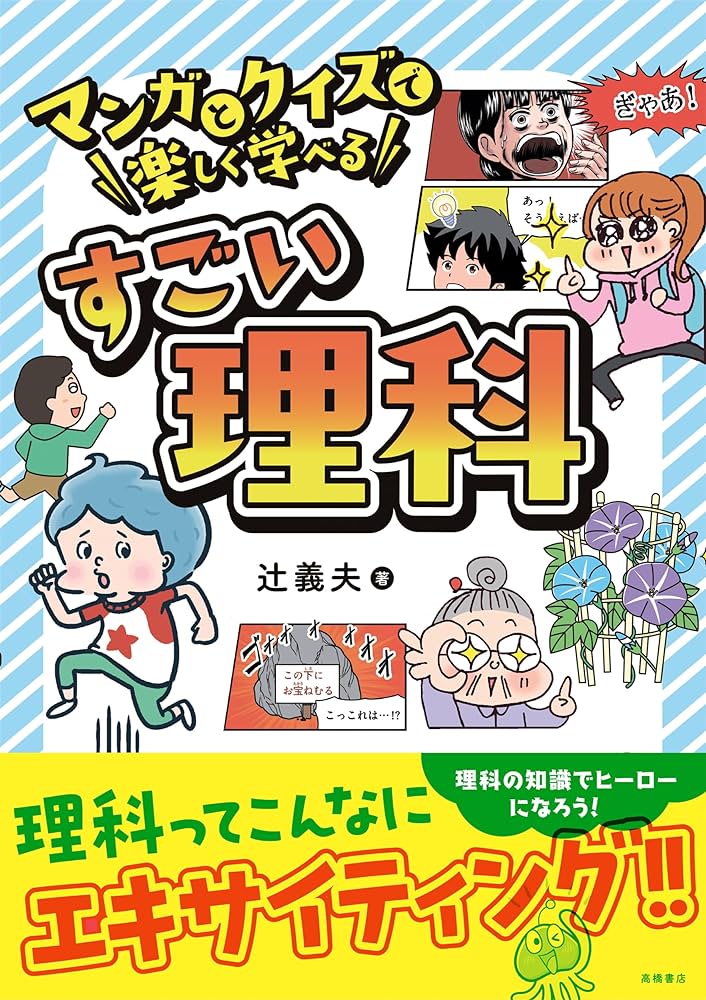
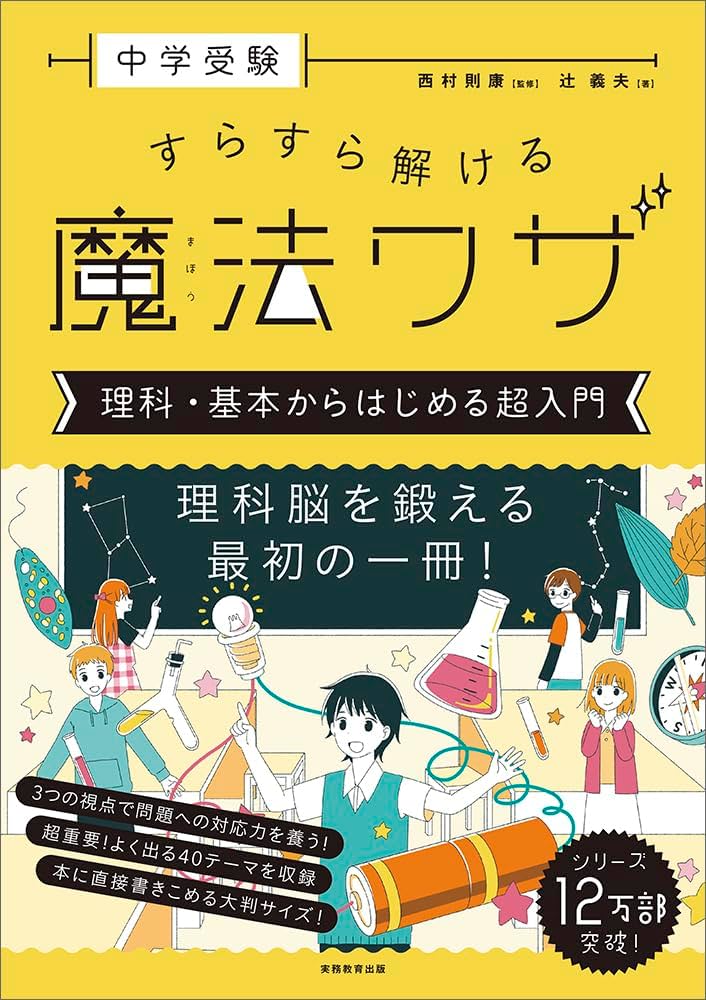
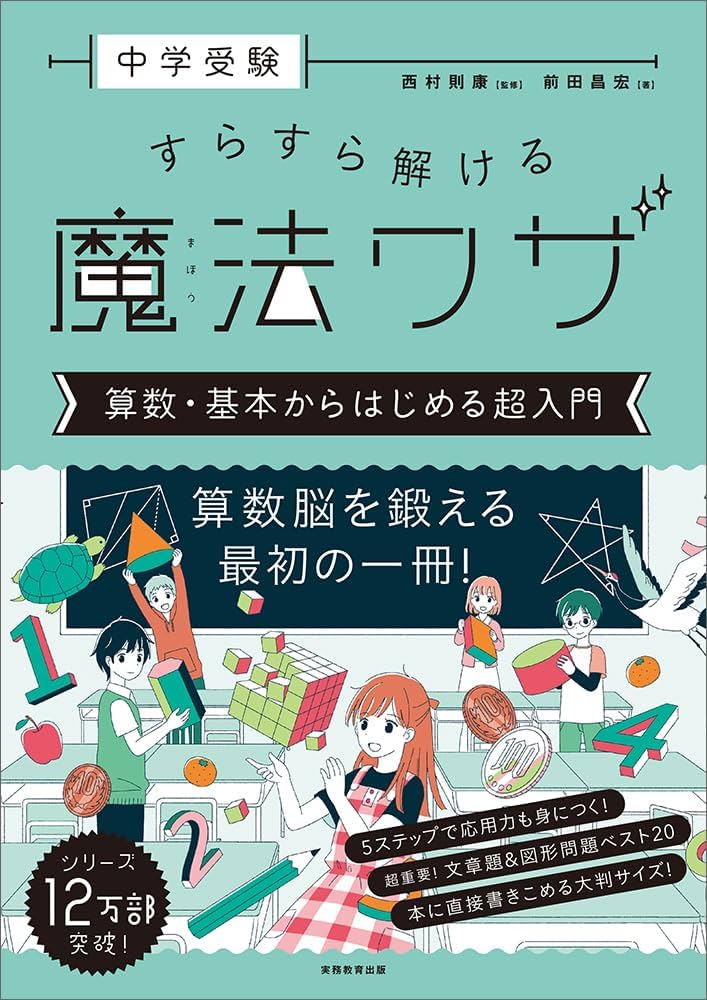
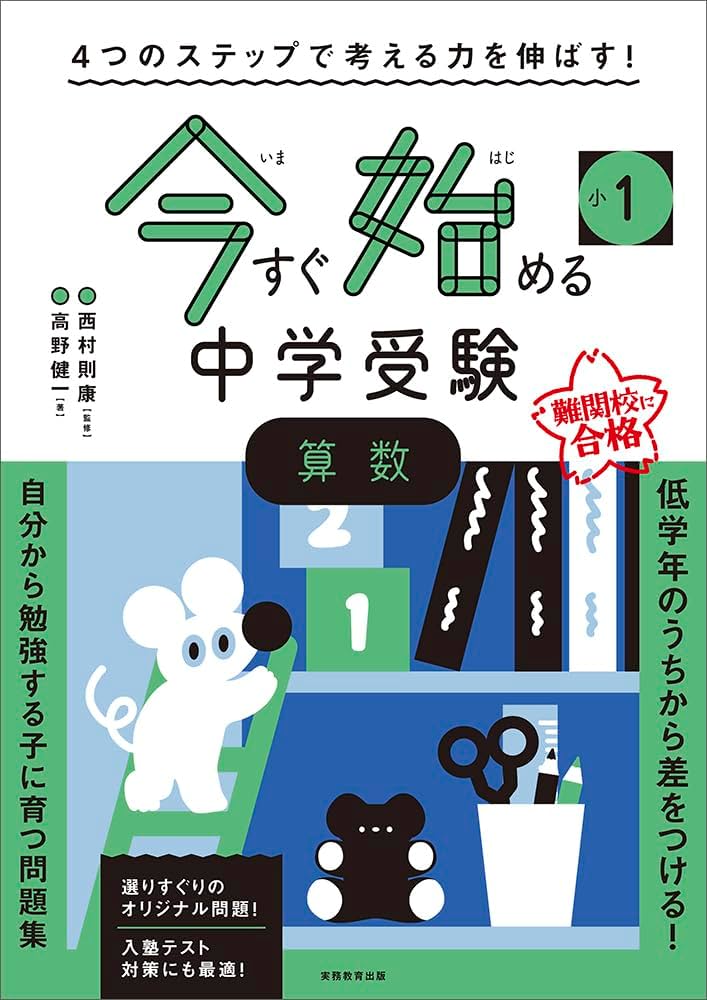
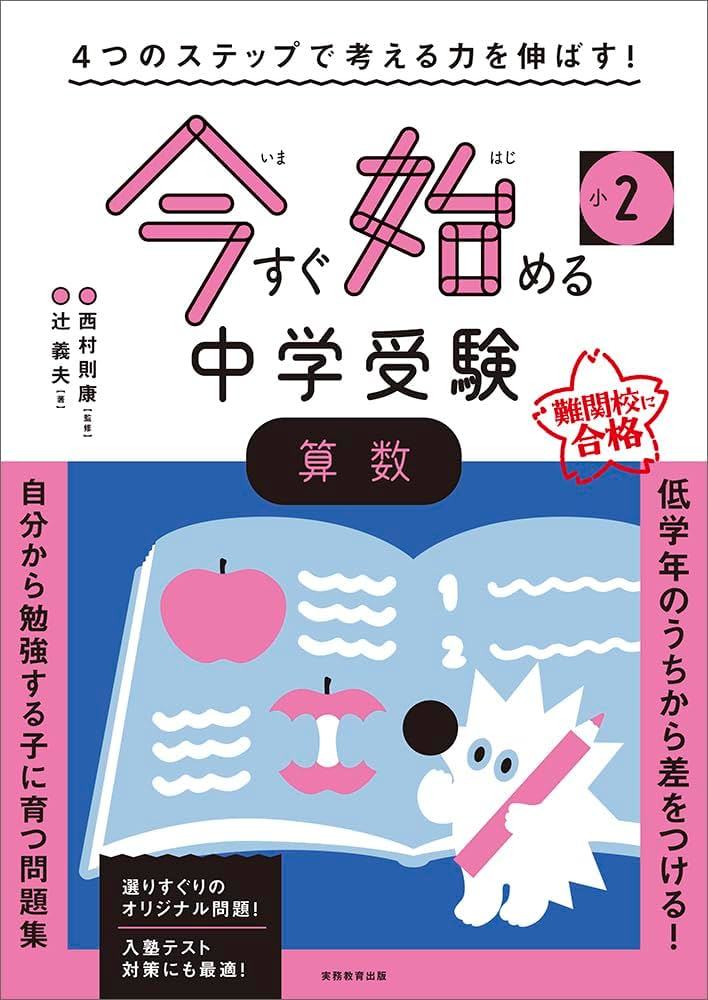
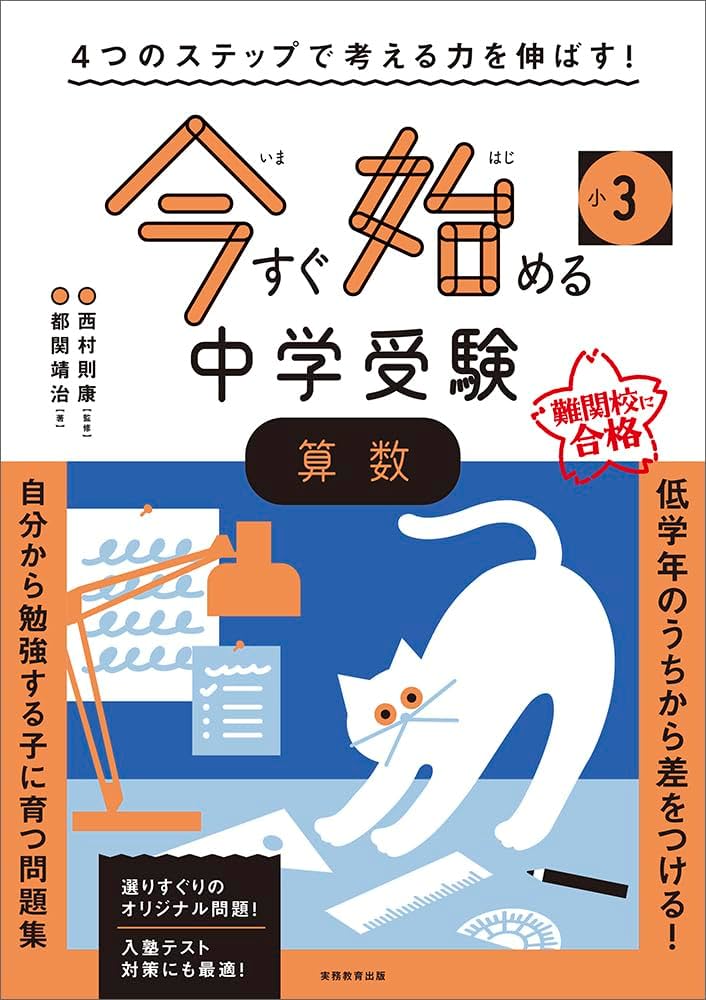
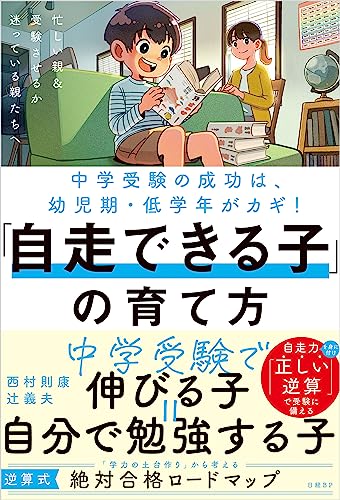
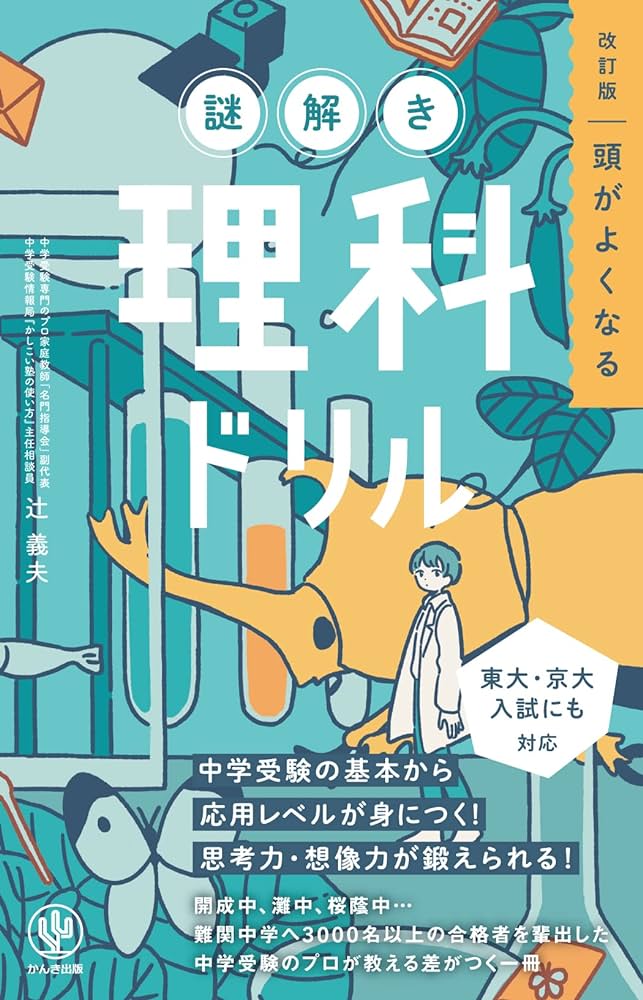
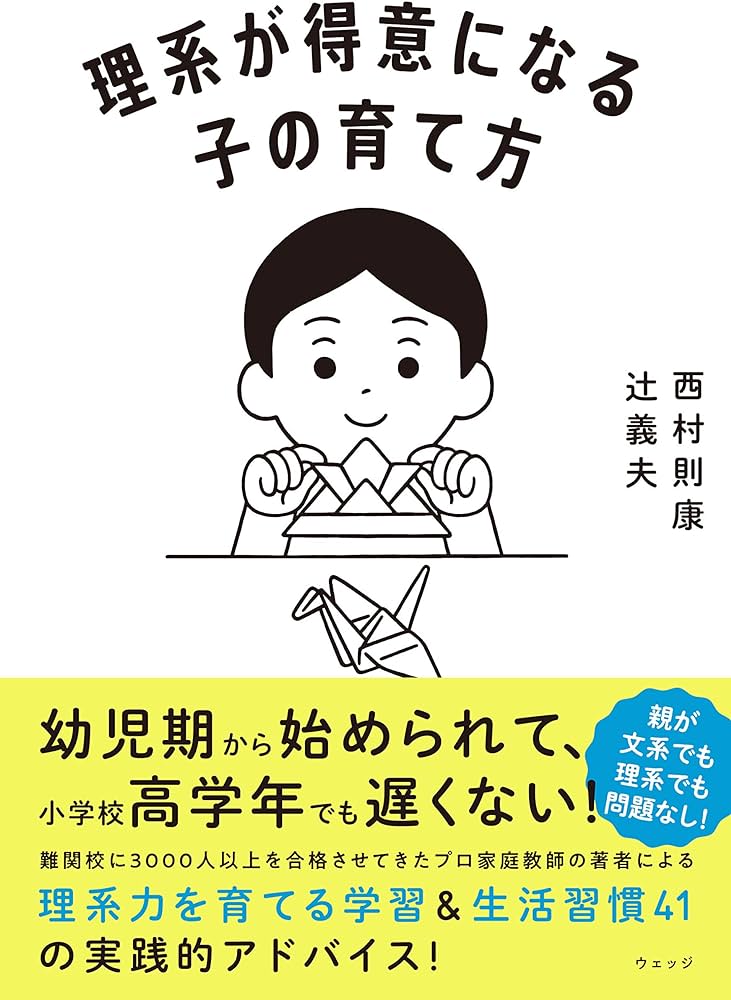

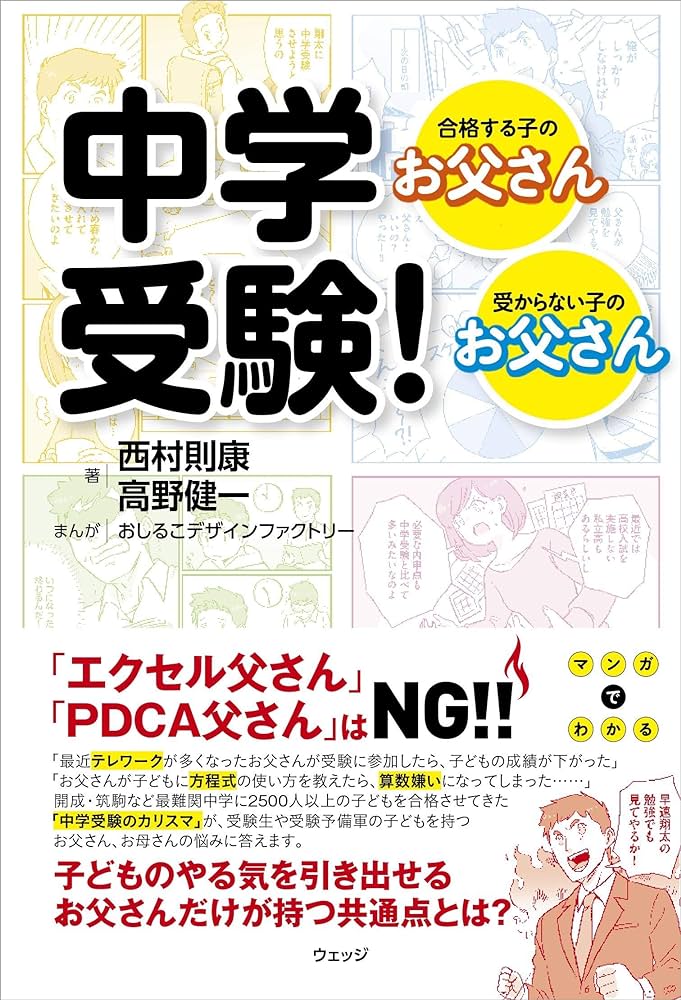
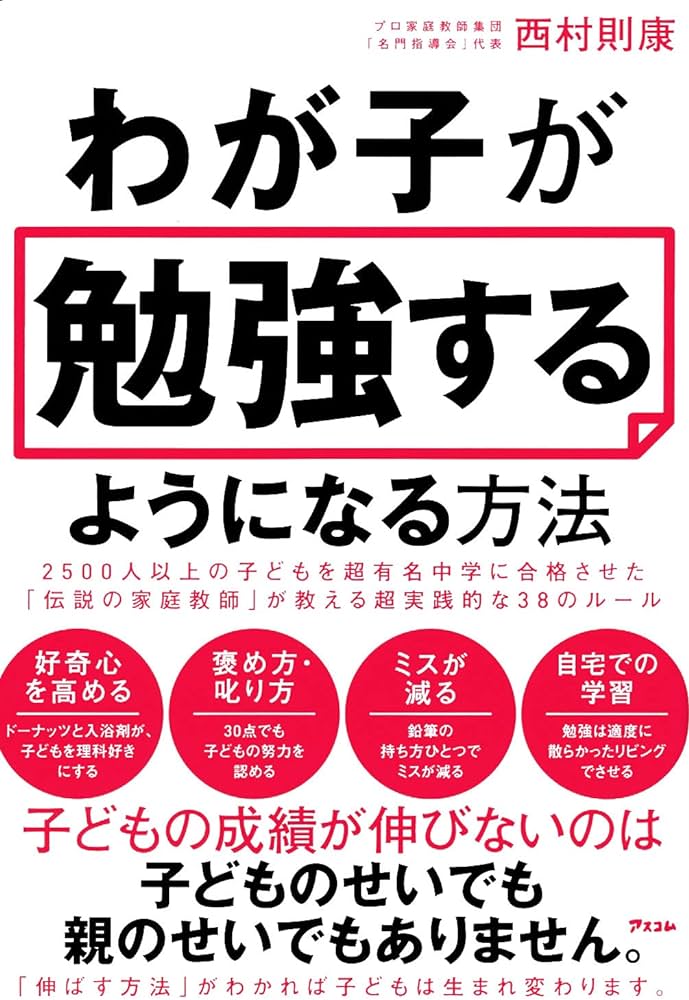
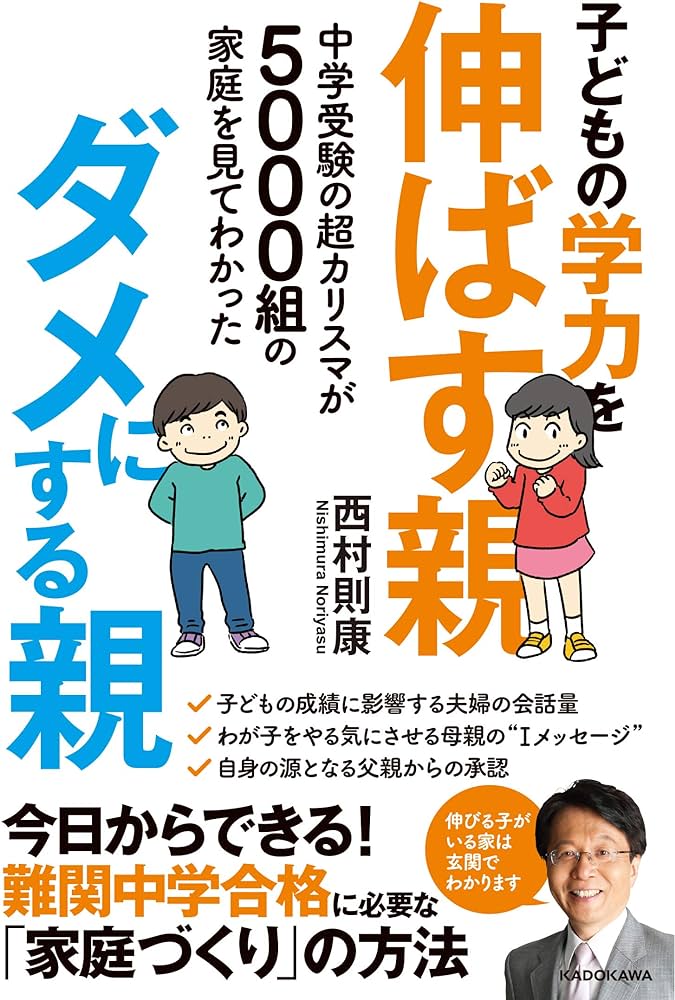
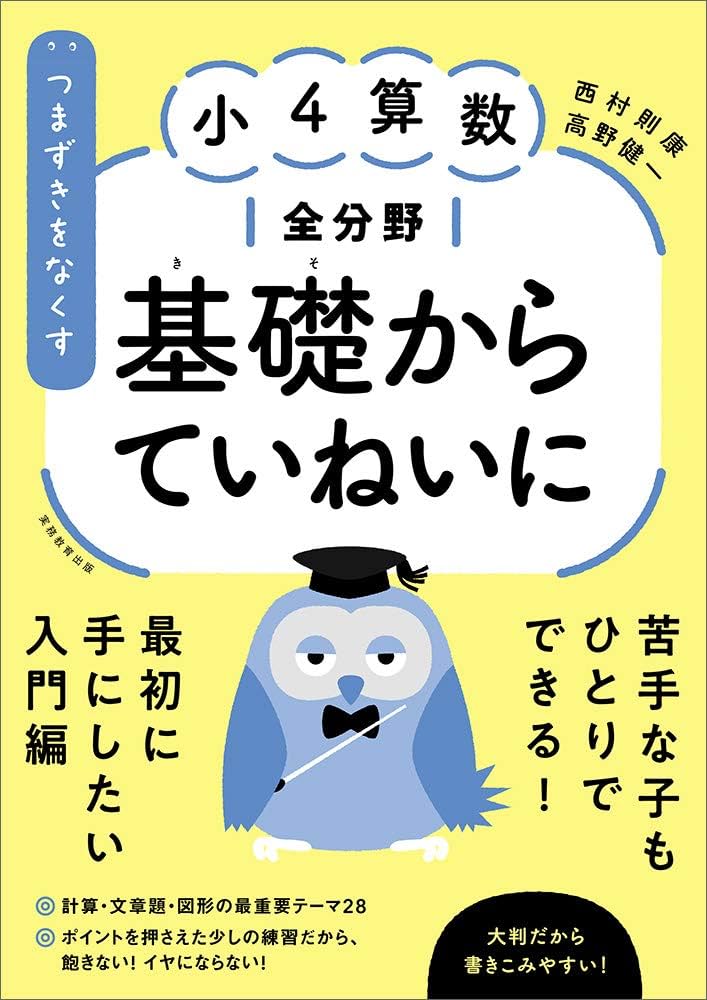
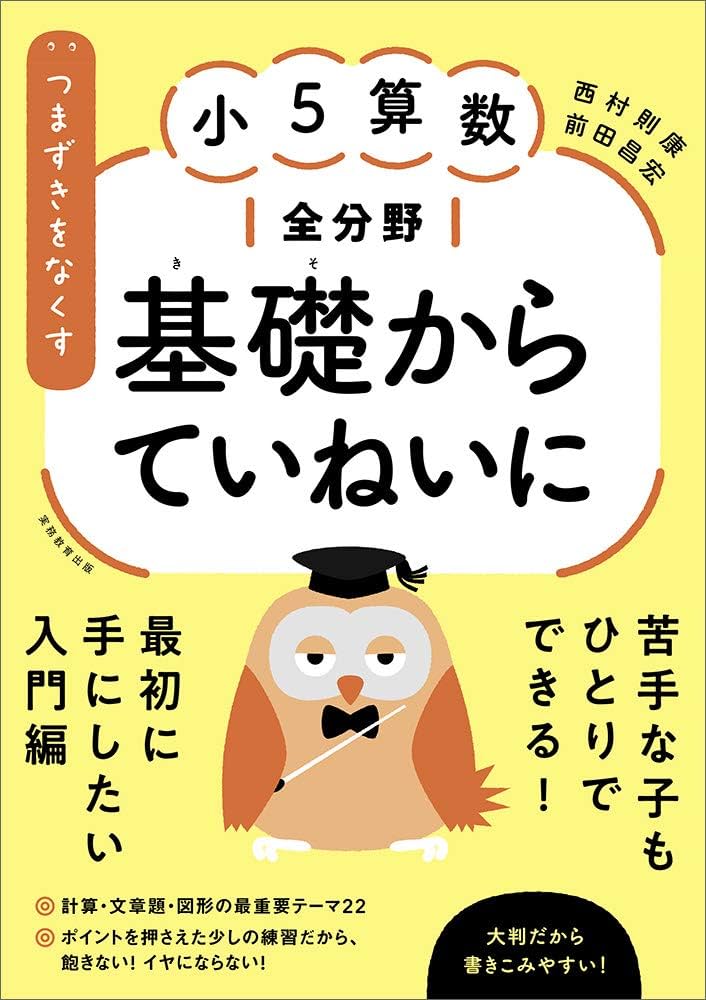
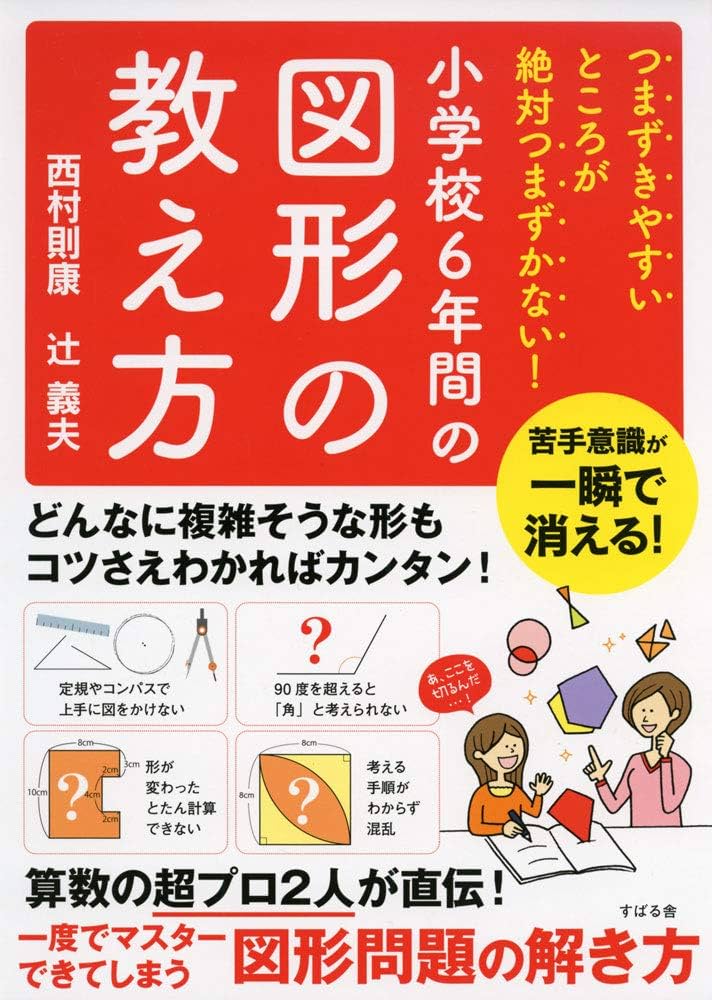
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)