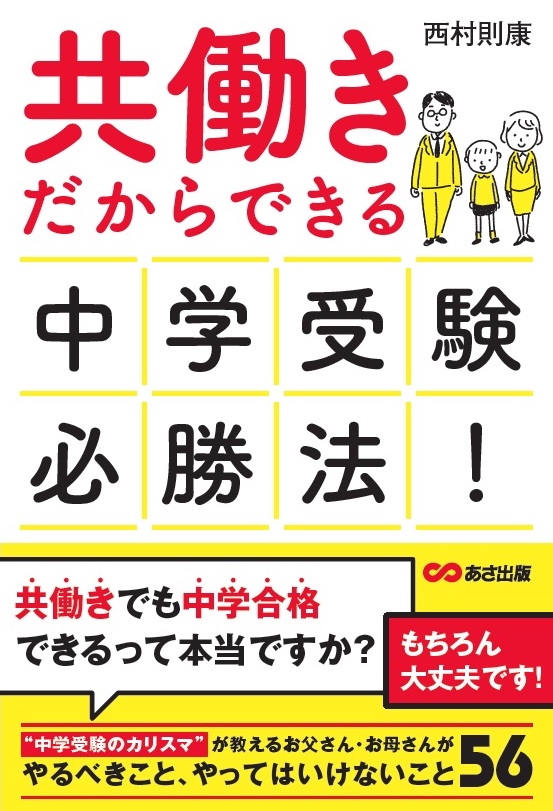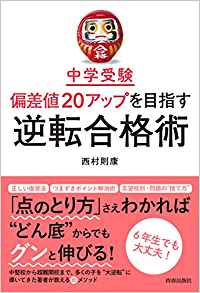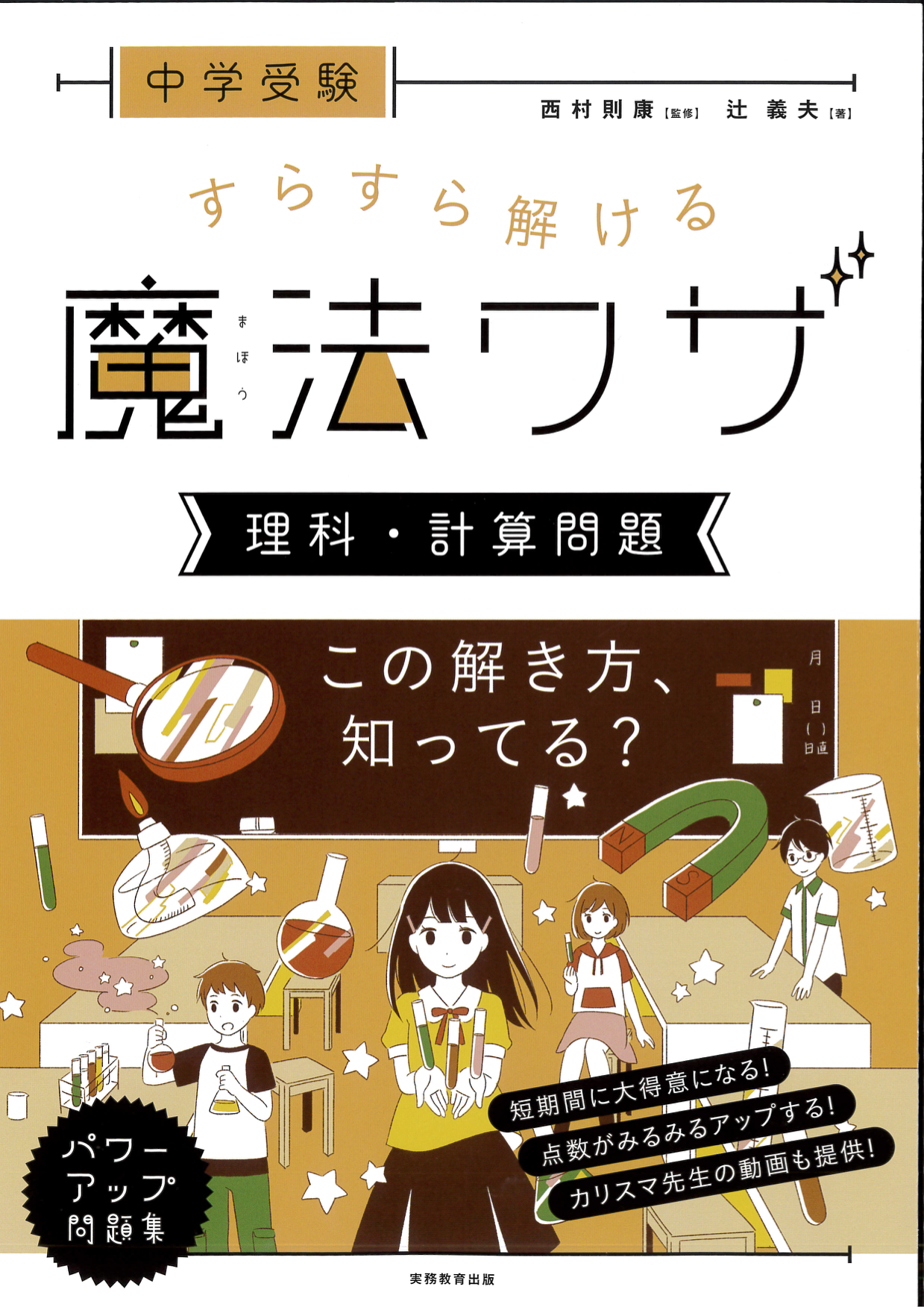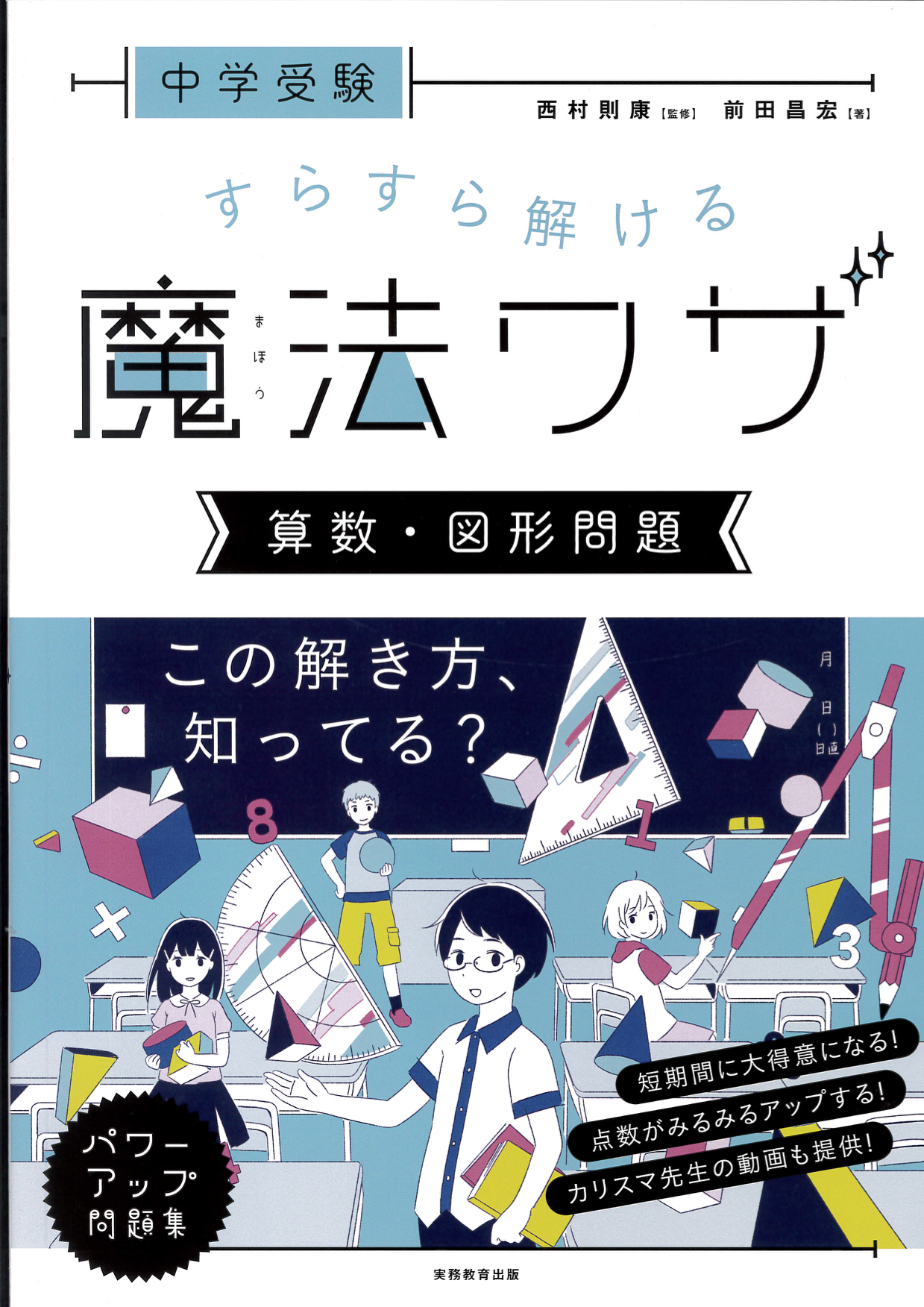目次
近年の入試傾向と偏差値変動の現状
個別学校の入試変更と注意点
志望校選びと受験戦略における考慮点
お子さんの心理的側面への配慮
真夏のような気温の日が続いています。
こうなると、特に6年生のお子さんのご家庭では、否が応でも夏、そして本格的に始まる志望校対策を意識せずにいられませんね。
ここでは、志望校選びや受験戦略において、近年の入試傾向や偏差値変動からの雑感をお伝えしたいと思います。
近年の入試傾向と偏差値変動の現状
これまで「比較的容易に合格できる」と思われていた学校のレベルが軒並み上がってきており、第二志望や第三志望校の設定が難しくなっています。特に午後入試のレベルも上がり、多くの学校を受験しても合格可能性が高まるとは限らない状況です。
各塾、特にSAPIXのような難関校志向の塾の発表する「合格可能性偏差値」に関して、「偏差値50以下の学校は当てにならない」という見方があります。SAPIXの先生も「偏差値40台までは『ボリュームゾーン』だから、偏差値50を超える志望校を目指しても問題ない」と話すケースがあるようです。ただし、常に40を切る状態だと注意が必要とも言われています。
私は実感として、多くの学校で偏差値が数ポイント違う程度では合否を判断できず、過去問との相性が合否に大きく影響すると感じています。20%から80%の合格可能性偏差値帯では、飛び抜けた上位や下位を除けば、実質的に過去問との相性で結果がいくらでも変わりうると考えています。
上記のサピックスとは逆に、日能研のR4偏差値は、中堅校ラインでは信頼でき参考になるものの、最難関校ではサピックスや浜学園のデータの方が確実という側面があります。
個別学校の入試変更と注意点
2026年は2月1日が日曜となる「サンデーショック」の年となるため、キリスト教系の学校の2月1日入試が2月2日に変更になるケースがありますので、注意が必要です。
女子学院
入試日が2月2日に変更されたことで、合格難度が上がる可能性が予測されています。(2月1日に他の御三家中などを受験した生徒が受験する可能性が高いため)
青山学院
昨年の2月3日から2月2日へ入試日が変更されますが、青山学院は元々2月2日が入試日だったため(2025年は2月2日が日曜だった)、特に変わる要素はないと考えられています。
サンデーショックについては、お子さんの志望校に関わりがあるかどうか、チェックしておくことをおすすめします。
立教池袋
2月5日の2回目入試は、合格の出し方が独特です。学校側が受験者平均程度の「選考範囲最低点(足切り点)」を設定し、それを超えた受験生の中から面接などの評価も加味して合格者を決定します。そのため、偏差値が中間層(四谷大塚で50~55程度)でも場合によっては合格のチャンスがあるとされています。2024年の2回目入試では、選考範囲最低点が極端に低かったケースも報告されています。
志望校選びと受験戦略における考慮点
夏前の合否判定テストなどで偏差値が達していない場合、「このままこの学校を目指していいものか」という思いが頭をよぎることがあるかもしれません。しかし夏の講習期間中、あるいは少なくとも9月いっぱいまでは、第一志望校を目指して学習を続けることをおすすめするケースが多いです。
この時期に安易に第一志望を変更するような話をすると、お子さんの学習モチベーションが低下する可能性があるためです。
併願校を含めた受験校の最終的な決定は、塾の個人面談が本格的に行われる11月以降を目安にするのが良いと感じています。それまでの間は、お子さんの状況をよく見て、必要に応じて柔軟に計画を調整しましょう。
11月の面談では、塾の先生もある程度正直に感じておられる合否の見通しについてお話しされると思います。しかし塾の先生がどのような受験戦略を提案しているかを確認し、それを踏まえて受験校を決定するのは最終的にはご家庭です。
偏差値だけで決めるのではなく、過去問との相性も見つつ、塾から提供される各学校の最新の入試情報(例えば上記の立教池袋の2回目入試のような独特な合否判断基準など)も考慮に入れて決定しましょう。
お子さんの心理的側面への配慮
テストで実力を発揮できないお子さんの中には、「頑張って解いても解けなかった時の恐怖感」や「できないと恥ずかしい、できないと恐怖だ」という感情が根底にある場合があります。
特に6年生は、1回1回のテストで「志望校に合格できるかどうか」を数値で突きつけられるため、プレッシャーもあるはずです。
このようなお子さんに対しては、テストの目的が「満点や高得点ではなく、部分点でも点を積み重ねて合格点を目指すこと」であることを伝えてあげてください。解答用紙を白紙にせず、とにかく何かしら書くように促すことが有効です。
6年生であれば、塾のテスト結果に一喜一憂しすぎず、「志望校の過去問が解ければ良い」という割り切りも必要です。これは「受験鬱」のような状態に陥ることを避けるためにも有効です。
あと1月あまりで「受験の天王山」と言われる夏休みが始まります。
まずは前回記事「6月 夏休みに向けて準備しておきたいこと」でお話しした準備に取りかかっていただければと思います。
充実した夏への周到なご準備ができることをお祈りしています。
受験相談・体験授業お申込み
必須の項目は必ず入力してください。

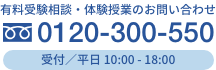


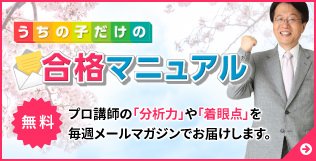



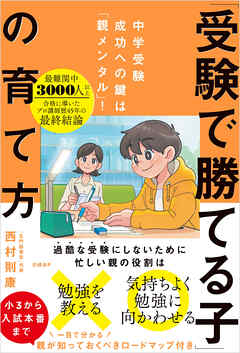
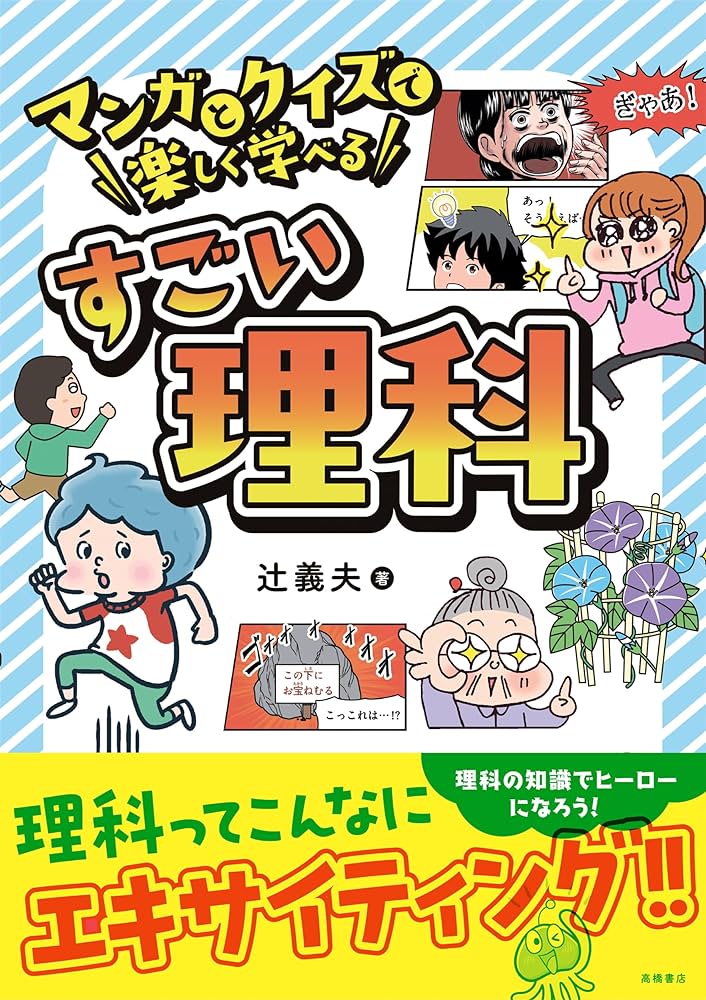
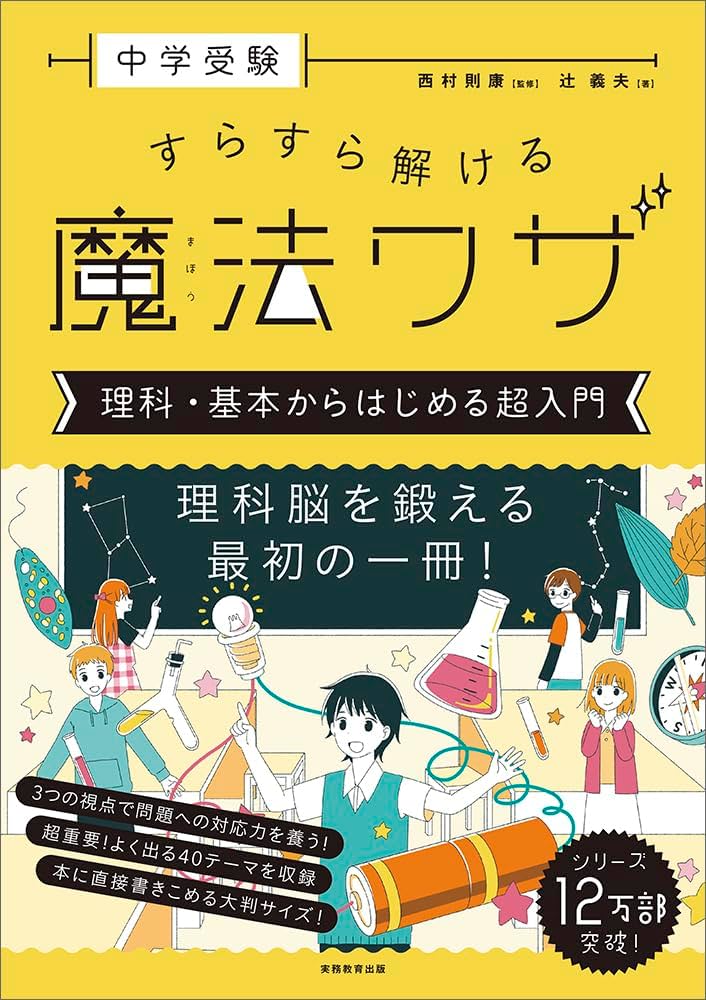
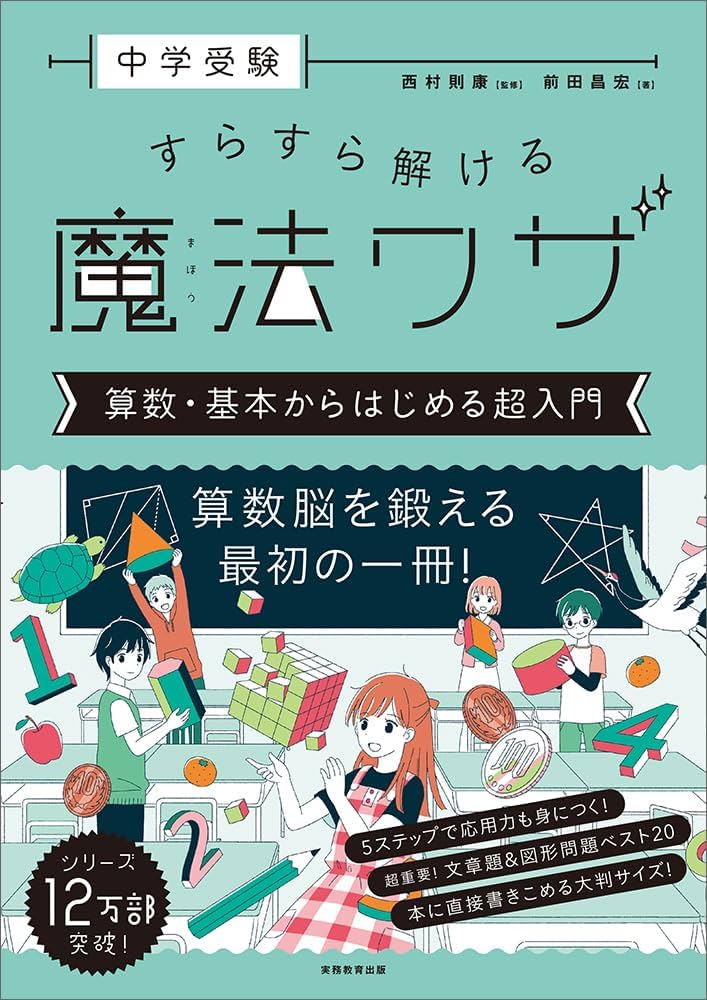
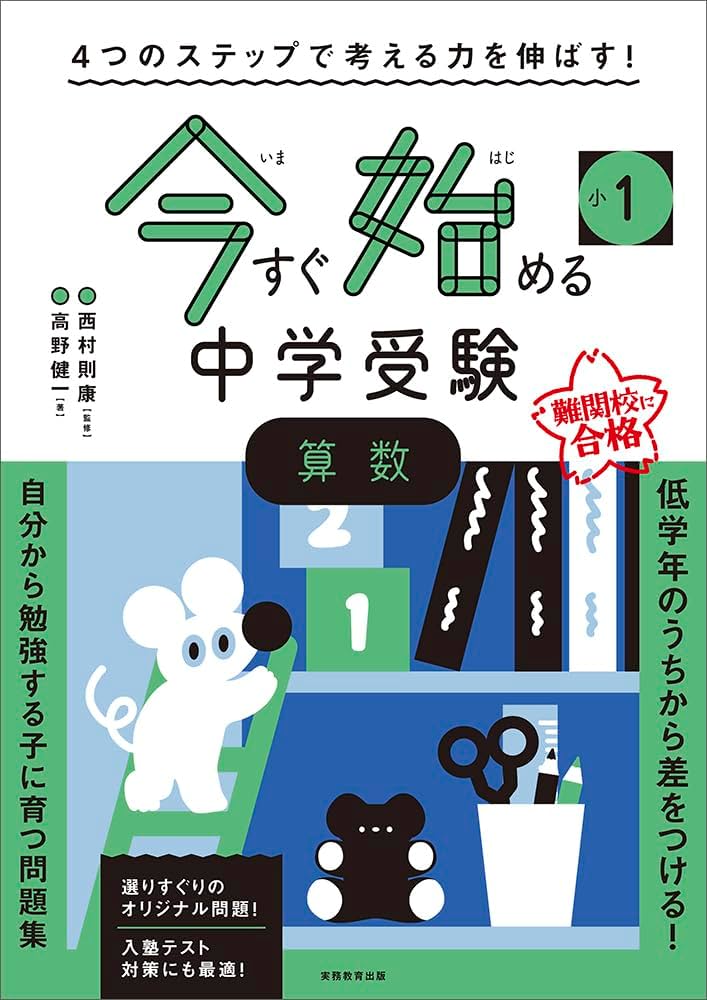
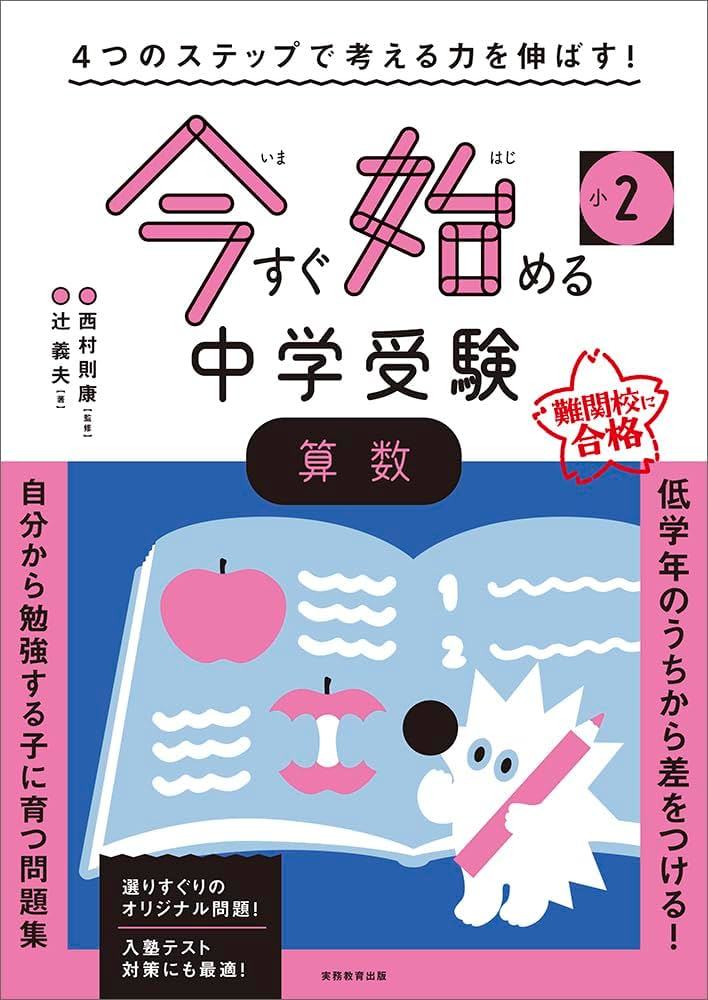
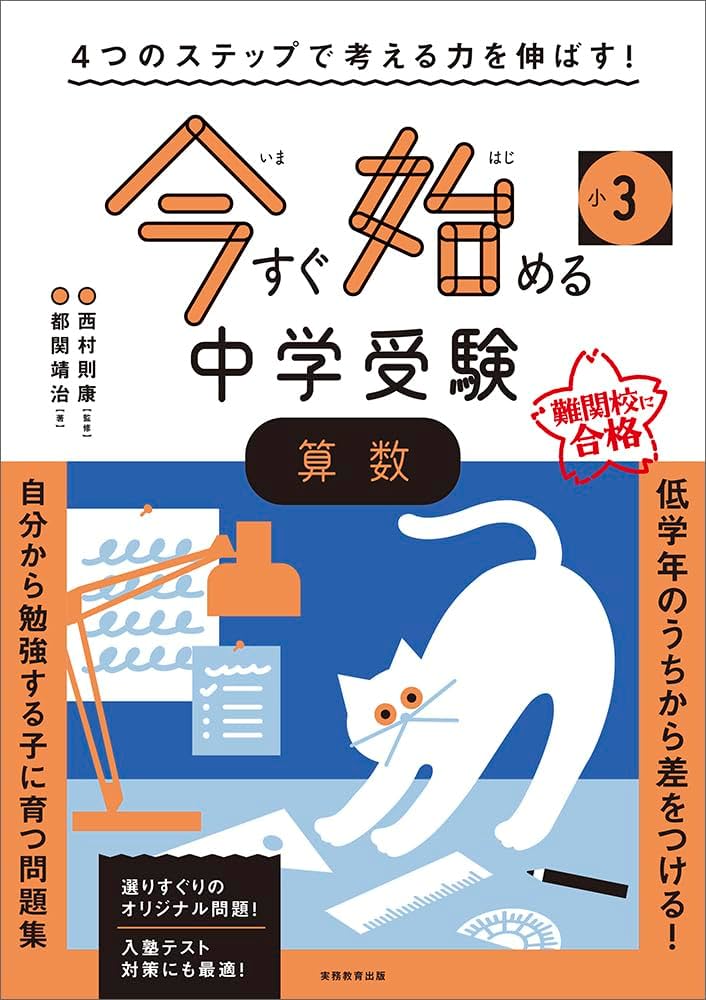
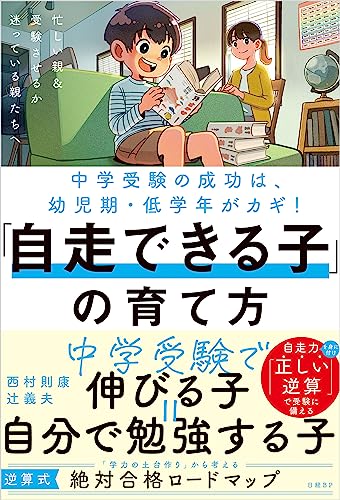
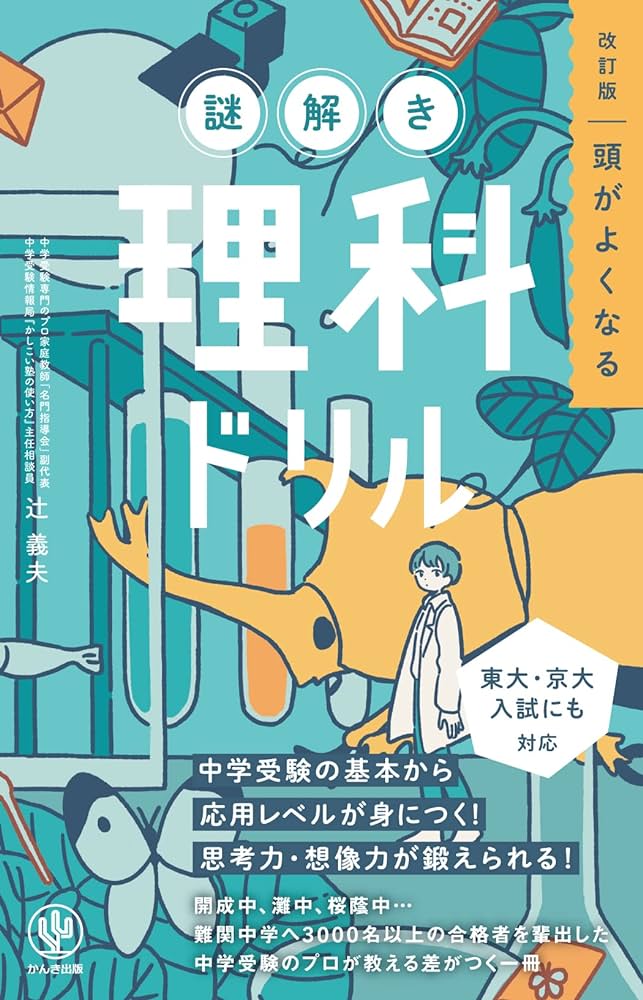
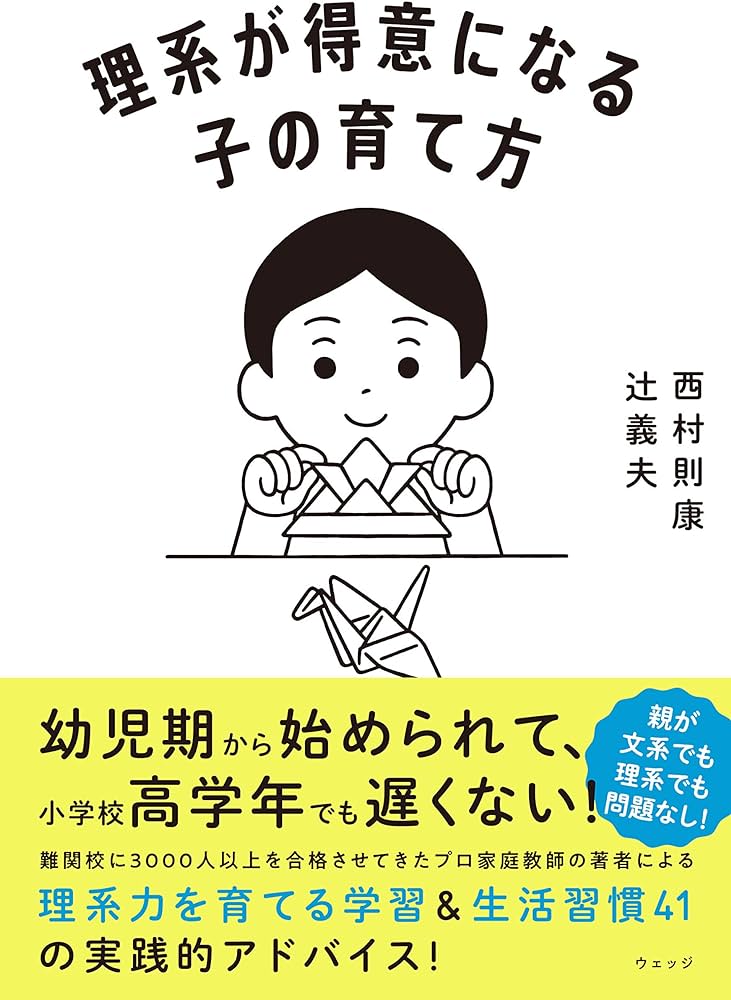

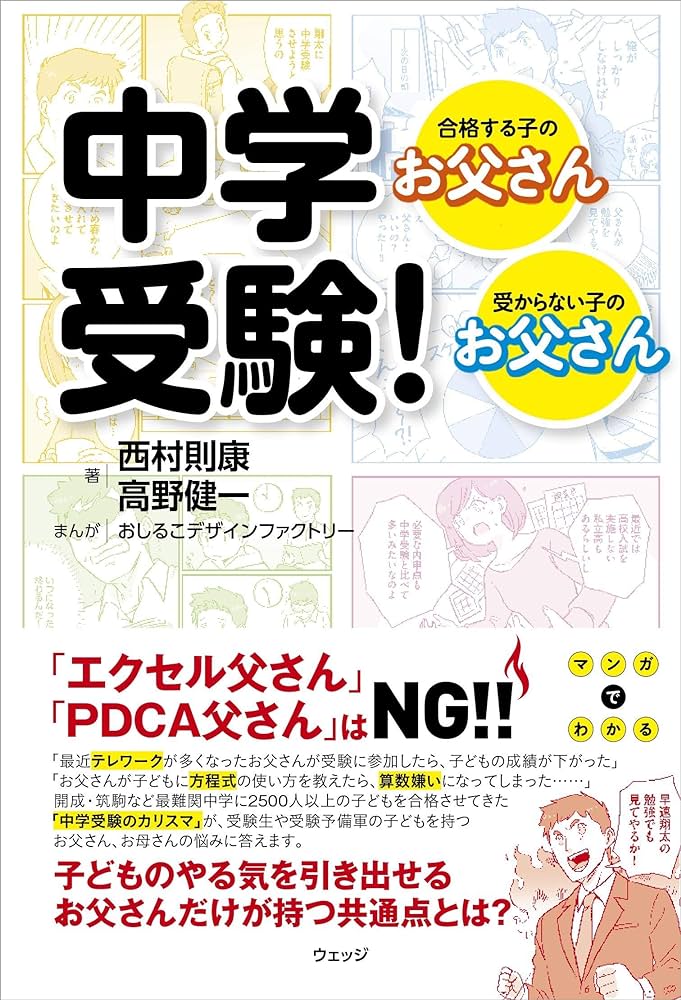
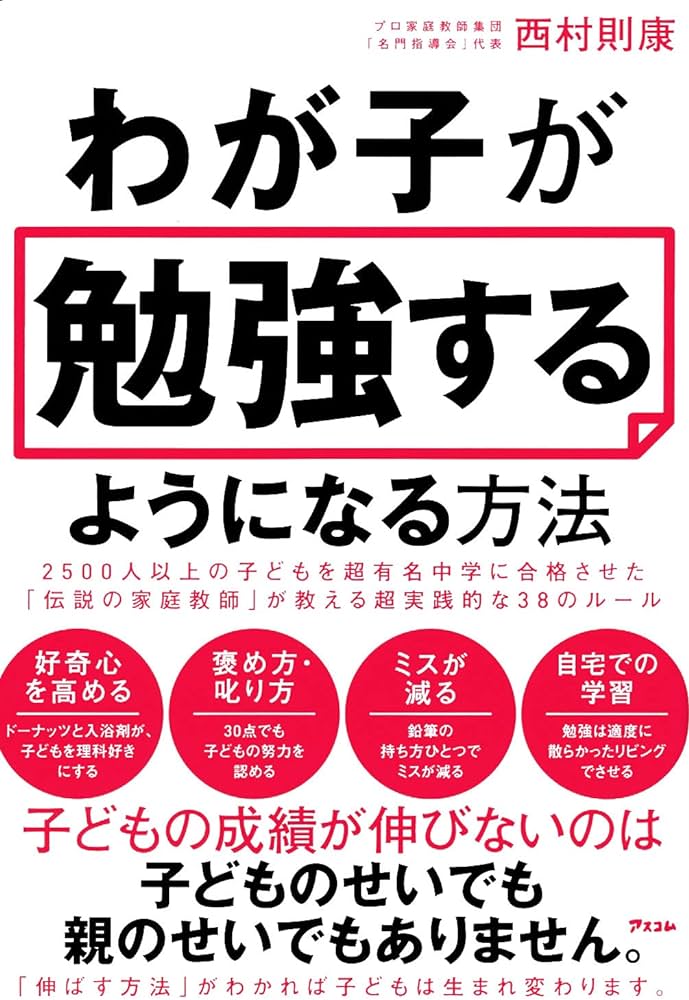
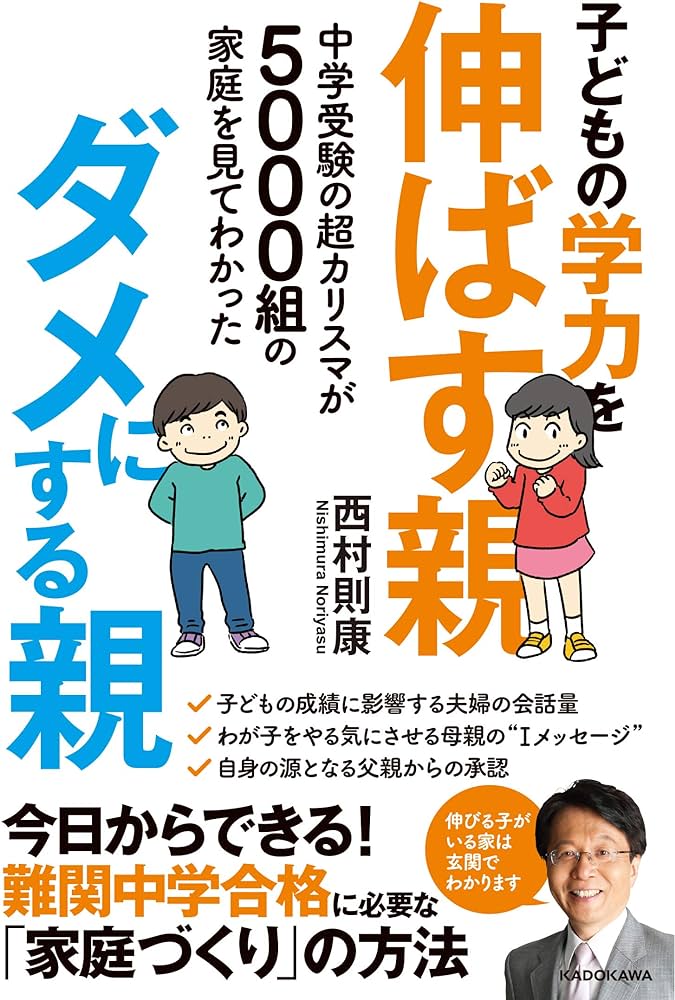
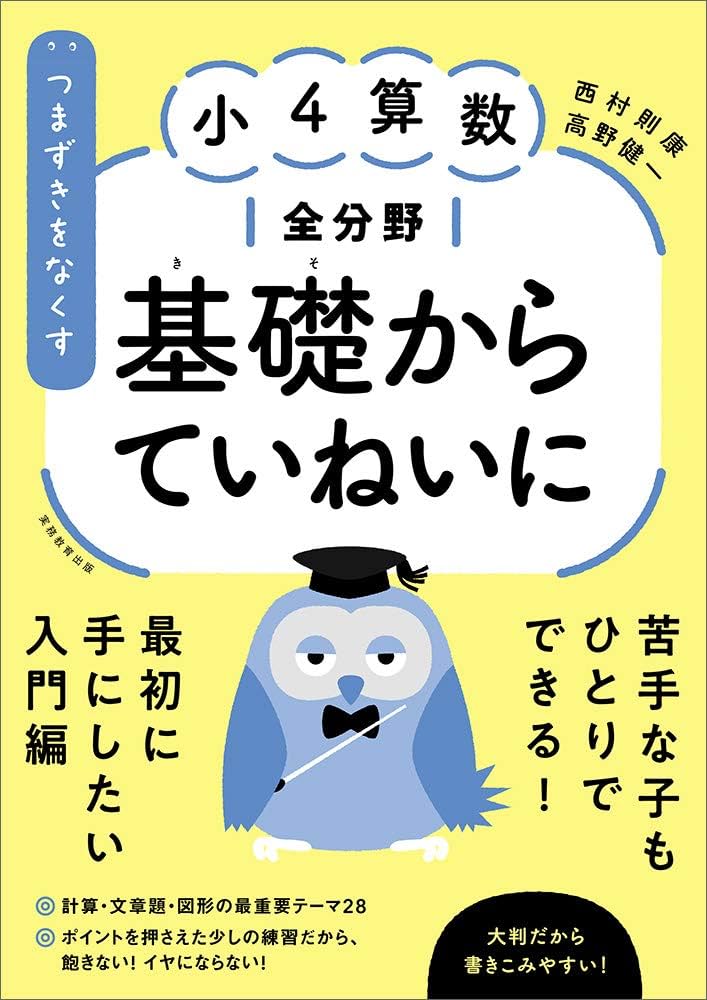
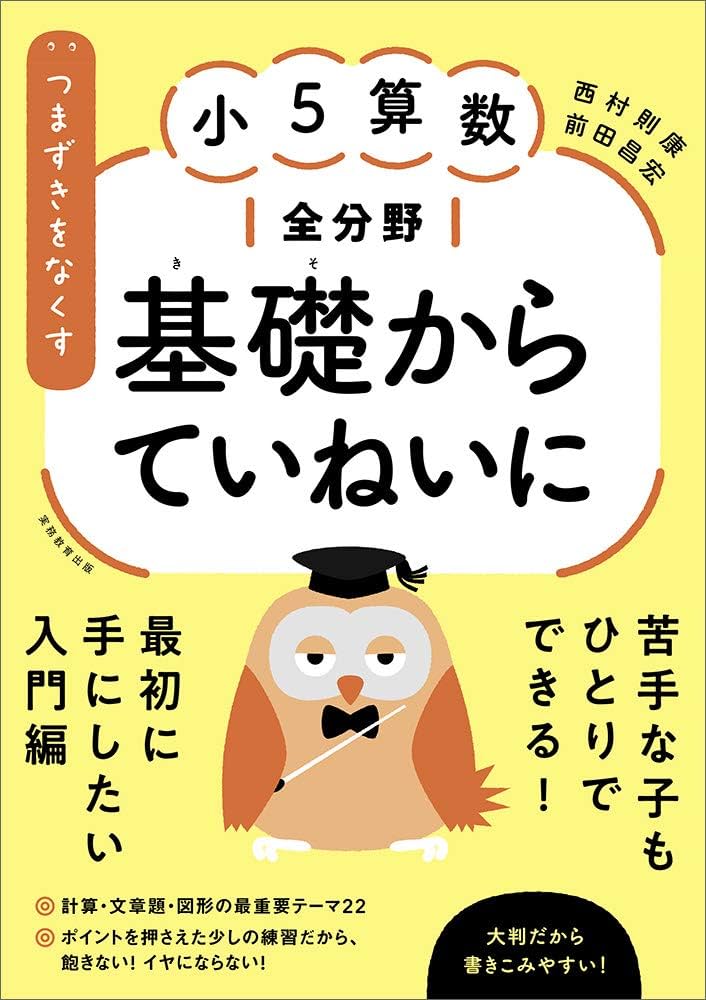
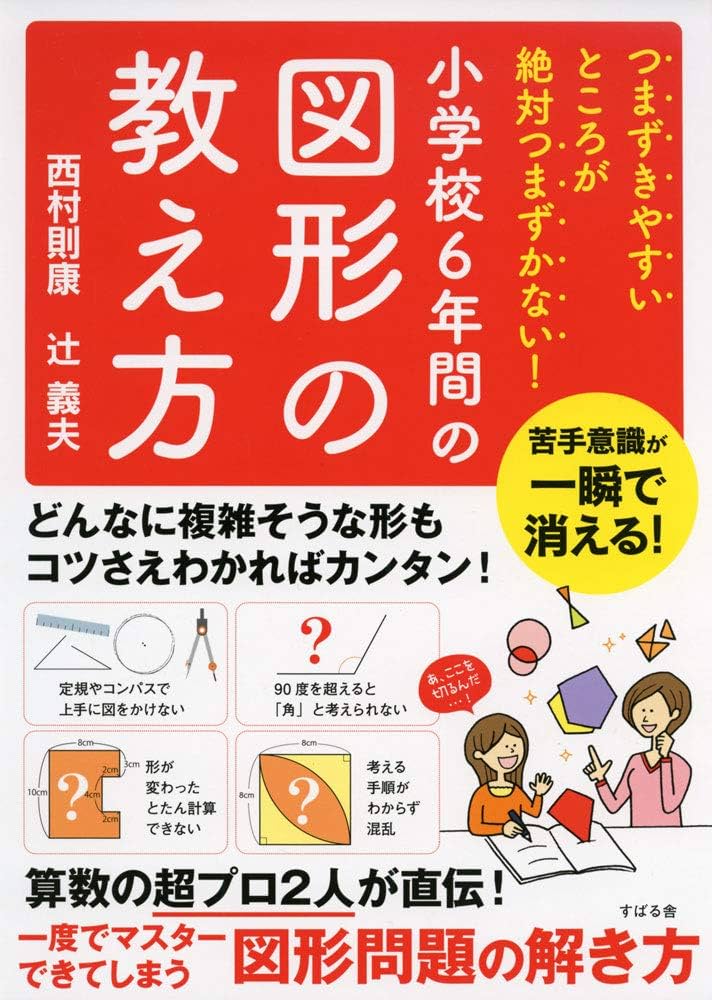
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)