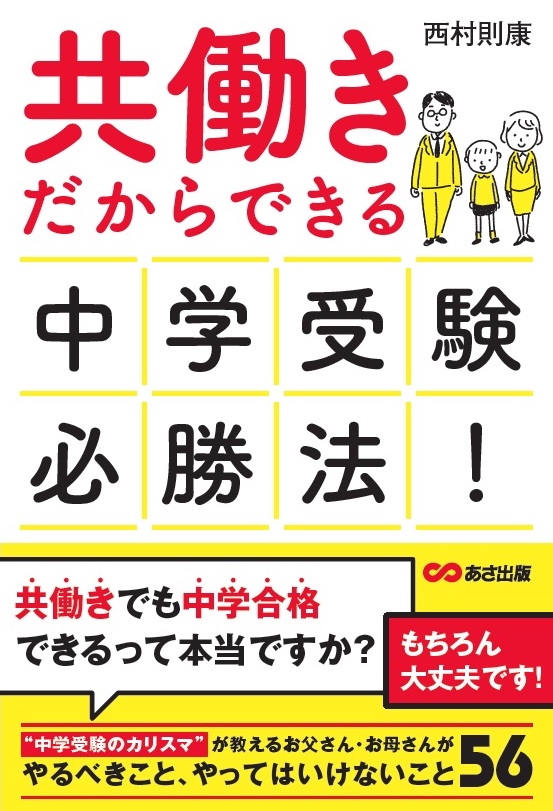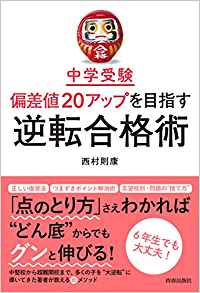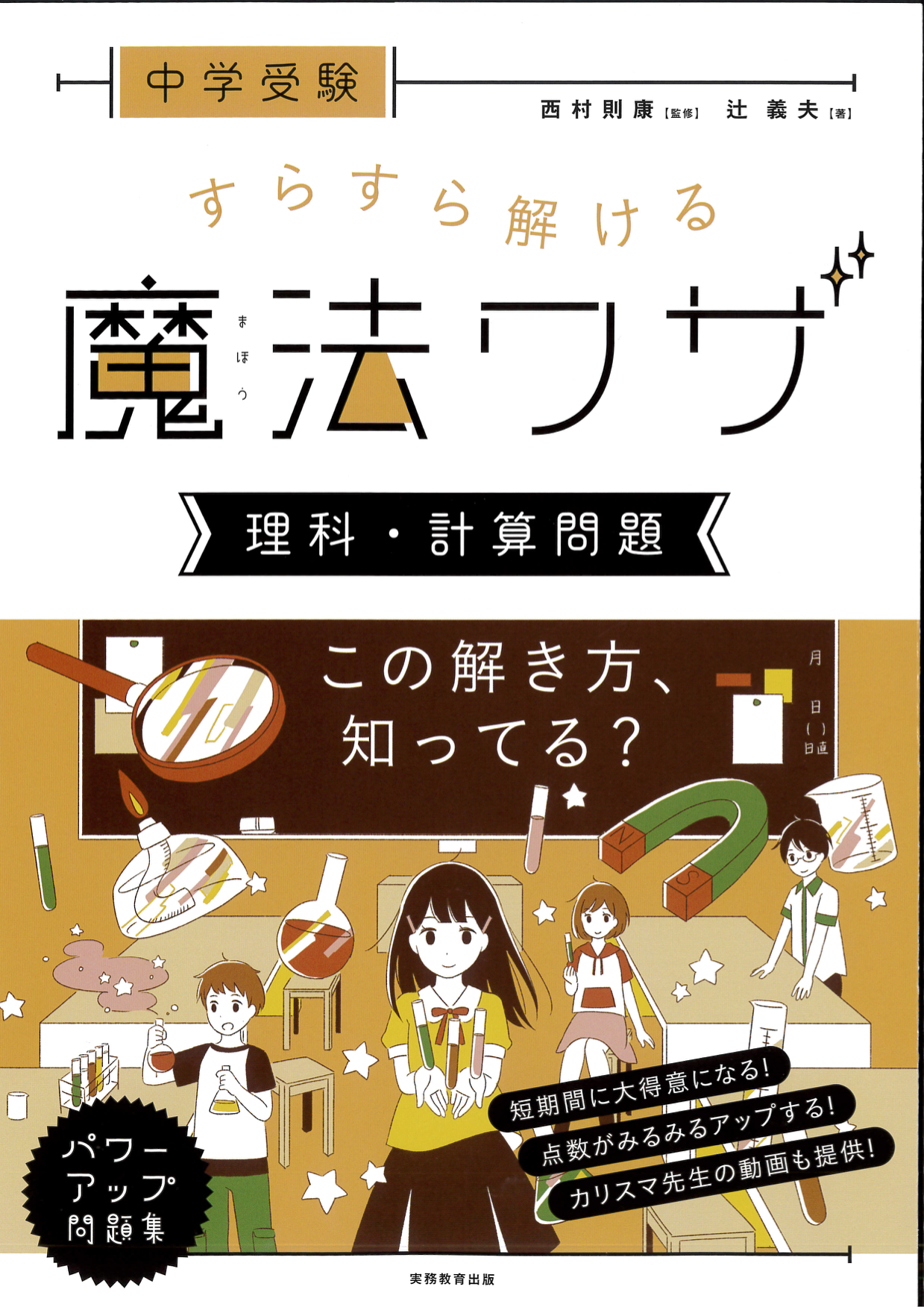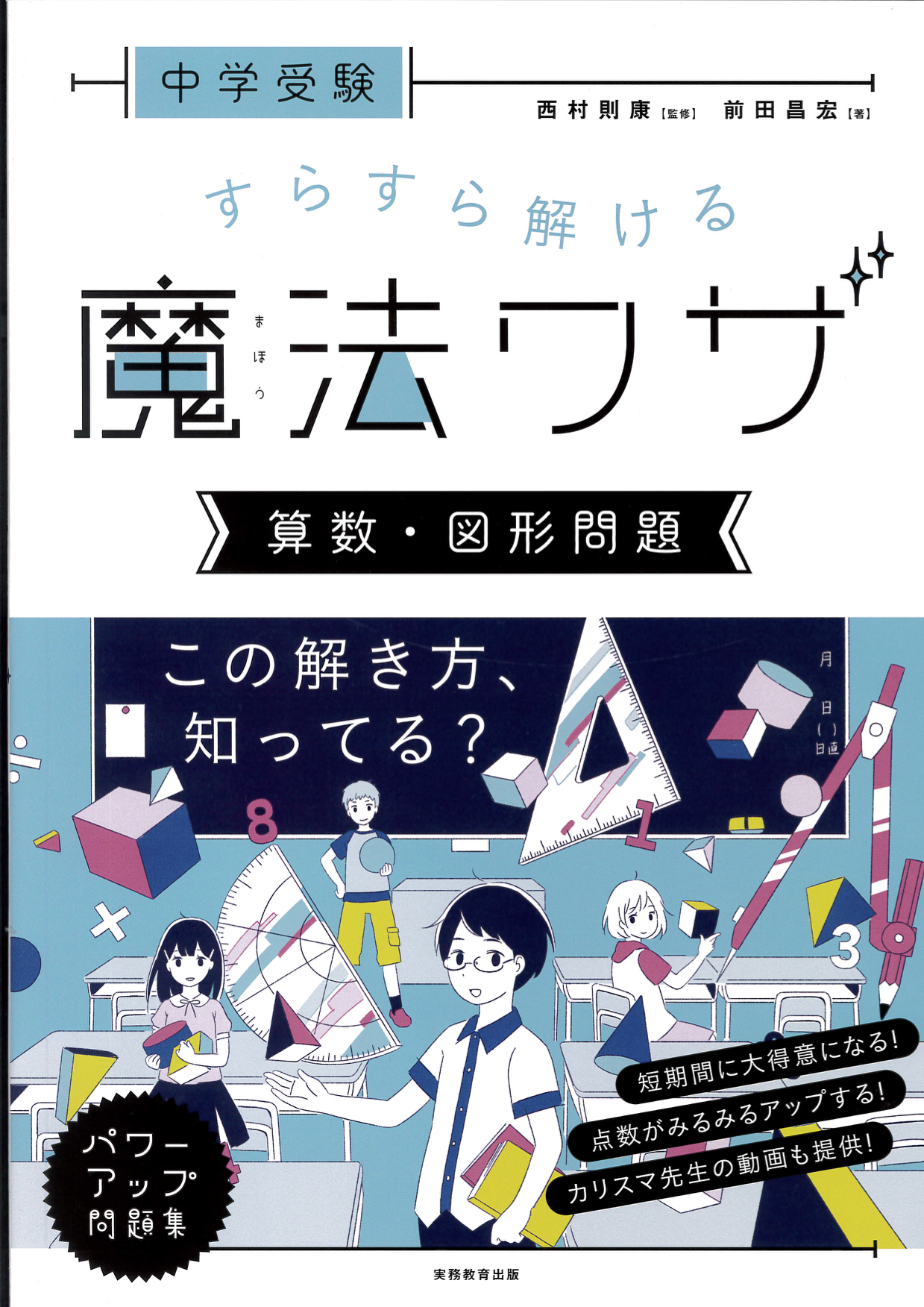目次
全体的な学習方針と計画について
カリキュラムと塾との連携について
教科別の注意点
もう6月末。来週にかけては、また全国的に気温が上がり、真夏のような気候になるようです。
体調に気をつけて過ごしたいですね。
さて今回は、夏期講習を効果的に活用し、お子さんの学力向上と負担軽減を両立させるために注意すべき点について、塾別、科目別に考えてみたいと思います。
全体的な学習方針と計画について
塾のカリキュラム学習を追っていると「やったかやってないか」という「タスク管理」になりがちですが、成績を上げるためには「学習の質」が重要です。深く理解しているか、納得しているか、注意深く問題を読んでいるか、解説を丁寧に読んでいるかといった点が大切になります。
もちろん夏期講習は忙しく、大量の課題が出されます。そこで1日1問でいいので、タスク管理型で焦って解くのではなく、1問をじっくり読み、注意深く解き、解説を丁寧に読むことを目指してみましょう。
このような学習を心がけることで、お子さん自身が間違えやすいポイントが見えてきます。
最初は1日に1問から始めて、苦手教科の中から「得意の核」を作ることを目的としましょう。
その「1問」ですが、自己肯定感を高めるためにも「あと少しで解けそう」な問題を選ぶことが大切です。
夏期講習開始までに、何をするのかを明確にした学習計画を立てることが非常に重要です。
まずはこれまでのテストの正答率表を頼りに、「正答率が高いのに間違いが多かった分野はどこか」をチェックすることから始めましょう。
ただし、計画はあくまで出発点であり、お子さんの状況や体力面に合わせて、必要に応じて内容や回数を変更する柔軟性を持つことも大切です。
カリキュラムと塾との連携について
サピックス
サピックスの夏期講習は、日程だけ見ると余裕があるように見えますが、実際にカレンダーに落とし込むと「2日行って1日休み」のようなハードな日程になるため、非常に忙しいです。
早稲田アカデミー
早稲アカの小5夏期講習は特にハードであり、カリキュラムも復習内容と新出単元の折衷型になっています。事前にどれが復習でどれが新出単元なのかを確認しておく必要がありますね。
四谷大塚
四谷大塚は夏期講習とテスト、そして8月後半の特訓(すべて必修となっています)で計26日間もの拘束がありますが、カリキュラム内容がざっくりしているという指摘もあります。場合によっては、必修とされている8月特訓でも、受講を断ったり、時々休んだりする(8月特訓は純粋な復習内容のため)ことを検討してもよいでしょう。
浜学園
浜学園の夏期講習は、平常のマスター講座との「二階建て」になります。つまり夏期講習で総復習を行いながら、平常授業では新出単元を習い続ける形です。必然的に平常授業優先となりますね。夏期講習はカリキュラムを確認し、あらかじめ力を入れる単元の見当付けをして臨むといいでしょう。
学習には「たくさんの知識を身につけるカリキュラム学習」と「学習のやり方を学習する」という2つの車輪があります。
塾のカリキュラムは回し続ける必要があるため、塾の学習は継続しつつ、学びの質を高める取り組みも並行して行うことが重要です。
一方で、夏期講習があまりに忙しく、終わった後にペースを崩してしまう子どもが非常に多い傾向があります。
多くの塾でやる内容が多すぎ、頭の中が混乱し、これまで解けていたものが解けなくなるというケースも見られます。
頑張りすぎている子どもに対しては、親御さんが意図的にブレーキをかけてあげる必要があるでしょう。
教科別の注意点
算数
夏期講習開始までに、特に力を入れたい重要単元(苦手単元、得意の核にしたい単元、志望校に頻出の単元)を決めておくと、夏休みに克服したいテーマがはっきりしてよいですね。
上記の単元が、お通いの塾の夏期講習で扱われているか、確認しておきましょう。
5年生では、平面図形や割合・比を重点的に学習することで、割合や比の考え方を速さや水量の問題にも応用できる力をつけることを目標としたカリキュラムの塾が多くなっています。
国語
小4・小5では、語彙強化が重要なテーマです。夏休みは語彙強化に時間を割く良い機会です。
小6では、サピックスでは夏から前倒しで過去問の宿題が出ます。
他塾にお通いの場合でも、場合によっては過去問をやり始めることを検討してよいでしょう。
夏期講習中は忙しく大量の問題を解くため、読み方が雑になり、得点が下がってしまうケースがよくあります。
また読解については、普段の授業の先生と夏期講習の先生で異なる指導がある場合もあるため、注意が必要です。
量と質のバランスが重要であり、長文を読むのが遅い子でも、1日1問など毎日コツコツと解く習慣をつけることが夏休み後の伸びに繋がります。
普段の家庭学習では負担が大きくなりがちな文章読解を、夏休みの時間の余裕を活かして、朝の塾が始まる前などに生活のペースに取り入れることも有効です。
理科
理科は他教科に比べて、単元による出来・不出来が顕著に出やすい科目です。
まずは夏までに、これまでのテストの正答率表をチェックし、お子さんがどの単元でつまずいているのかを割り出しましょう。
生物や地学の知識がついていない場合であれば、夏期講習に先駆けて塾で使用している暗記用のテキストなどを使って学習しておきます。
このようにして、一問一答レベルの知識だけでも学び直しておけば、夏期講習の授業の理解度がぐんと上がります。
5年生以下の学年のご家庭は、6年生にくらべると夏期講習の日程・時間に余裕があると思います。ぜひ遊びやお出かけのメニューも準備してあげてください。
社会
社会のテストの地理の点数が伸び悩んでいるお子さんの場合、夏休みは、地理の図表(農産物や工業地帯の順位・割合)の読み方を強化することを1つのテーマにするとよいでしょう。
歴史では、出来事と人物を結びつける学習(例:人物カードの作成)が効果的です。
公民は、時事問題と結びつけて学ぶと理解が進みます。今起こっている米の値段の高騰や円安などについて、親御さんが会話の中で話題を振ってあげるなどしてもいいですね。
ふだんの家庭学習では社会の学習時間を確保しにくいものですが、夏期講習の「空き日」に最低限のポイントに絞って学習したり、「3日間で地理をまとめる」など集中して学習する方法も有効です。
夏休みは長いようですが、夏期講習に忙殺されていると(特に四谷大塚や早稲田アカデミーなど日程のボリュームが大きな塾)、あっという間に終わってしまいます。
「なんだかバタバタしている間に終わってしまった」となってはもったいないですね。
まずは夏期講習の日程をカレンダーに落とし込み、どのような毎日になるのかイメージすることから始めてみましょう。
お子さんがよい状態で夏を迎えられることを願っています。
受験相談・体験授業お申込み
必須の項目は必ず入力してください。

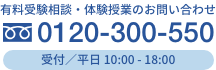


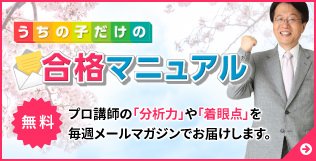



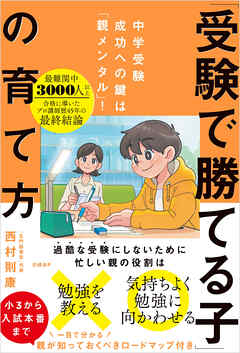
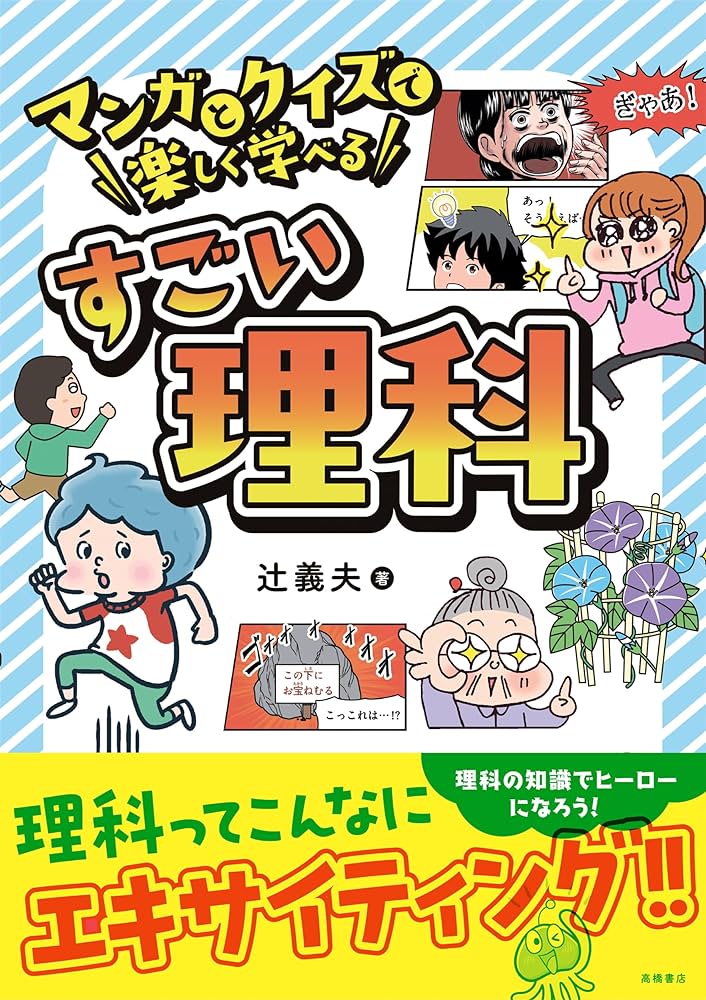
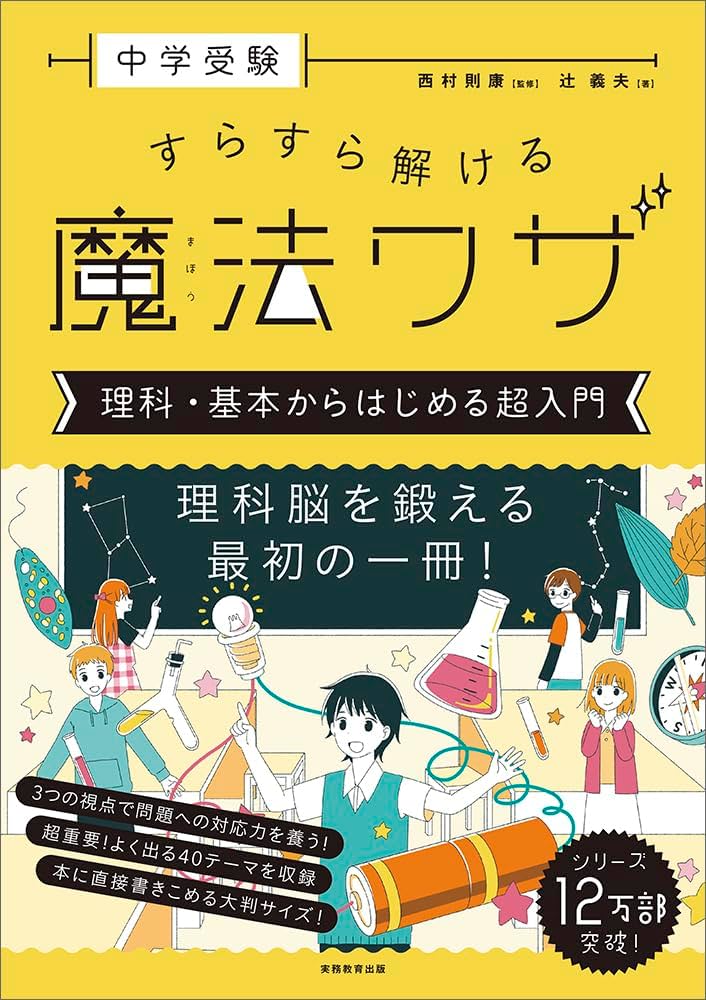
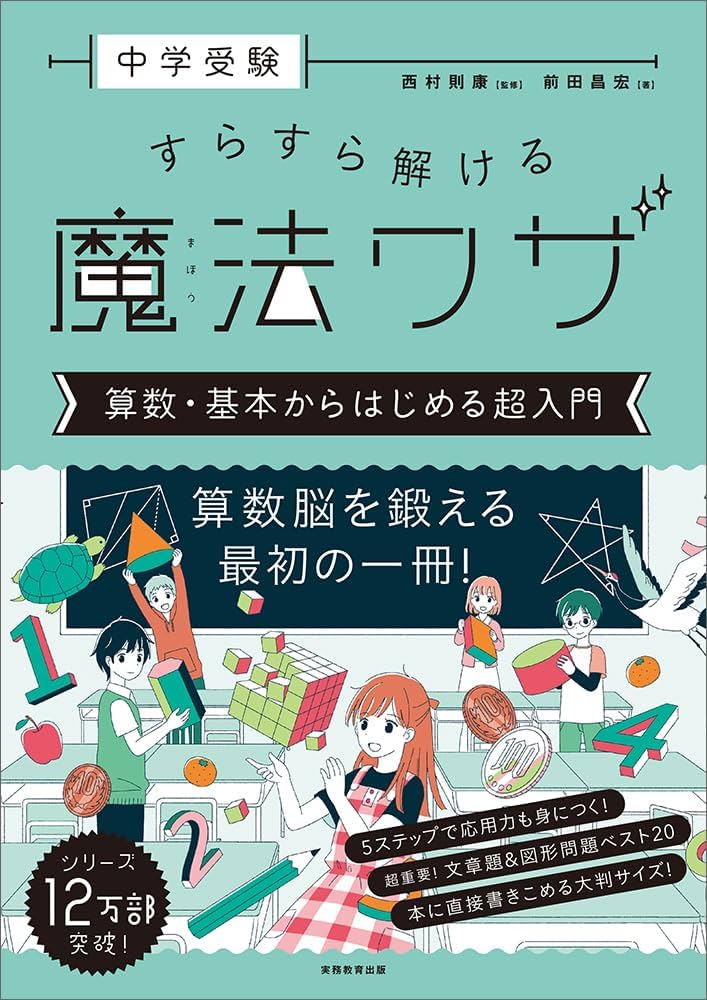
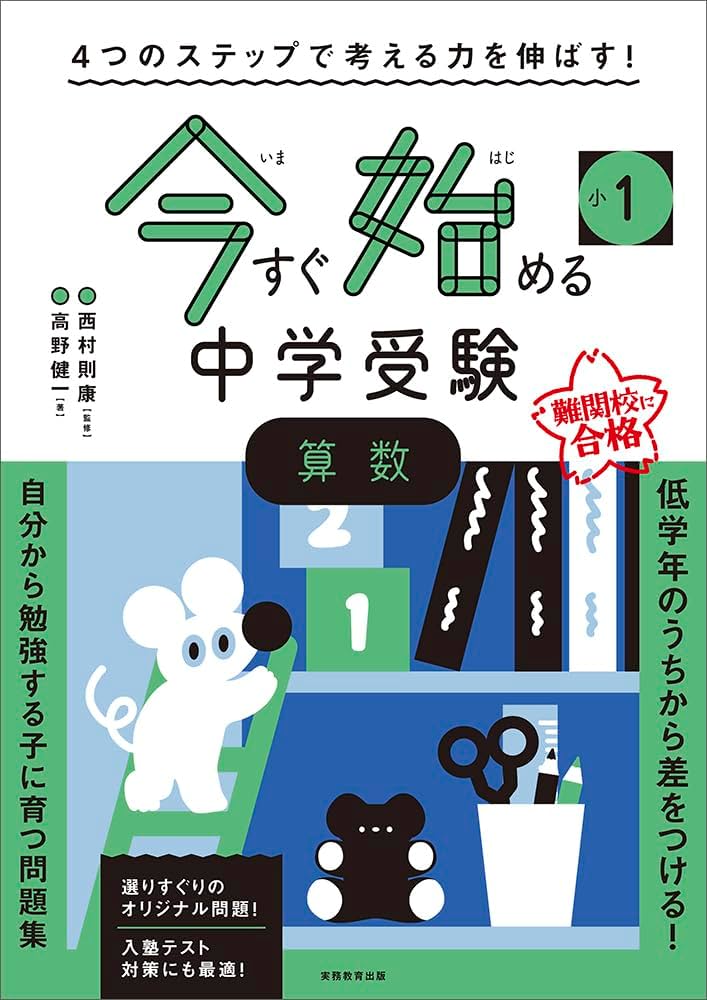
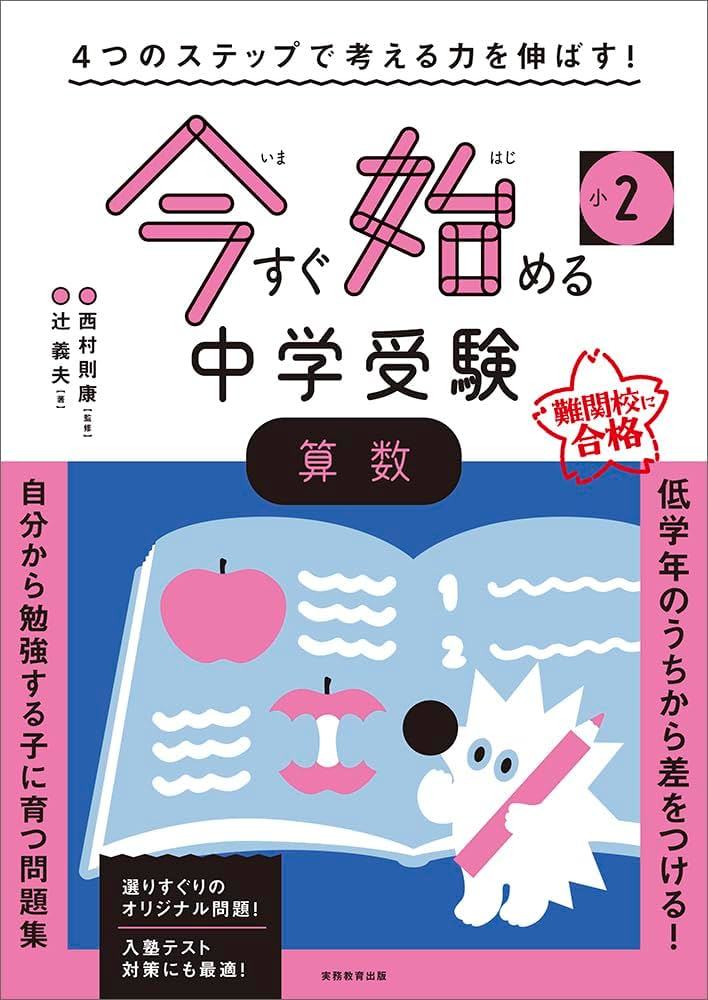
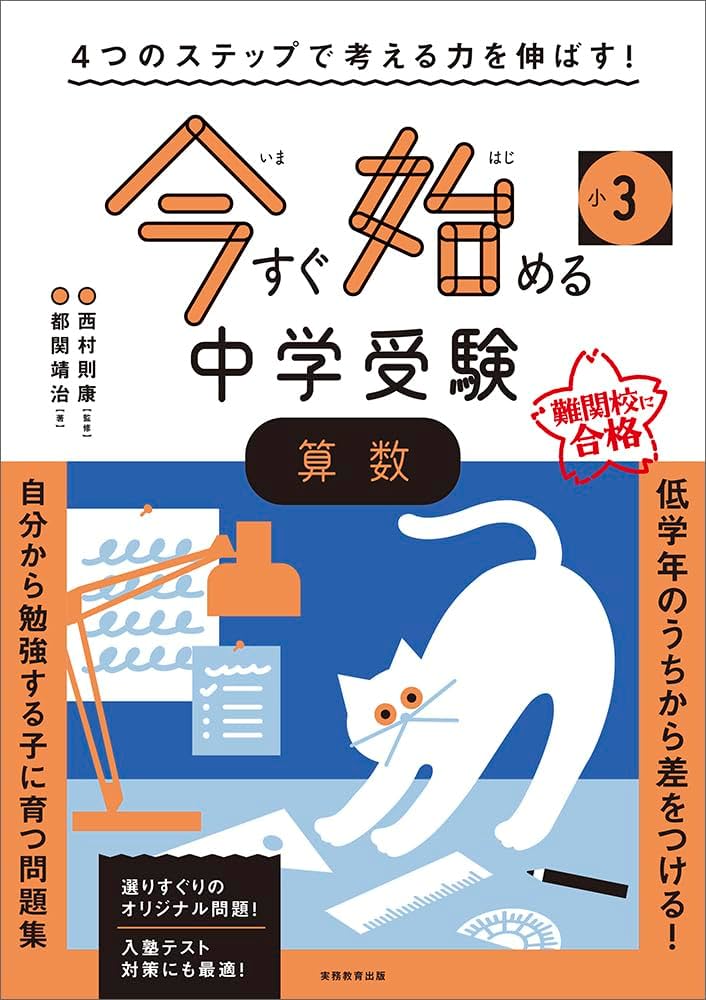
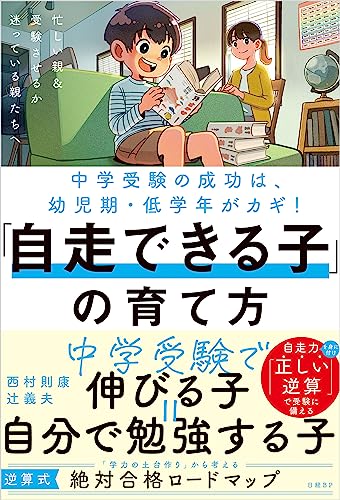
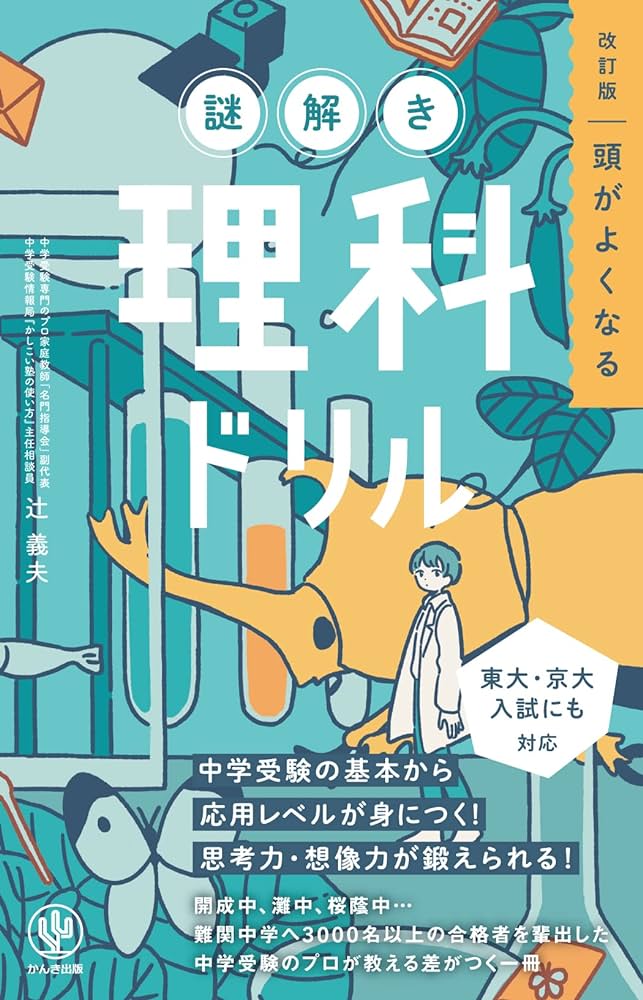
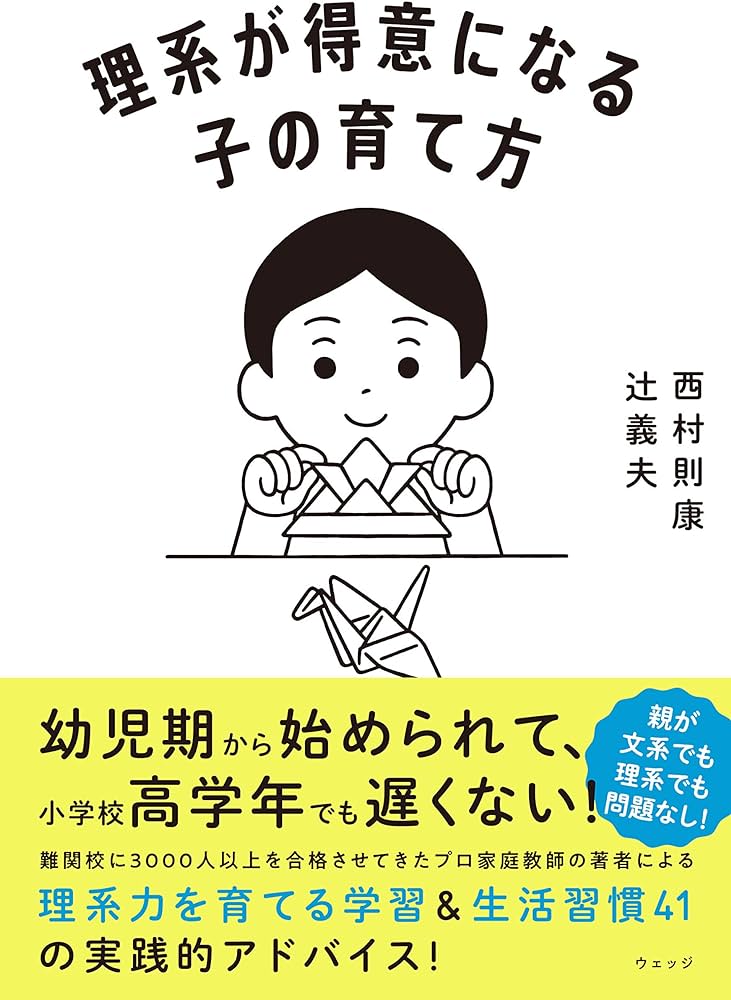

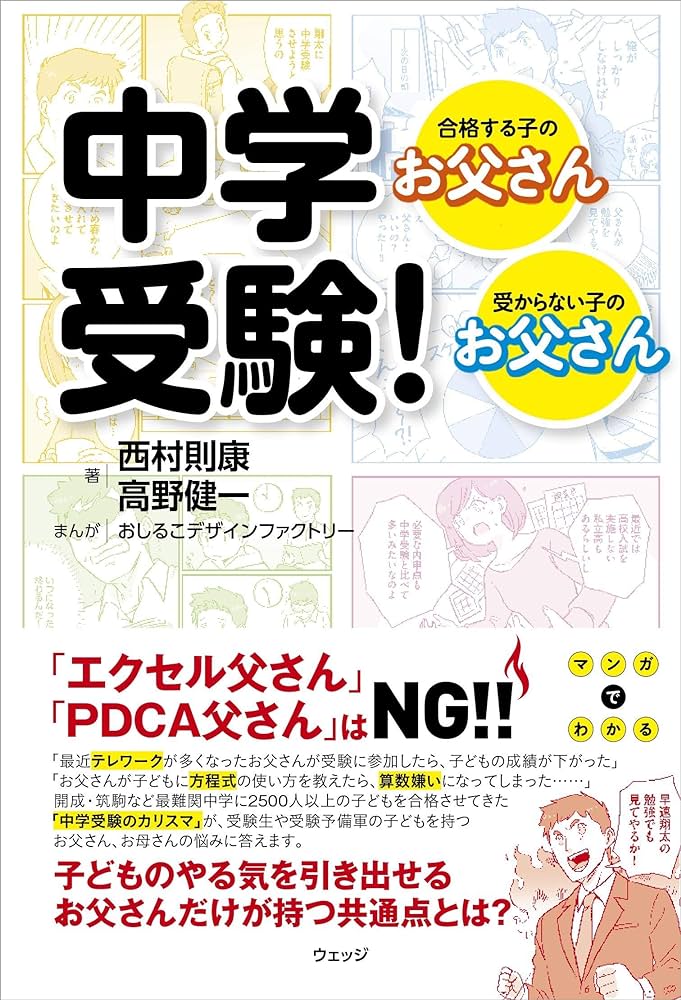
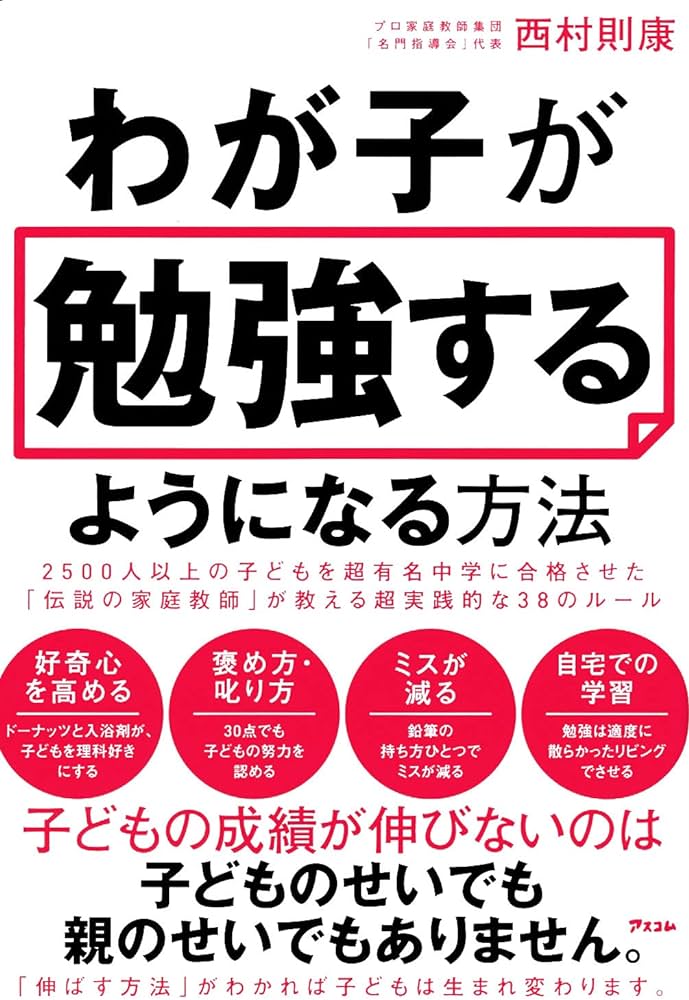
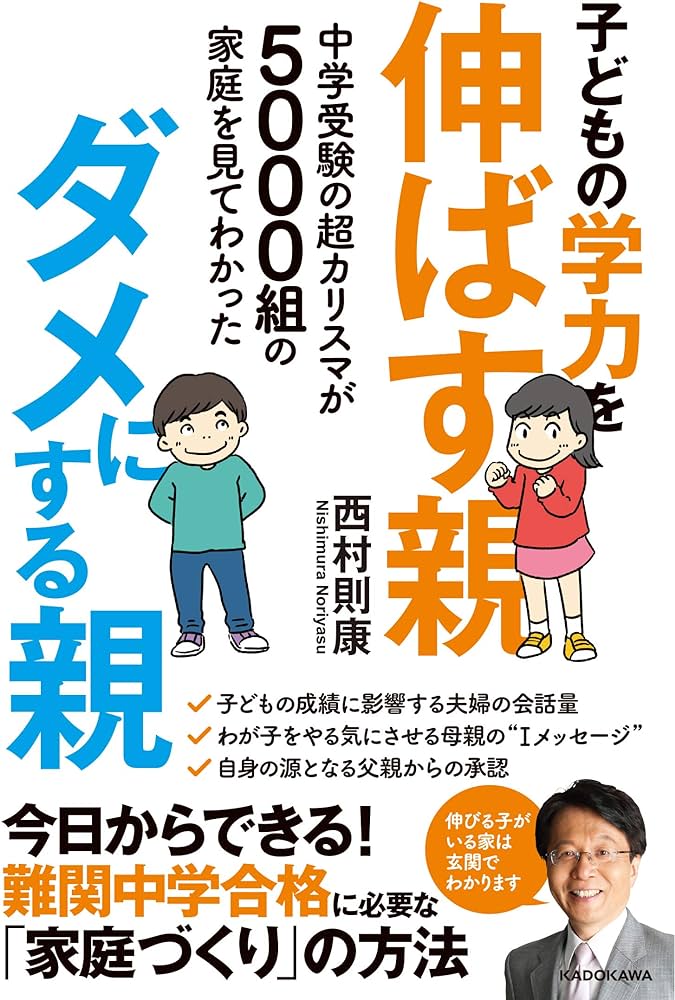
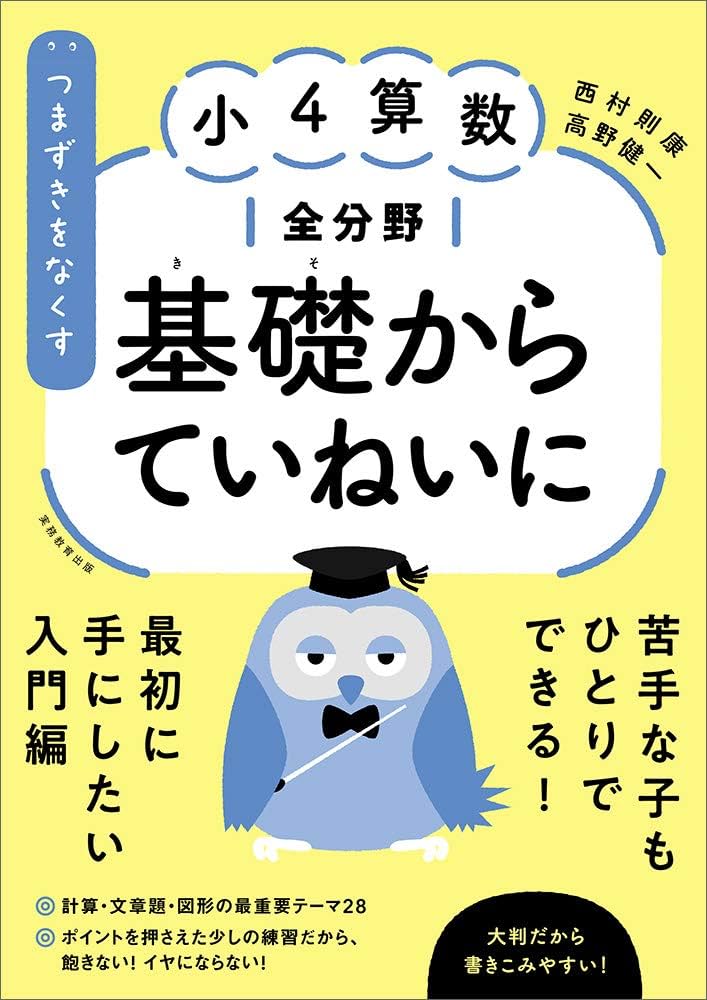
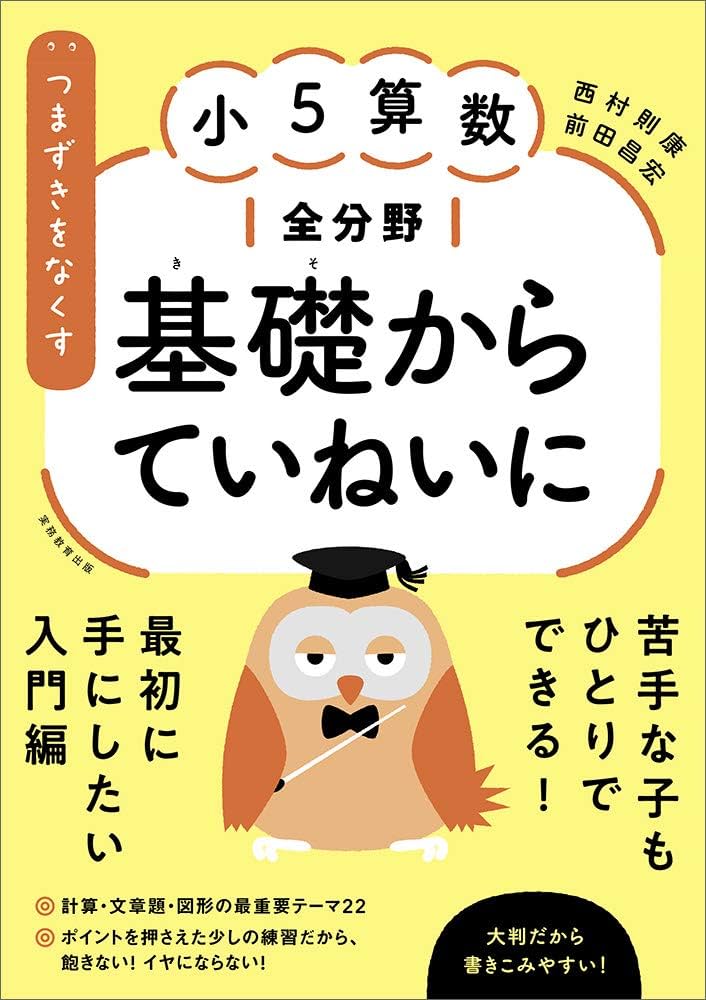
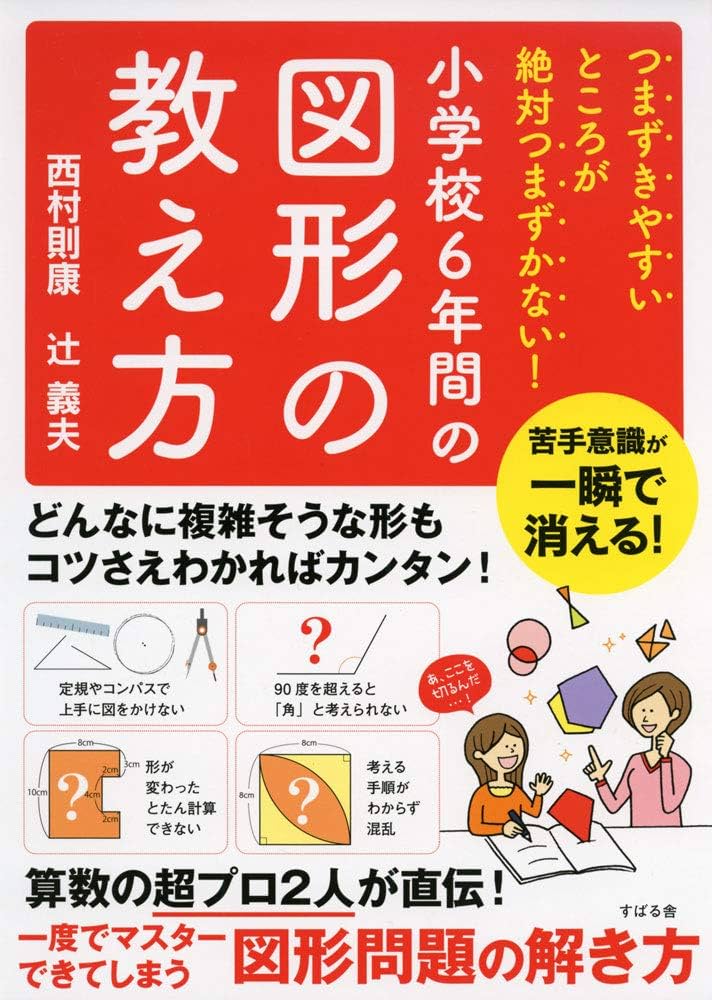
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)