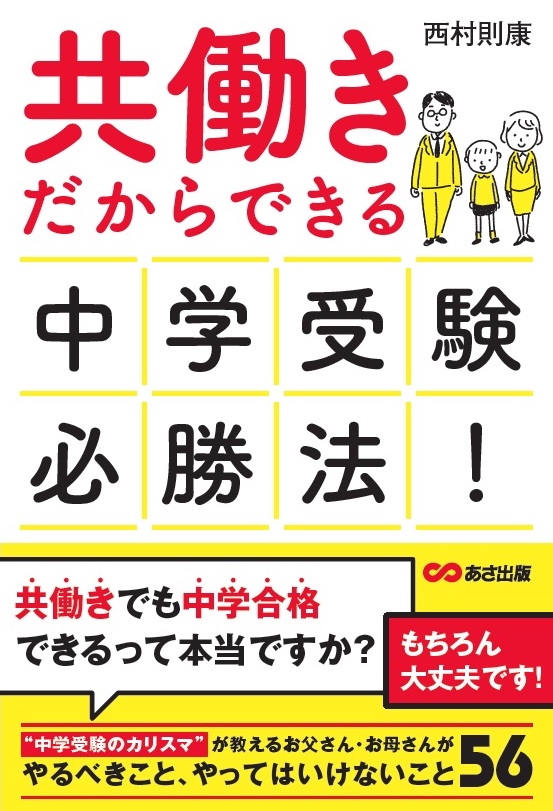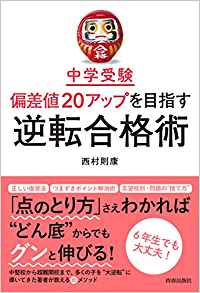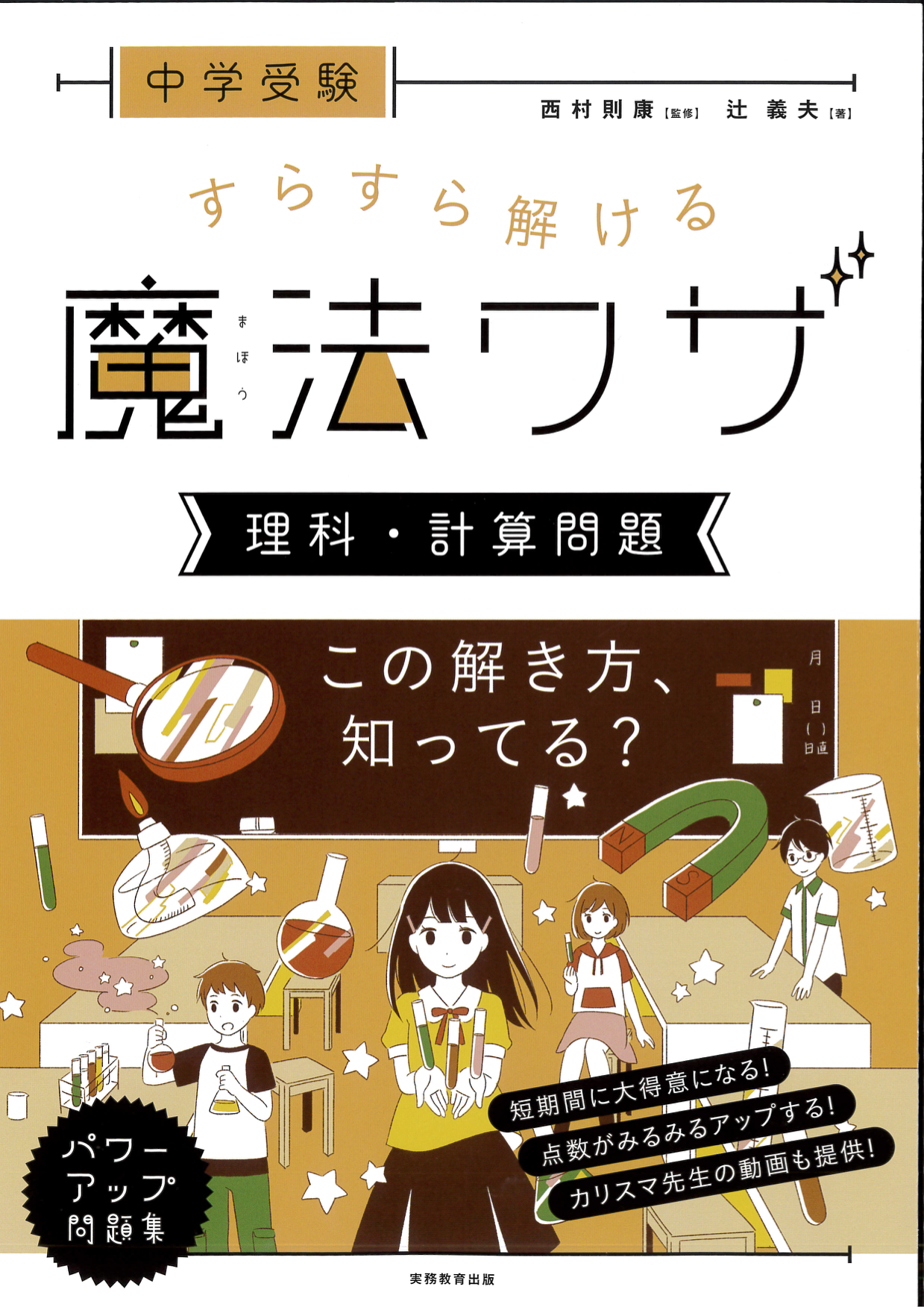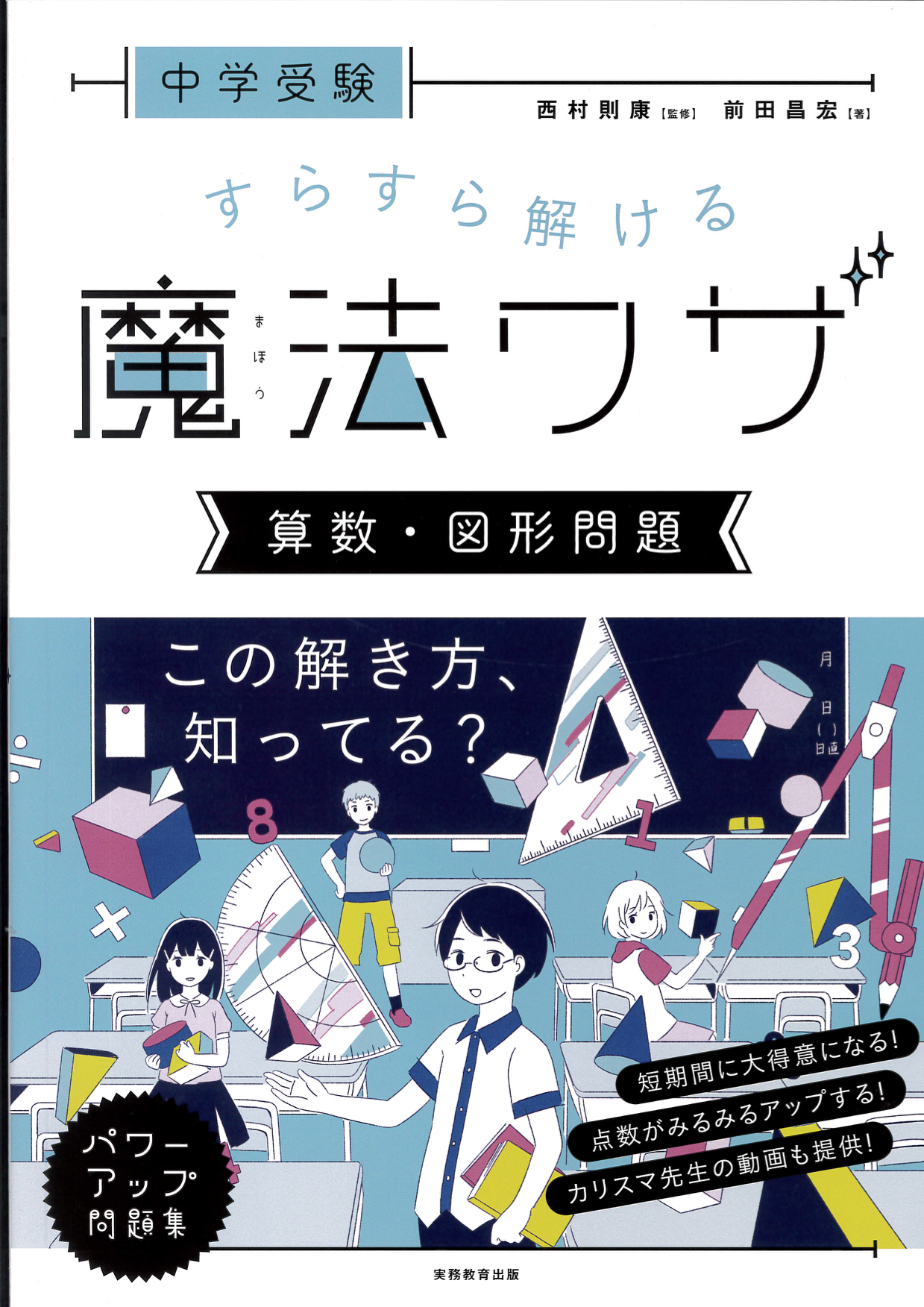目次
過去問演習の時期、やり方に正解はあるの?
過去問演習に関する4つのポイント
過去問演習の注意点は?
夏休みが近づくと、中学受験生の皆さんから
「受験校の過去問はいつから解きはじめたら良いの?」
という質問が増えてきます。
そこで今回は、過去問演習について考えてみたいと思います。
過去問演習の時期、やり方に正解はあるの?
首都圏や大阪圏のように私立中学がしのぎを削っているエリアでは、学力の輪切りが進んでいます。
たとえば偏差値50〜55くらいの子は第1志望がA中学かB中学、55〜60だとC中学かD中学、というように、同程度の学力と得点力を持っている子どもたちが同じ学校を受験しているということです。
その結果として、多くの子どもたちがひしめくボーダーライン付近の混戦から一歩抜け出すためには、該当校の傾向対策が非常に重要なポイントになるため、過去問学習の量や時期、やり方が中学受験の合否を左右すると言っても過言ではありません。
ところが、夏休みは塾の学習量や課題量が多いため、ご家庭で別途、過去問に取り組む時間を取るのは、なかなか難しいものですし、過去問についての指示内容も塾によって大きく異なります。
夏期講習を前にしたお友達同士、親御さん同士の会話などから過去問演習についての違いを耳にし、
「うちの塾では過去問は秋からで充分と言われていたのに、○○さんの塾は夏休みから過去問演習が始まるらしい」
「あなたの塾では夏休みの課題に過去問が出ているけれど、△△さんは塾の先生から、夏休みのうちはまだ過去問に手を出したら絶対にダメと言われたんだって……」
などと、お子さんたちや親御さんが不安になったり混乱されたりするのも無理はありません。
たとえばサピックスや四谷大塚などでは、夏期講習中から過去問演習が家庭学習の課題の一つとなりますが、本来、過去問演習は、塾の志望校別日曜特訓の有無やカリキュラム、志望校の入試問題傾向、ご本人の今の学力、併願校の入試問題傾向など、あらゆることを考慮して考えていく必要があります。
ですから、それぞれの塾での過去問演習のタイミングは決まっているものの、細かなこと(やり方や、いつ頃から、どの学校のものから取り組むか等)については、ご相談への返答がお一人お一人全く異なるのです。
過去問演習に関する4つのポイント
過去問演習に関して、大きなポイントは次の4点だと考えています。
1. 塾の志望校別日曜特訓と並行し、10月あたりからやっていくとよい。
2. 設問の文章が長かったり、記述の文字数が多かったりなど、特徴がはっきりしている学校への対策は、早めに始める。
(前述の通り一人一人のケースにより判断は異なるが、大体夏休み後半や9月あたりからが目安。志望校の過去問だけではなく、傾向の近い学校の問題も数多く解くことが理想的。)
3. 基礎学力が、志望校に明らかに届いていない場合は、弱点対策が最優先。
この場合、傾向、対策は二の次で、11・12月頃から集中的に行う。
4. 併願校は、入試問題の傾向が似ている学校から探すことが出来ると理想的。
そうできない場合でも、あまりにも傾向のかけ離れた学校をいくつも併願するのはとても危険であることを覚えておく。
上記のことから考え、早めの過去問学習が必要になってくるのは、たとえば下記の学校などです。
・開成の国語
・麻布の算数・国語・理科・社会
・桜蔭の国語・算数
・栄光学園の算数・理科
・筑駒の算数・国語
・武蔵の国語・理科
・渋幕の算数・理科・社会
・渋渋の理科
・学習院女子の国語・理科
・海城の理科・社会
過去問演習の注意点は?
また、過去問演習で注意したいこととして、下記があります。
1. 制限時間を守る。(一人一人のケースによるが、常に1〜5分短く解くようにするのが効果的な場合もある)
2. 問題文を読み飛ばさない。
3. やりっ放しにせず、間違った問題の復習をしっかり行う。
4. 間違った問題、分からなかった問題をすべて復習しない。(赤本のデータ欄などを確認し、合格者平均点に届く点数くらいを目処にすると良い。)
5. 解説が詳しい過去問題集を使うと良い。
(詳しくなくても、塾の先生や個人指導の先生にしっかりと丁寧に解説してもらえば問題ない。過去問の解説は最低限のため、どれを使っても、それだけで深く理解するのは困難な場合がほとんど。)
6. 解答用紙は、拡大コピーして使うと良い。(特に算数)
過去問演習の一つの大目的は、入試問題を見たときに、
「この問題はどうやって解くのだろうか?」
と、その解法を自力で見つけ出すことができるようになること、また、今解いている問題が、過去に解いたどの問題と似ているのか、どの知識や解法を使えば解けそうなのかを瞬時に判断できる力を養うことです。
6年生の夏休み頃では「最終的な合格者」でも解けないものばかりです。
今どれくらい解けるかということよりも、解いてみて解けなかった、わからなかった問題をきちんと理解し、こんど類似した問題に出会ったときにはしっかり対処できる状態にしておくことが何より大切だということを忘れず取り組んでください。
また、夏休み前の今のうちに、受験生の皆さん、もしくは親御さんが「行きたい、気になる学校」の過去問をチラッと見ておくと、志望校、併願校の検討にも役立ちますし、過去問演習のちょっとした心の準備も出来るのでおすすめです。
あらかじめ第一志望校などの過去問を少し見ておくだけでも、たとえば
「開成や麻布中は国語の解答欄がほぼ記述で、選択問題が極端に少ないのか!」
といったことや、
「麻布中の理科は長文問題で、今まで見たことも聞いたこともない話題の文章を読んで解答しなければならないことが多そうだなぁ」
といったことが分かり、普段からどんなことに気を付けたり、学習でどこに力を入れたりしたら良いかの参考になると思います。
中学受験生の皆さんが、元気に充実した夏休みを送り、それぞれに効果的な過去問演習(もしくはその準備)が出来るよう、応援しています。
受験相談・体験授業お申込み
必須の項目は必ず入力してください。

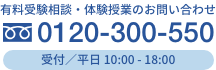


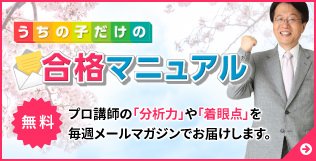



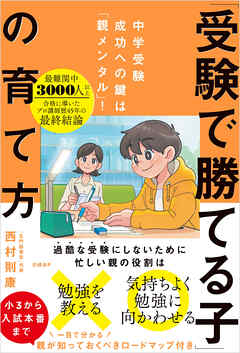
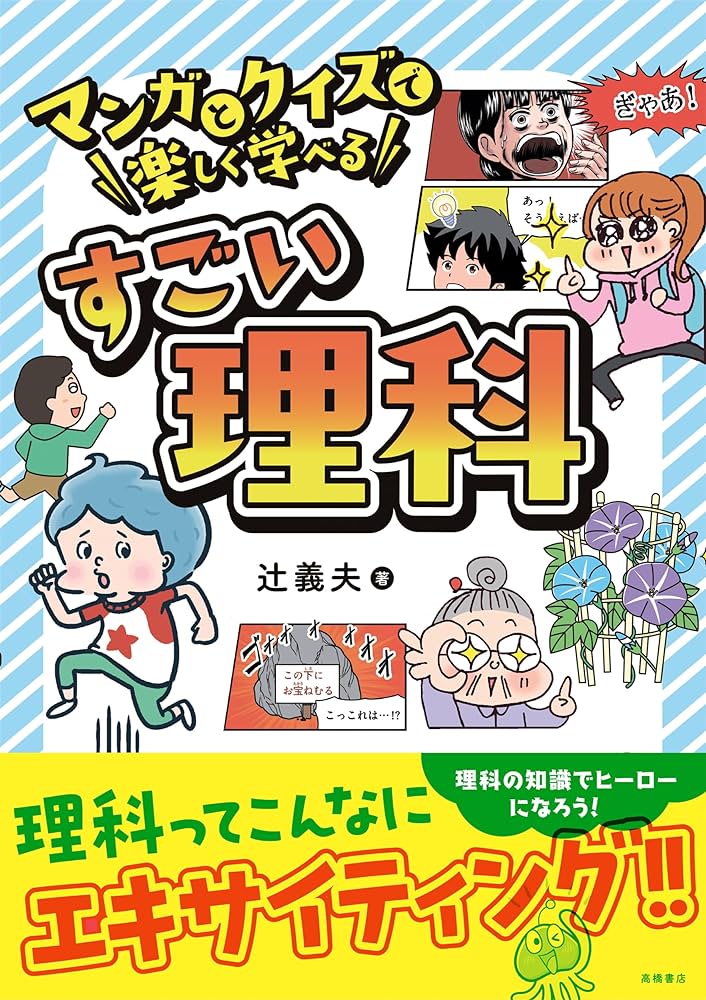
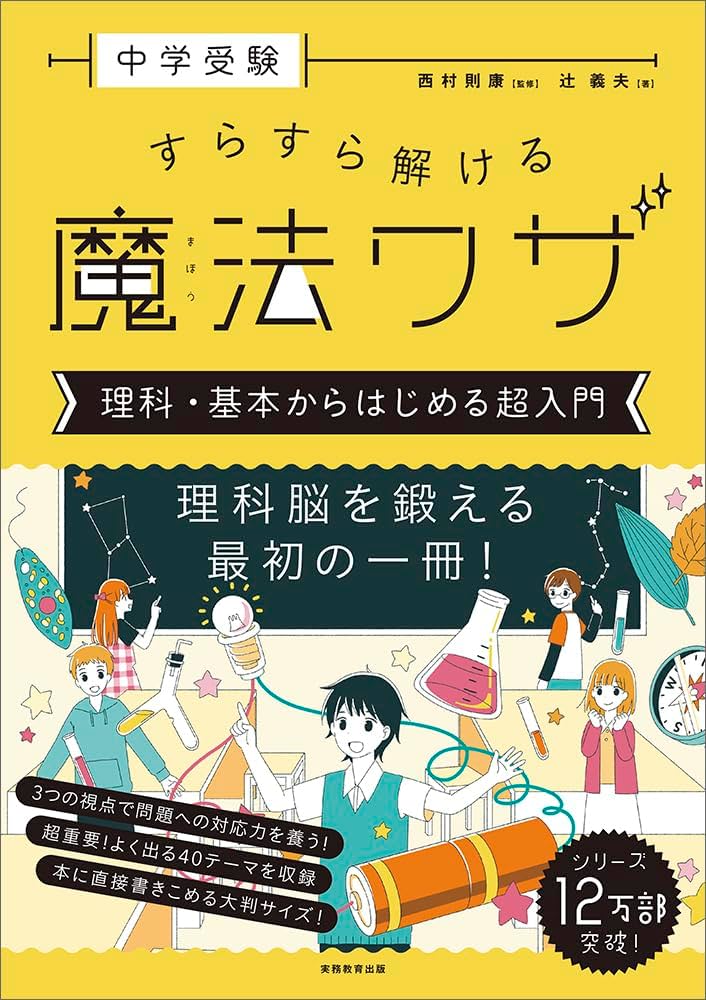
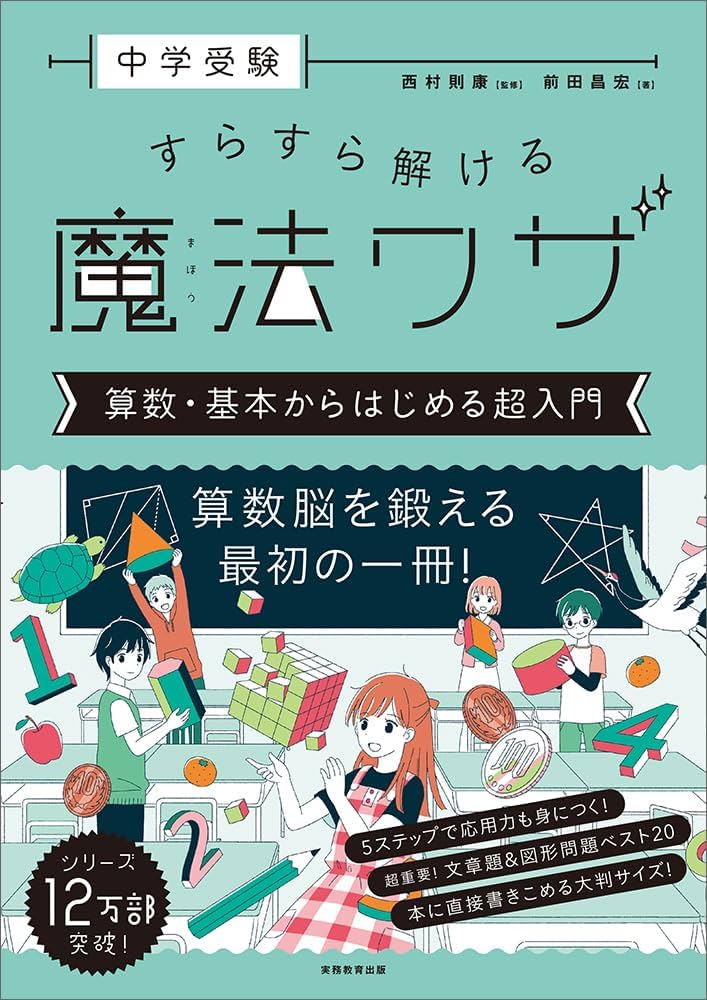
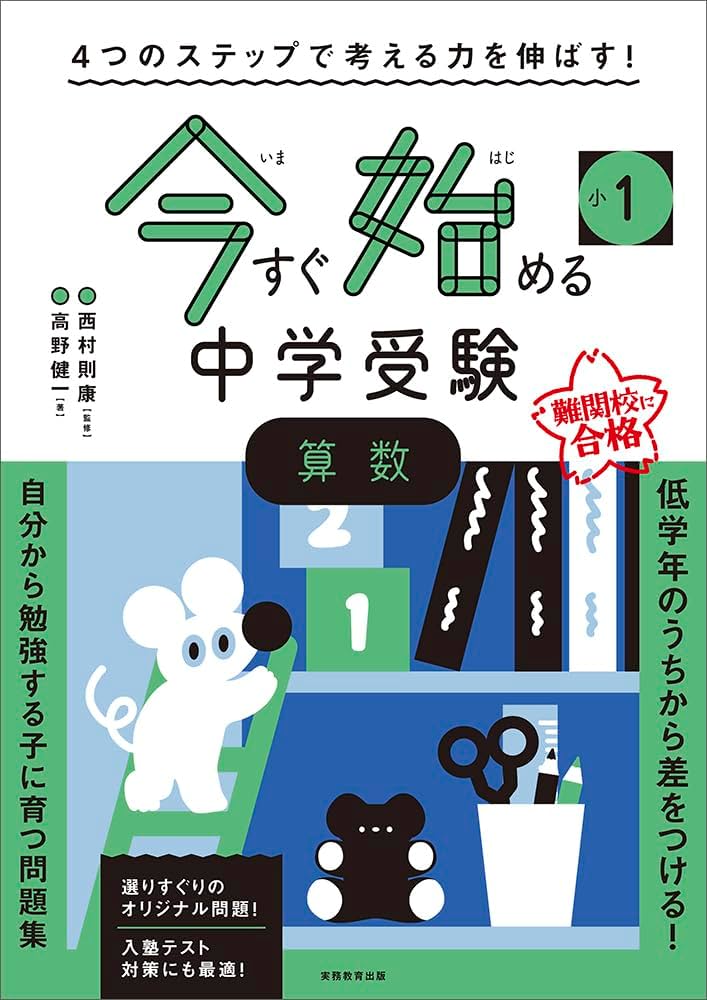
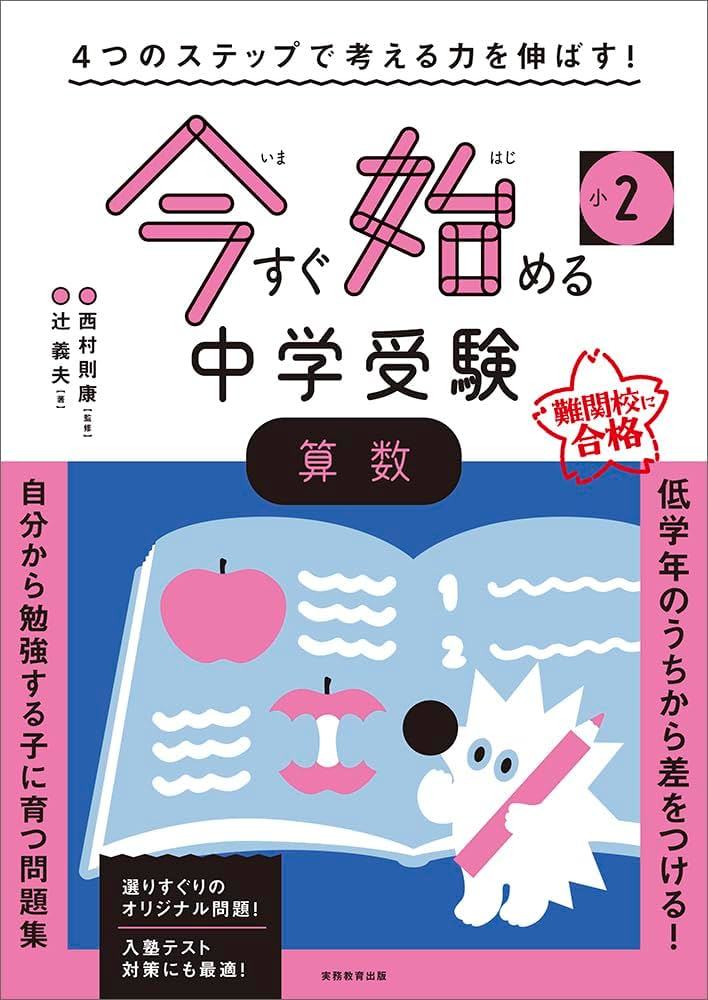
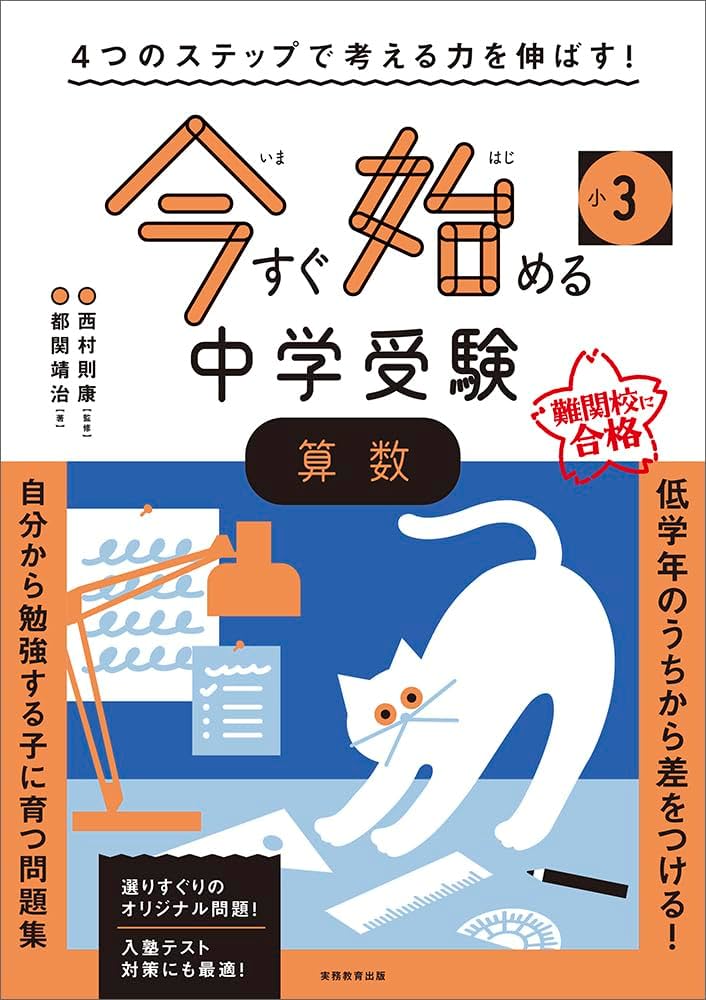
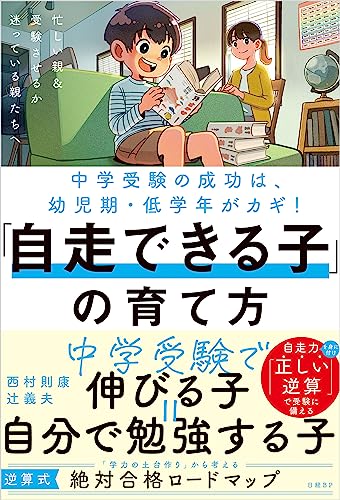
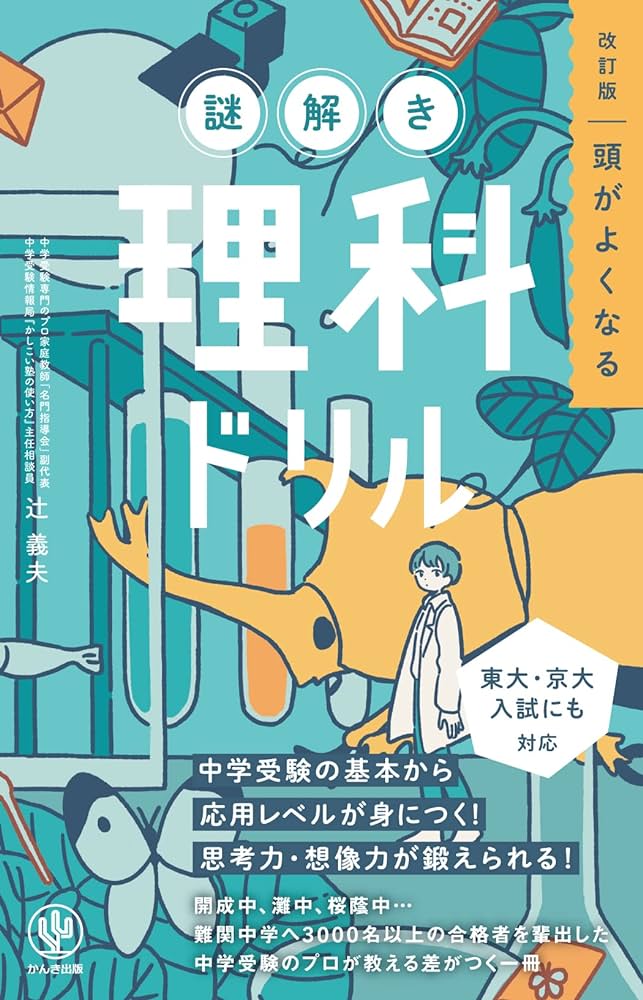
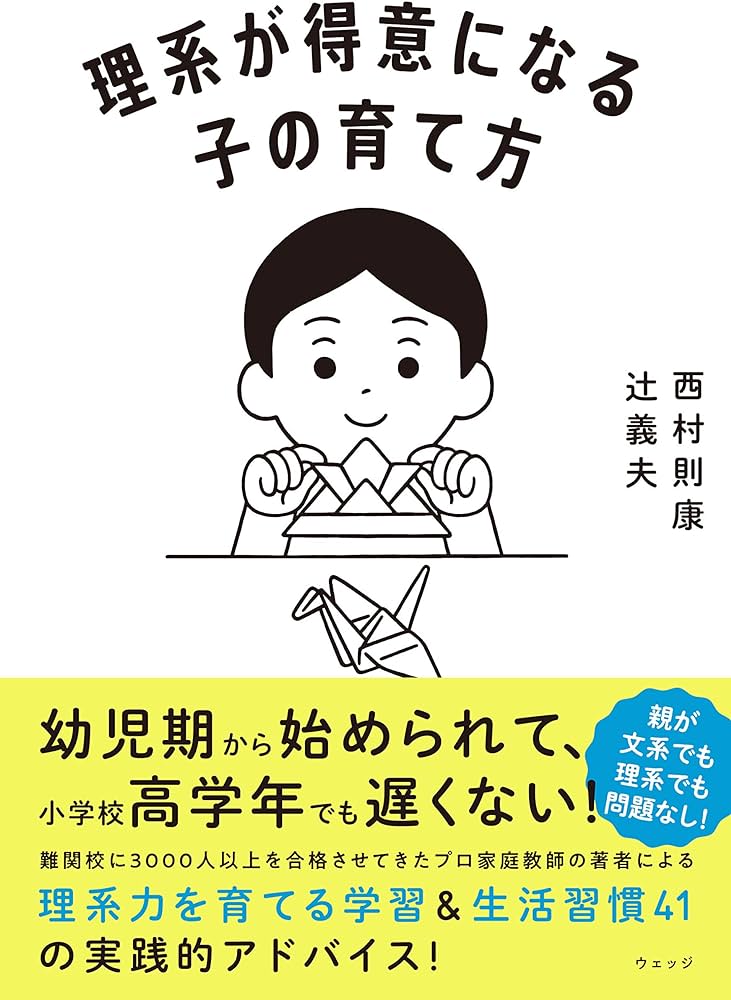

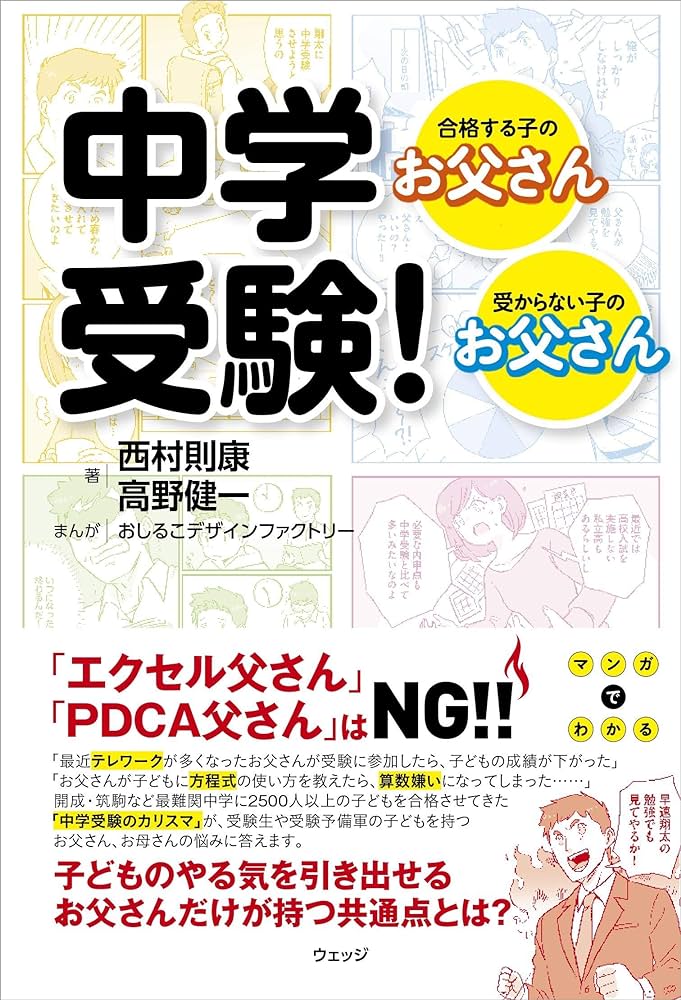
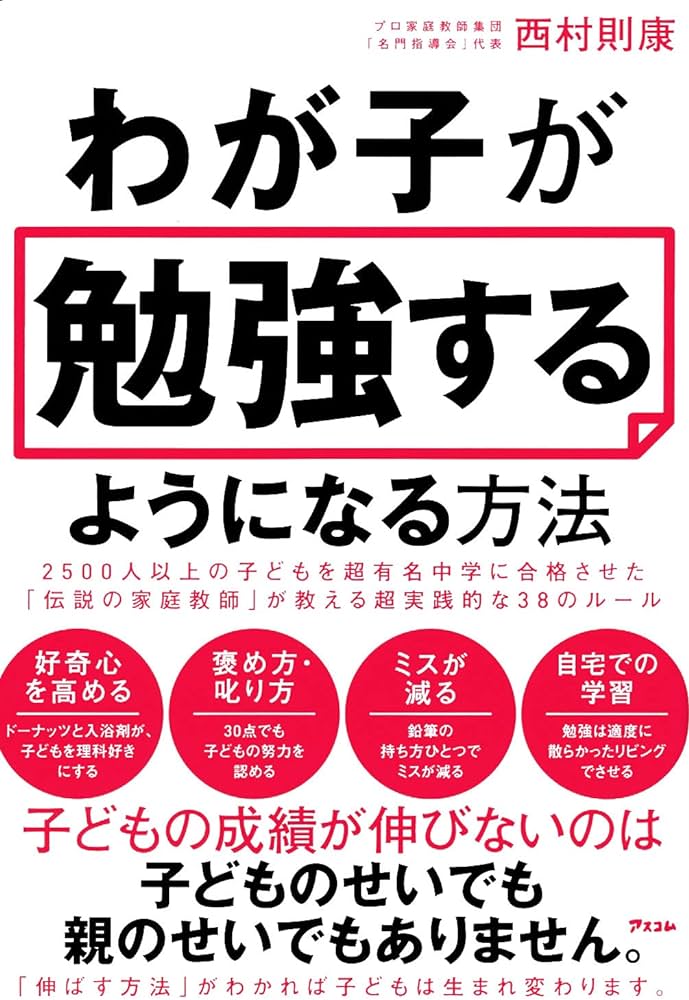
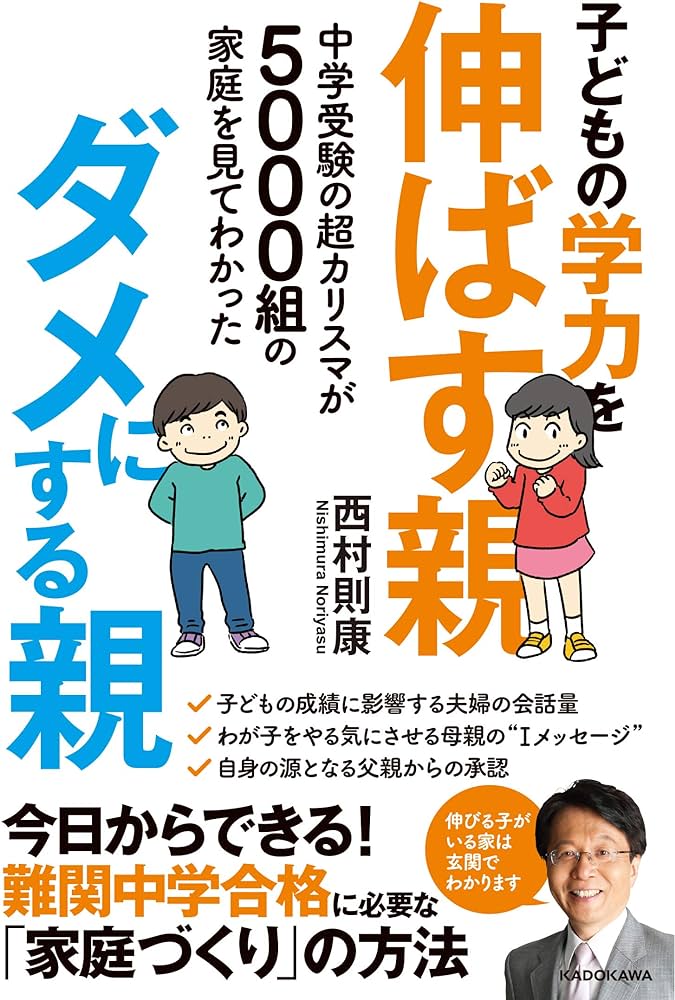
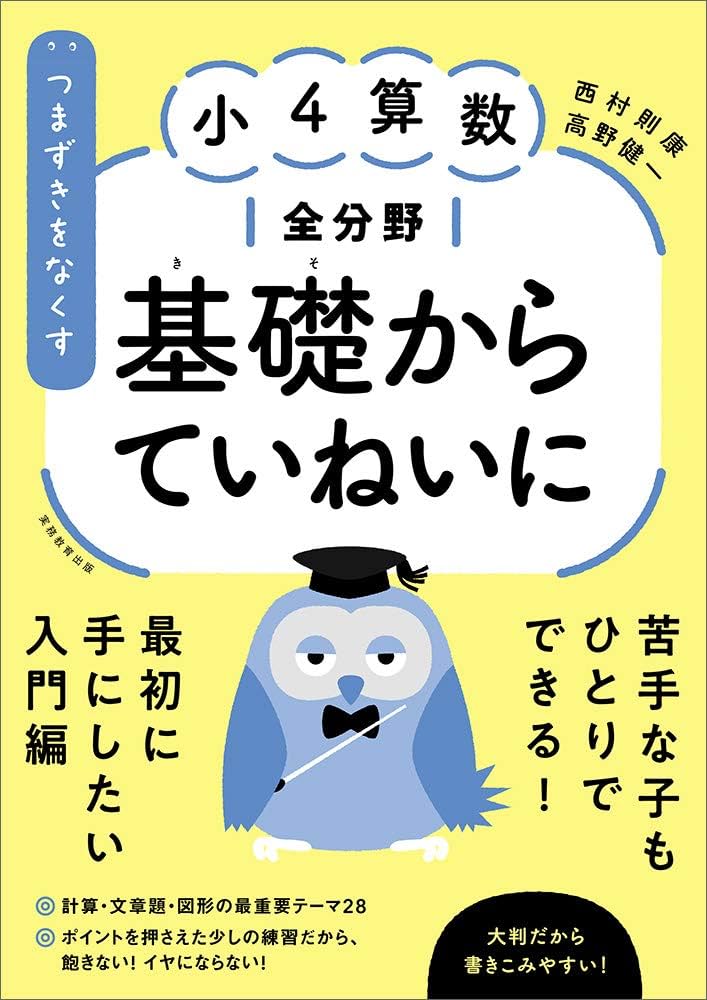
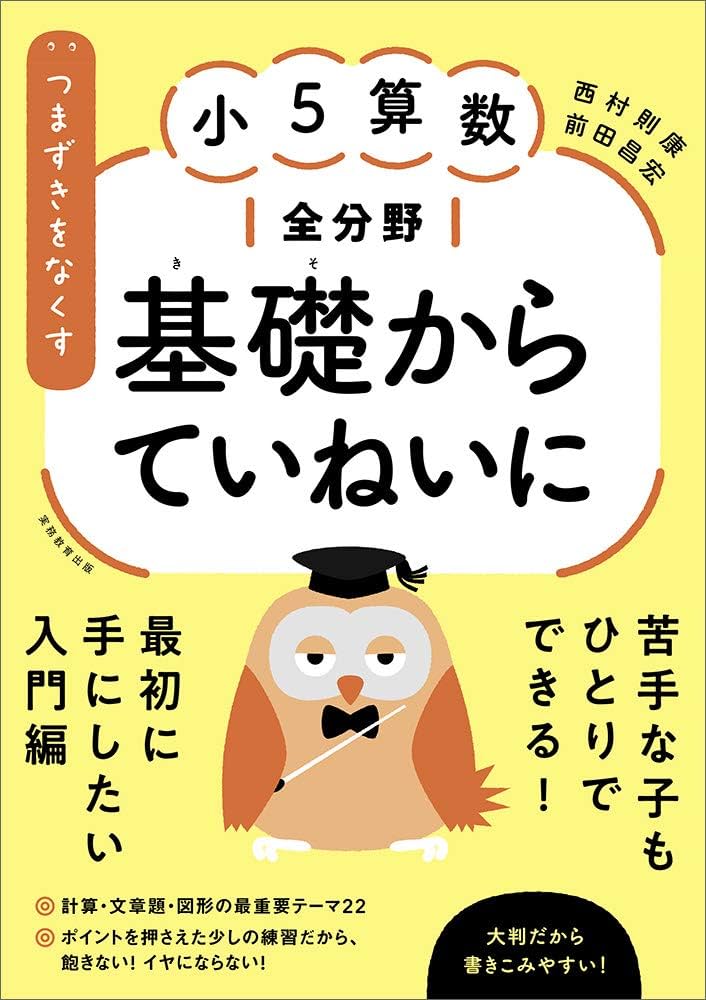
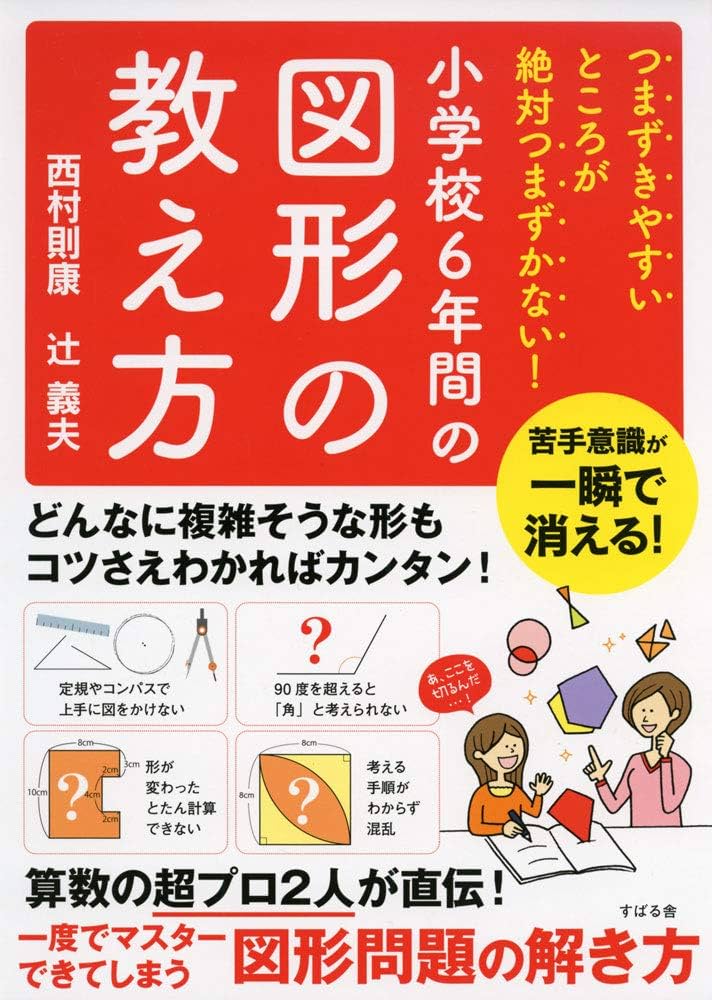
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)