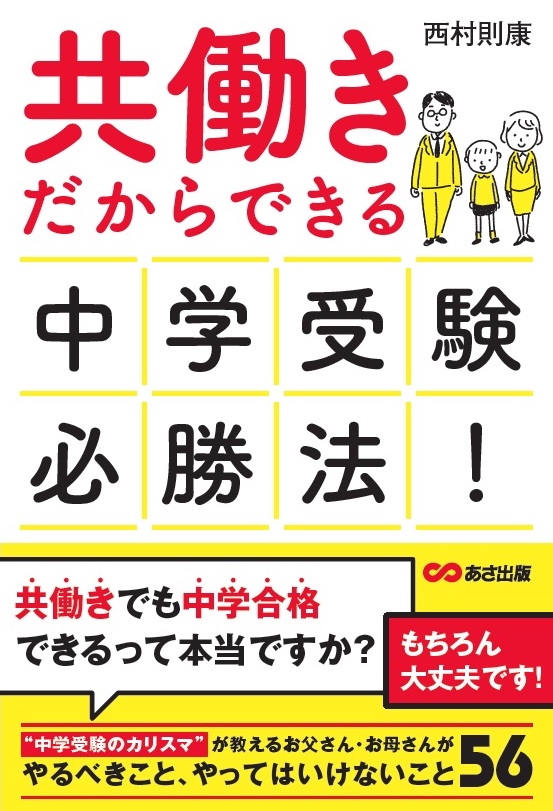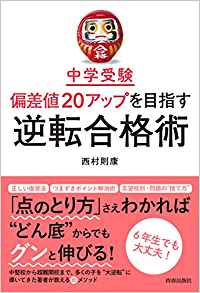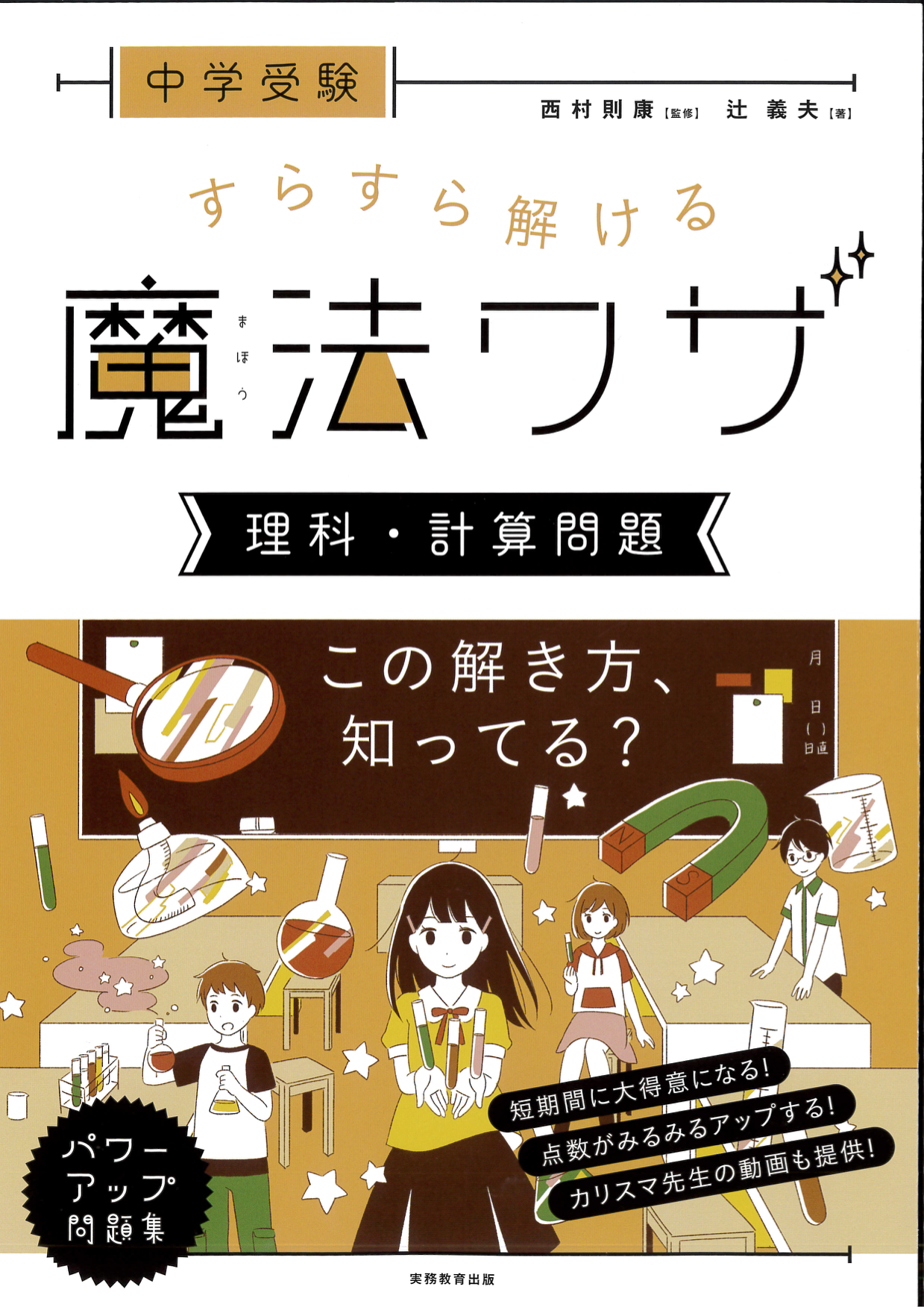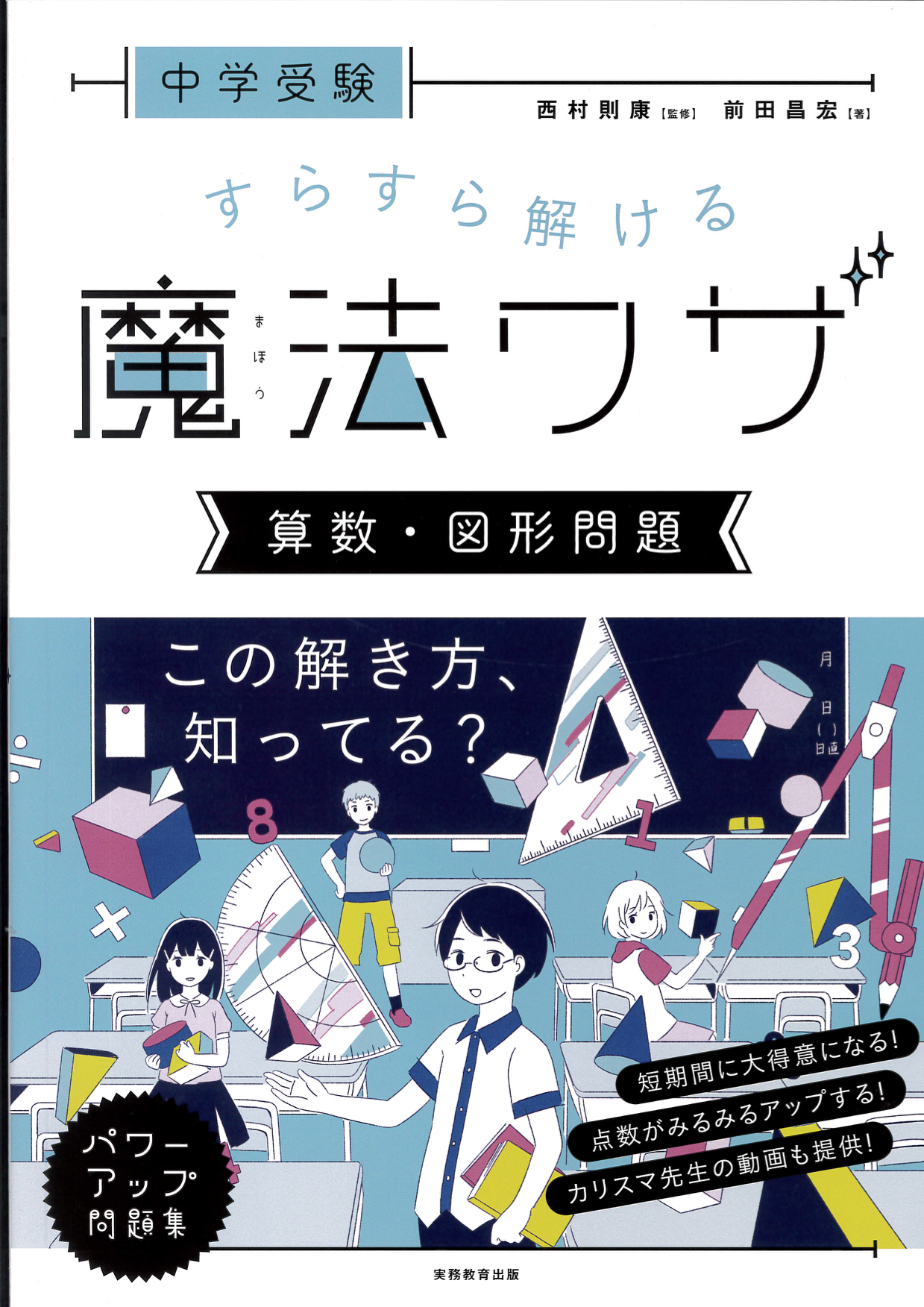目次
受験生の眠気、主な原因は?
6-13歳は大切な成長期
睡眠と休息は堂々と、しっかり取ろう!
★オマケ★ 自分で押せる!眠気に効くツボ
12月も半ばを過ぎ、一段と寒くなりましたね。
東北では雪の日が増え、関東でも日中からダウンを着ている人が増えてきました。
12月は最高気温と最低気温の差が1カ月を通して10度以上あり、日中暖かくても夜はグッと冷え込むことがあります。
帰りが遅くなる受験生の皆さんは、体調管理にますます気をつけていきましょうね。
さて、このように季節が大きく変わる時は、ホルモンの関係で眠気に悩まされやすくなります。
授業中やお家での勉強中にウトウトしてしまい、先生に怒られたり、目が覚めたら何時間も経っていて後悔したり……というのは誰しもが経験する事だと思いますが、眠気は必ずしも「やる気のなさ」など、本人の気持ちが原因ではありません。
そこで今日は、受験生の眠気を引き起こす主な原因と、その対策についてお話ししたいと思います。
受験生の眠気、主な原因は?
特にこの時期、受験生が眠くなってしまう主な原因は大きく分けて4つあります。
①ホルモンや自律神経の乱れ
②慢性的な睡眠不足や疲れ
③精神的な問題
④食事に関する問題
①は前述の通り。
季節の変わり目(特に秋から冬至の頃にかけて)は日照時間がドンドン減っていく事もあり、睡眠をうながすメラトニンの分泌が日中も抑制されにくくなるため、一日を通して眠気を感じやすくなります。
また、激しい気温差により自律神経が乱れる事も原因となります。
➡︎体温調節がしやすい薄手の重ね着を心がけ、いつも快適に過ごせると良いですね。
「◯時間続けて勉強できた!」ということにこだわらず、細めに息抜きを取り入れましょう。
部屋の温度を少し下げるのも、眠気対策には効果的です。
②受験生に限らず、前の日に深夜まで起きていれば、翌日は昼間でも眠くなってしまいがちです。あるいは、常日頃の受験勉強の慢性的な疲れがたまってしまっている場合も眠くなりやすいでしょう。
また、睡眠時間そのものは長くても、眠りが浅いと、やはり睡眠不足になります。
➡︎ 翌日に影響しない時間までで勉強は切り上げましょう。
パソコンやスマホを就寝の直前まで見ていると、液晶画面から強い刺激が脳に伝わって、眠りが浅くなります。
就寝直前は見ないように心がけましょう。
慢性的な疲れには睡眠が一番ですが、身体を捻って血流を良くしたり、一旦教室や部屋から出て冷たい外の空気を吸うだけでも効果があります。
③日照時間が減少していくこの時期は、メラトニン同様、幸せホルモンと呼ばれる脳内物質のセロトニンも分泌されにくく、気分が落ち込みやすくなり、気力も失われ、眠気を感じやすくなります。
➡︎朝起きたら朝日を浴び、冬休みも朝の散歩を取り入れるなど光を浴びられるよう工夫しましょう。
また、学習も苦手なことや単調なことばかり続けていると、疲れたりモチベーションが下がったりしやすくなります。
眠気を感じにくくするには、学習の順番を自分の好きな科目や内容と交互にするのも効果的です。
④食事の問題で眠気に悩んでいる受験生が、この頃意外と多いようです。
食後は血糖値が変化するために、誰しも眠くなりがちですが、特に血糖値の急上昇は強い眠気を引き起こします。
➡︎食事の時間も惜しい気持ちは分かりますが、砂糖や精製された炭水化物(特に菓子パン、清涼飲料水、甘いジュース、お菓子など)を食事の代用とするのはなるべく避けましょう。
これらは糖質が多く消化吸収が速いため、血糖値を急激に上げてしまいます。
コンビニなどでは1本のスティックやドリンクで十分なカロリーが摂取できると謳っているものも多々ありますが、それらを食事とする場合は、栄養素もしっかり網羅されているものを選びましょう。
糖質だけが多いものは、同じ現象を引き起こしてしまうので注意が必要です。
また、食事の順序としては、サラダなどの野菜、メインのたんぱく質(肉や魚)、主食の炭水化物(ご飯やパン、麺)の順に口にする様にしましょう。
ゆっくりよく噛んで食べるのも効果的です。
6-13歳は大切な成長期
中学受験生は宿題や課題に追われ、どうしても睡眠時間が短くなりがちです。
けれども連日睡眠不足でウトウトしながら授業や課題に取り組んでいるようでは集中力が保てませんし、学習効果も半減してしまい、本末転倒ですよね。
そして、中学受験に臨むための数年間は、皆さんの心と身体を育む大切な成長期でもあります。
6~13才の成長期に必要な睡眠時間は約10時間と言われており、睡眠不足がその一因と考えられている「キレやすい」子どもが増えていることも問題になっています。
受験勉強ももちろん「今しか出来ないこと」ですが、皆さんの心と体の健康のためにも、睡眠はしっかり確保しましょう。
睡眠と休息は堂々と、しっかり取ろう!
睡眠不足は、百害あって一利なし。
学習の関係で時々就寝が遅くなるくらいは問題ありません。
しかし、たとえ追い込み期であろうとも、睡眠をしっかり確保して学習に取り組む方が実は効率的だということは、ぜひ覚えておいてください。
また、受験生には睡眠と同様、休息もとても大切です。
大人にも休息が欠かせないように、身体も心も幼い10代前半の皆さんには、なおさら適度な休息が欠かせません。
過度なストレスや疲れにより、集中力にも体力にも精神力にも悪影響が出てしまう前に、少なくとも2時間に1度はしっかり休息をとりましょう。
勉強の合間に家の周りを散歩したり、お茶を飲んだり、ストレッチをしたり、15分ほどの仮眠をとるのもおすすめです。
睡眠や休息は恥ずかしいことでも、悪いことでもありません。
蓄積しきってからではなく、そうなる前に、こまめに息抜きや睡眠を取りましょう。
中学受験生の皆さんに必要な睡眠時間は、一般的には前述の通りですが、ひとりひとりに合った時間はそれぞれです。
皆さんにちょうど良い睡眠時間を確保できるよう、起床時間から逆算し、なるべく毎日決まった時間に布団に入るようにしましょう。
受験勉強に励む皆さんが、12月を元気に乗り切れるよう心から応援しています。
★オマケ★ 自分で押せる!眠気に効くツボ
◯耳(ほぐす)
◯中衝(ちゅうしょう。手の中指の爪の生えぎわから3mmほど下の部分。指で上下から挟んで押す)
◯清明(せいめい。目頭の内側、鼻骨の上あたり。つまむ様に優しく引っ張る)
これらは眠気に効くと言われているツボです。
眠いけれど、すぐに場所を変えるなどの対策が取れないときは、これらのツボをその場で軽く刺激してみましょう。
中衝にはリラックス効果、清明には目の疲れを解消する効果もあるので、ぜひ試してみてくださいね。

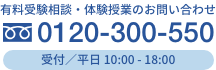




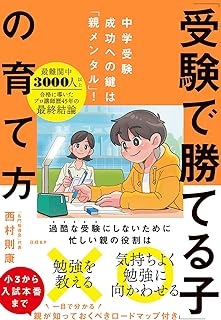



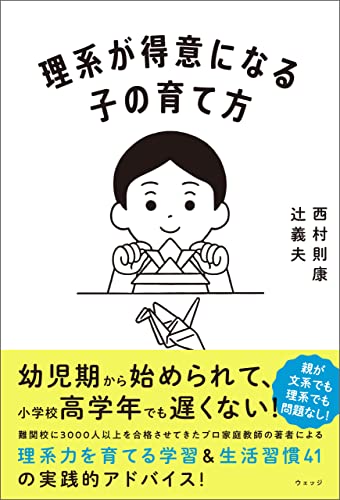




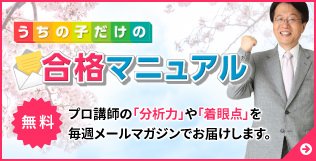



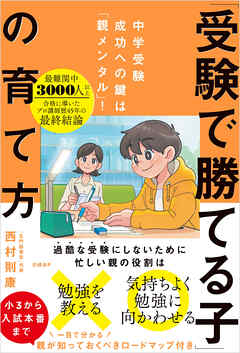
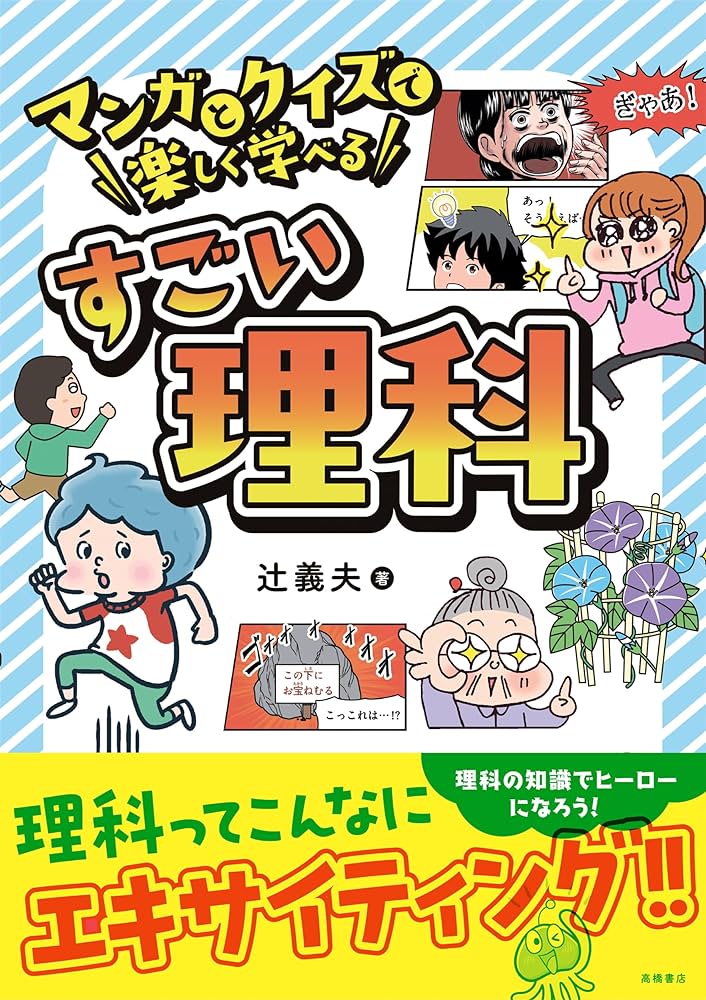
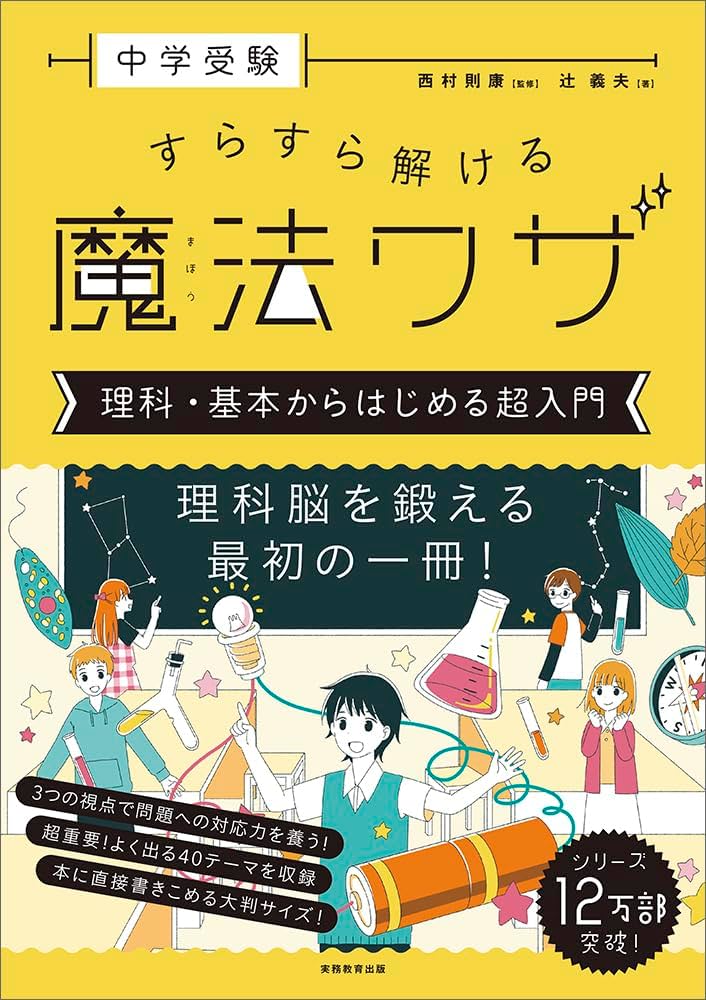
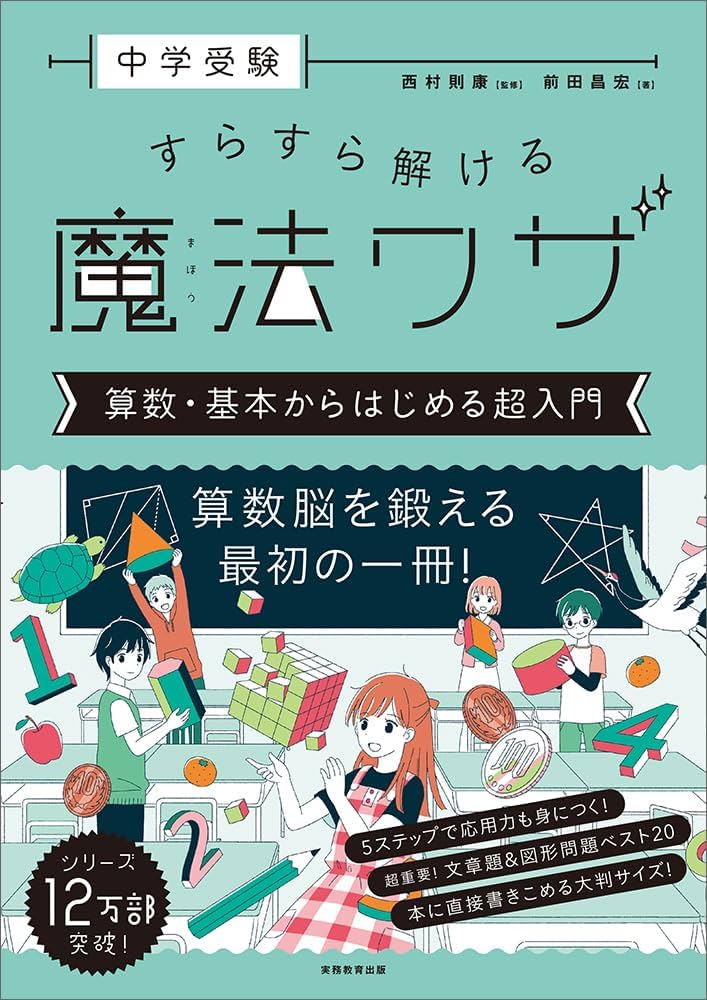
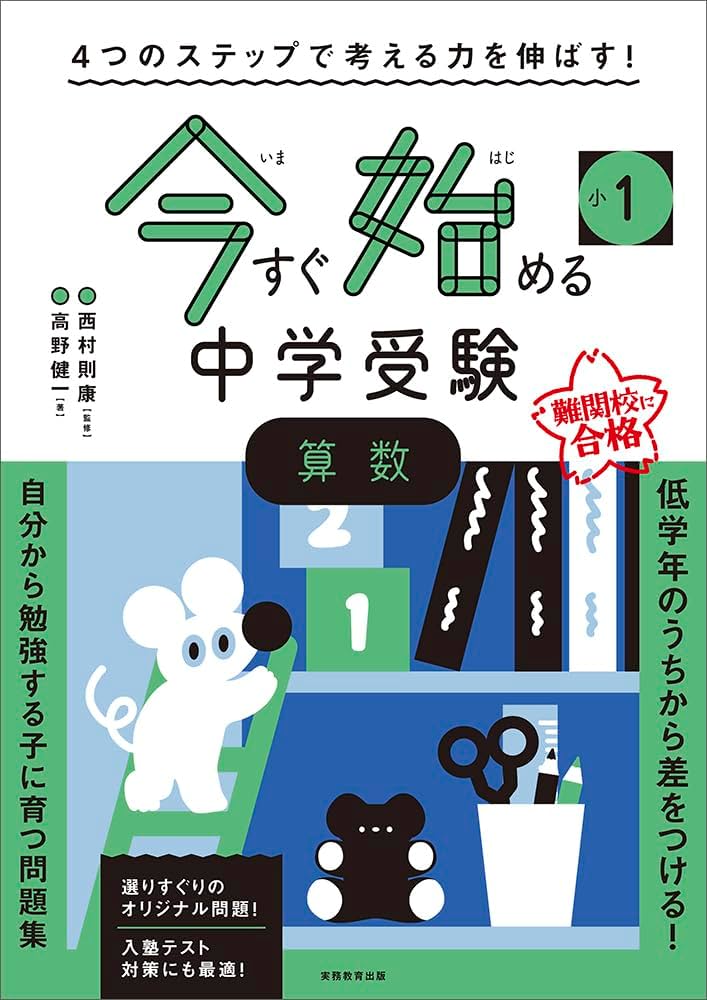
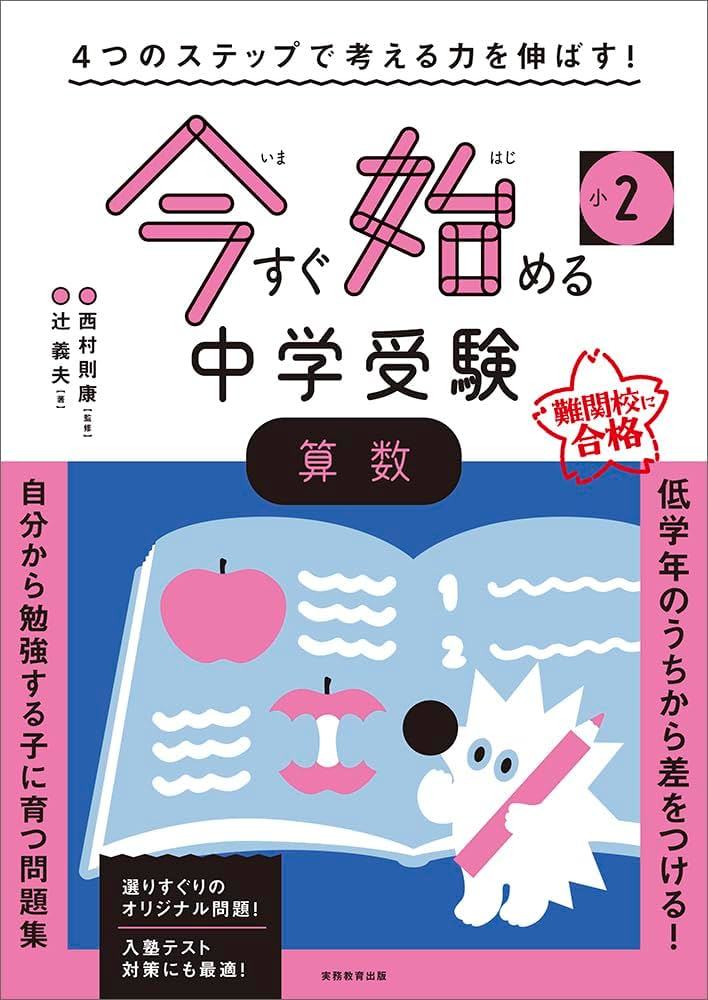
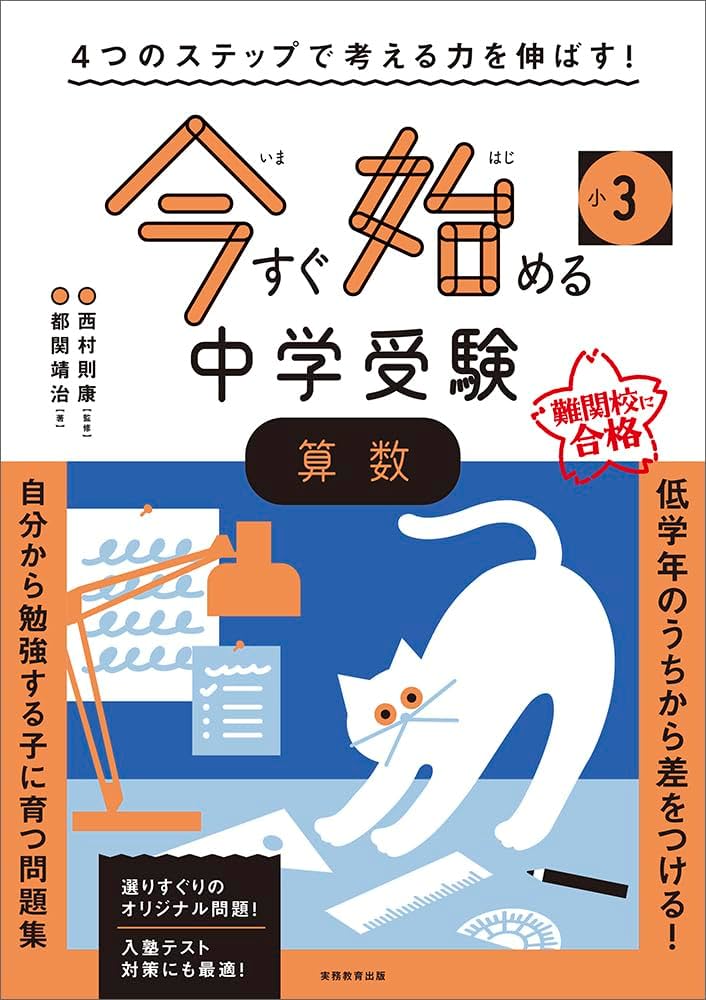
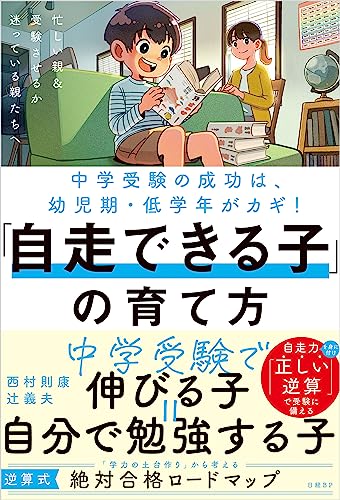
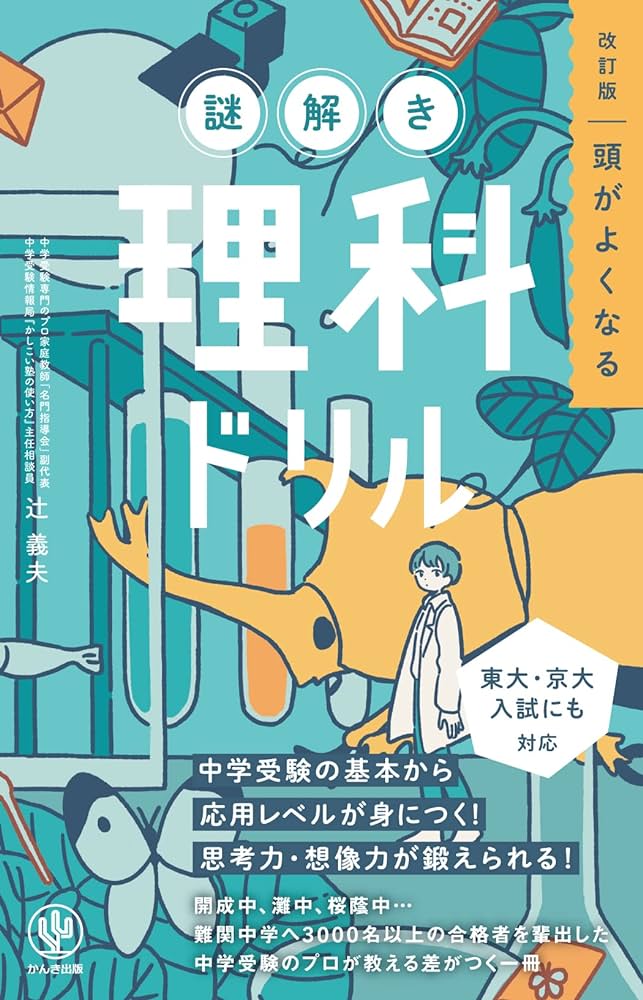
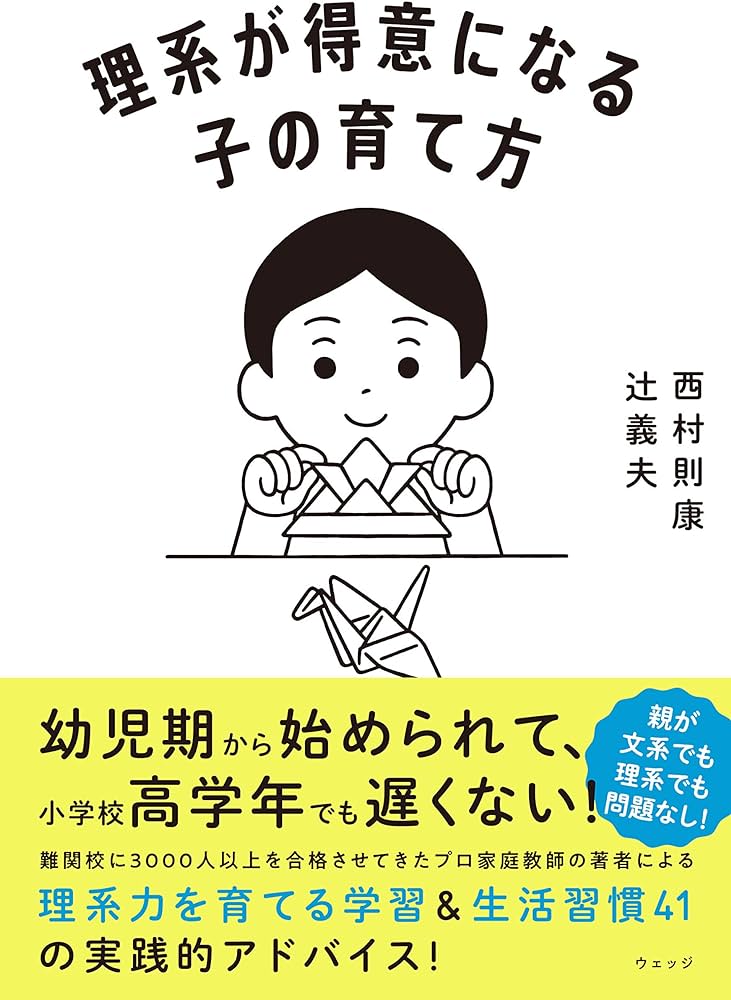

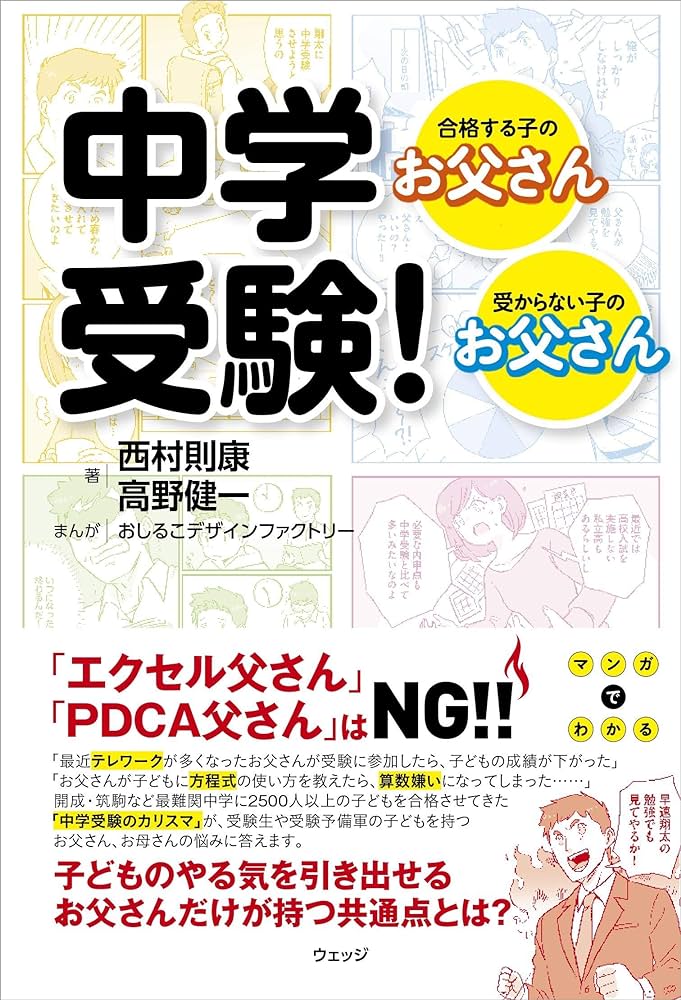
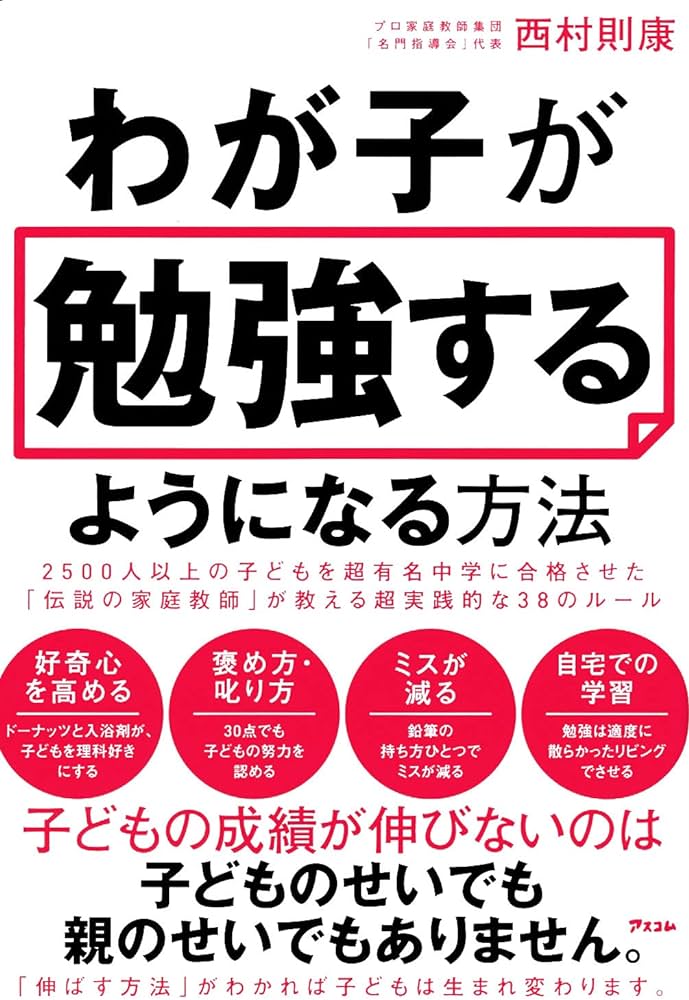
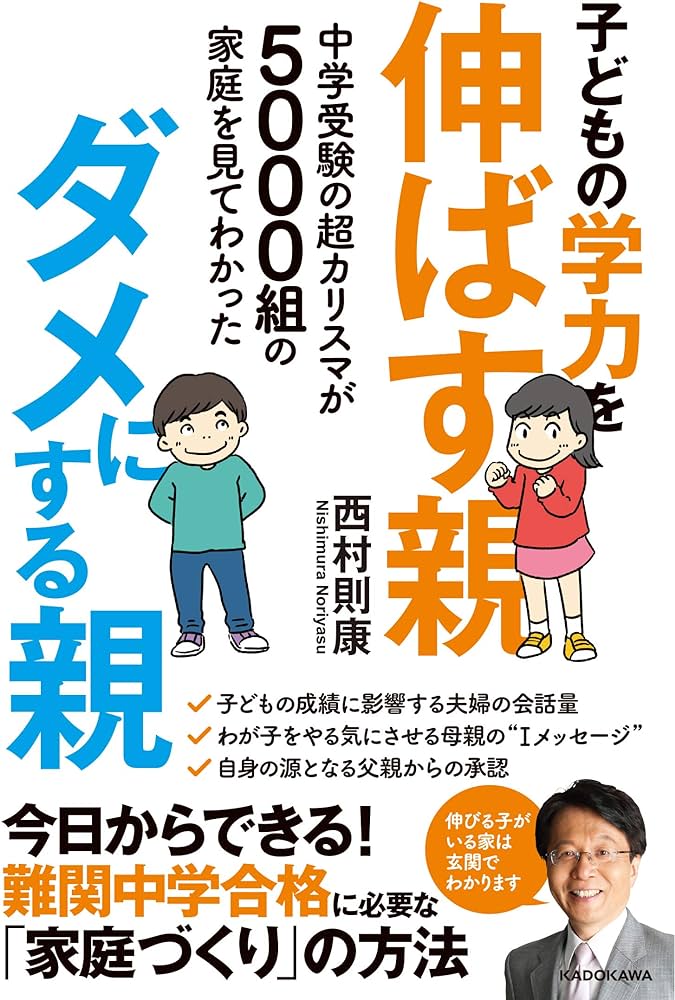
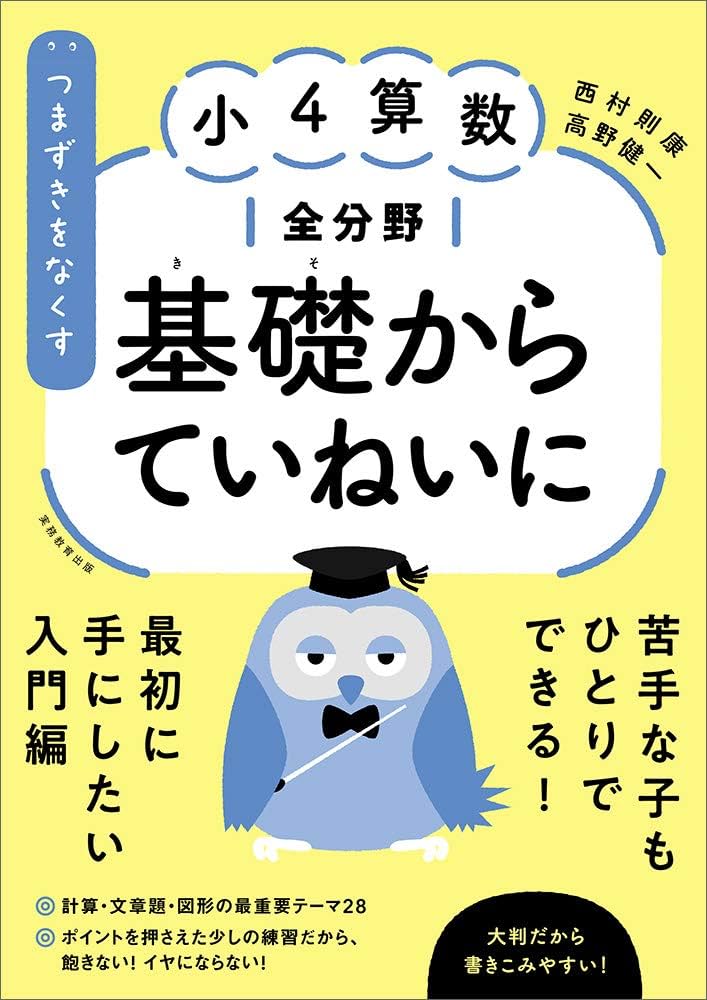
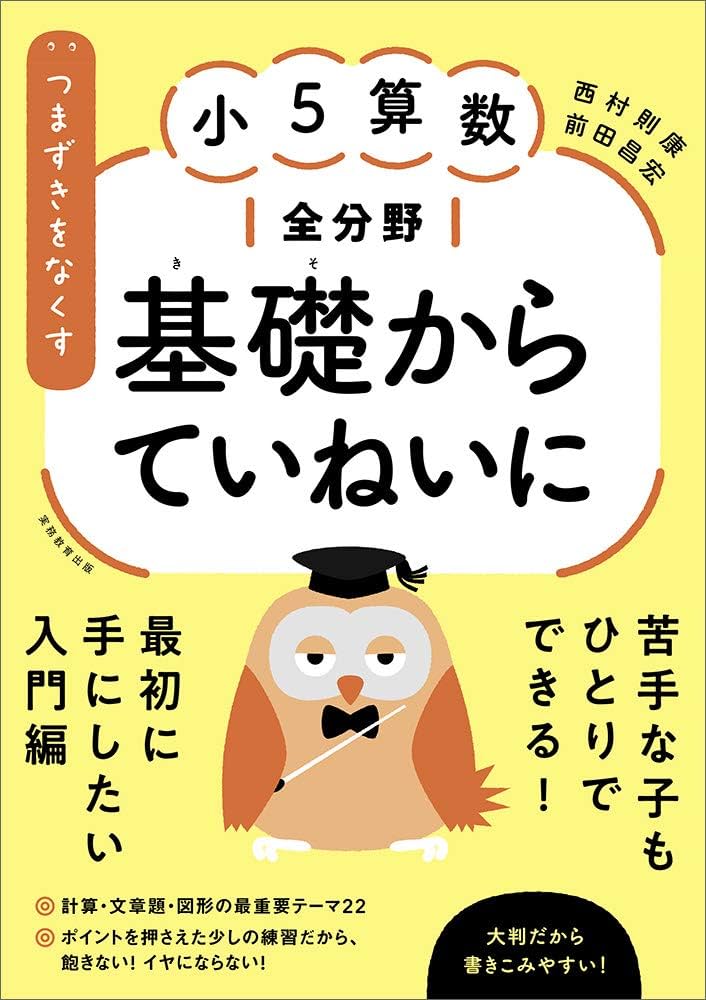
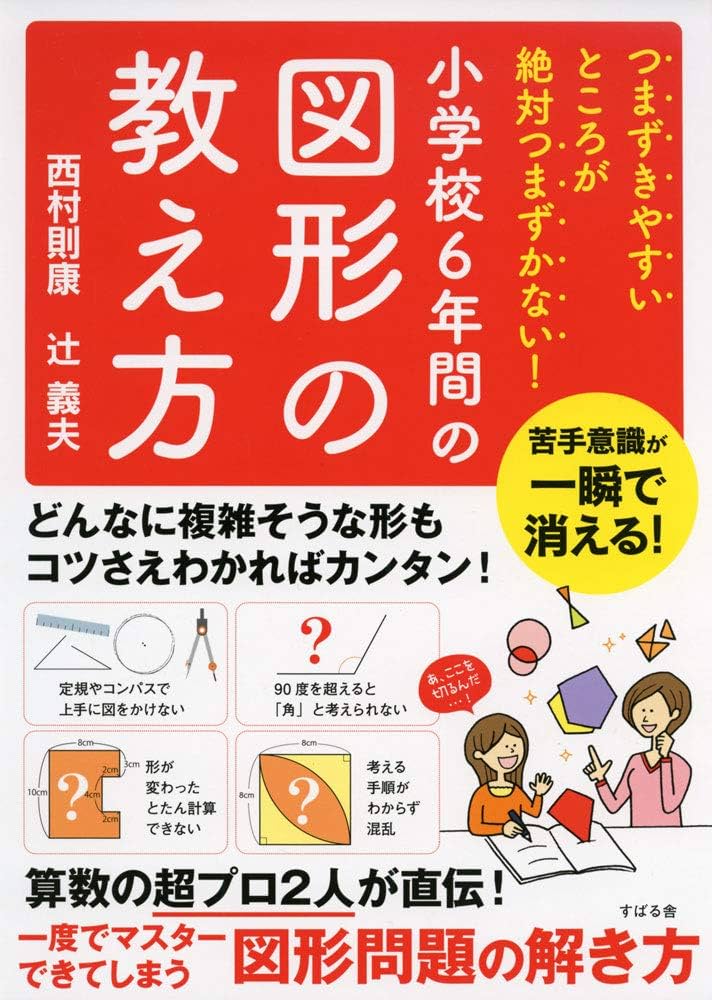
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)